映画『見はらし世代』以前と以降。
もしかしたら、この映画は後に事件として語られるのではないか。そんなことを思いながら、映画館の座席で団塚唯我監督の長編デビュー作『見はらし世代』を見ていた。
団塚唯我は現在27歳。この映画の撮影時は26歳だった。しかし、僕は確か2020年のなら国際映画祭の学生部門であるNARA-waveで団塚監督の映画美学校卒業制作『愛をたむけるよ』を見ている。この時から、彼の才能は群を抜いていた。そして、文化庁が若手の映画監督を育てるために出資して、プロのスタッフと共に30分以内の短編を完成させるNDJCにおいて制作した『遠くへいきたいわ』が前作を上回る強さと美しさを手に入れていて、驚かされたのだった。
そこから、彼は着々と準備を進めて、満を持して『見はらし世代』を世に送り出した。すでに海外ではカンヌ映画祭の監督週間に選出されるなど高い評価を得ている。その評価の新しいうちにということなのかもしれないが、バタバタと日本公開が決まった印象がある。まだ、十分に宣伝も行き渡っていないという中での公開は正直、残念な気がする。
だって、この映画の新しさは、新人とかベテランとか関係なく、自分の見たい世界をしっかりと作品として定着させるという、実は当たり前のことが日本ではとても希有だったことを教えてくれる。誰かが少し毛色の違う脚本を仕上げても、現場のベテランたちが、寄ってたかって、見たことのある、安心できる作品に仕立ててしまうのが日本の現場だ。監督もそれに抗える者なんてほんの一握りしかいない。
結果、トラウマを抱えた主人公が事件を起こし、それを見守っていた誰かと心を通わせ、きっと誰かが見ていてくれるんだよ、という承認欲求を満たすような結末を迎えて、そこに弱々しいピアノ曲が流れて、はい、お終い。
『見はらし世代』の新しさは、ちゃんと自分の見たい世界をスタッフと共有して、一緒に最高の作品にしようとあがいた結果が、しっかりと定着されているという点だと思う。だからといって、若い世代にしかわからない映画ではない。でも、年寄りが「若いっていいね」と笑っていられる映画でもない。
例えば、映画を撮りたいと願う人に対して、この映画は「あの、才能がなくても続けますか?」と喉元にナイフを突き付けてくるような緊張感がある。
ラスト近く、あまりストーリーに関係なくLUUPに乗る若者たちが登場する。今どきの若者をラストに見せるのか?という気持ちになったのだが、それは最初だけ。彼らの会話を聞いてる間に、どんどん自分も「わかればLUUPに乗るのになあ」と思わせてくれるのだ。そして、同時に、「でも、おれ、ケガする気がするから辞めとく」と言わされてしまう。
団塚唯我は、はっきりと意志提示をする。そして、「オレはこれが好きなんだよ」と僕たちに話しかけてくる。ただ、その話題があまりにもまっすぐで、正直なので、僕はなんだかはっきりと答えられずにモゴモゴとしてしまう。そのモゴモゴを許すような凡百の映画が多い中で、『見はらし世代』はそれを許さない。
団塚唯我の登場と『見はらし世代』の公開は、事件だと思う。何年か後に、きっと『見はらし世代』以前と以降で、日本映画は語られるはずだ。
この『今』としか言えない感性と、日本にしか生まれなかったはずの家族観や道徳観に裏打ちされた作品は、はっきりと小津安二郎の系譜と言える。もちろん、団塚唯我が小津を意識してるかどうか、好きかどうかなんて関係ない。「小津監督に影響されました」なんて気軽に言葉にできるような話ではなく、映画としての系譜の話だ。
いや、僕がいま言っていることが正しいかどうかは正直わからない。でも、劇場公開された今この映画を見ないと後できっと後悔する気がする。映画に興味があるなら、ぜひ、見てください。お願いします。団塚唯我と出会ってください。僕の教え子でも何でもないけれど、日本映画のちゃんとした系譜の中に生まれた、まったく新しい才能をぜひ見届けてやってほしい。この映画が仮に興行的にこけて、団塚唯我が次の作品を撮りにくくなるなんて、日本映画だけじゃなく、世界の映画の損失になってしまうから。
僕もあと何回か必ず見ようと思います。みなさんも、ぜひ、見てください。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松眞人(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。



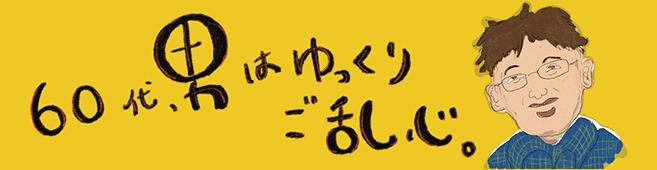

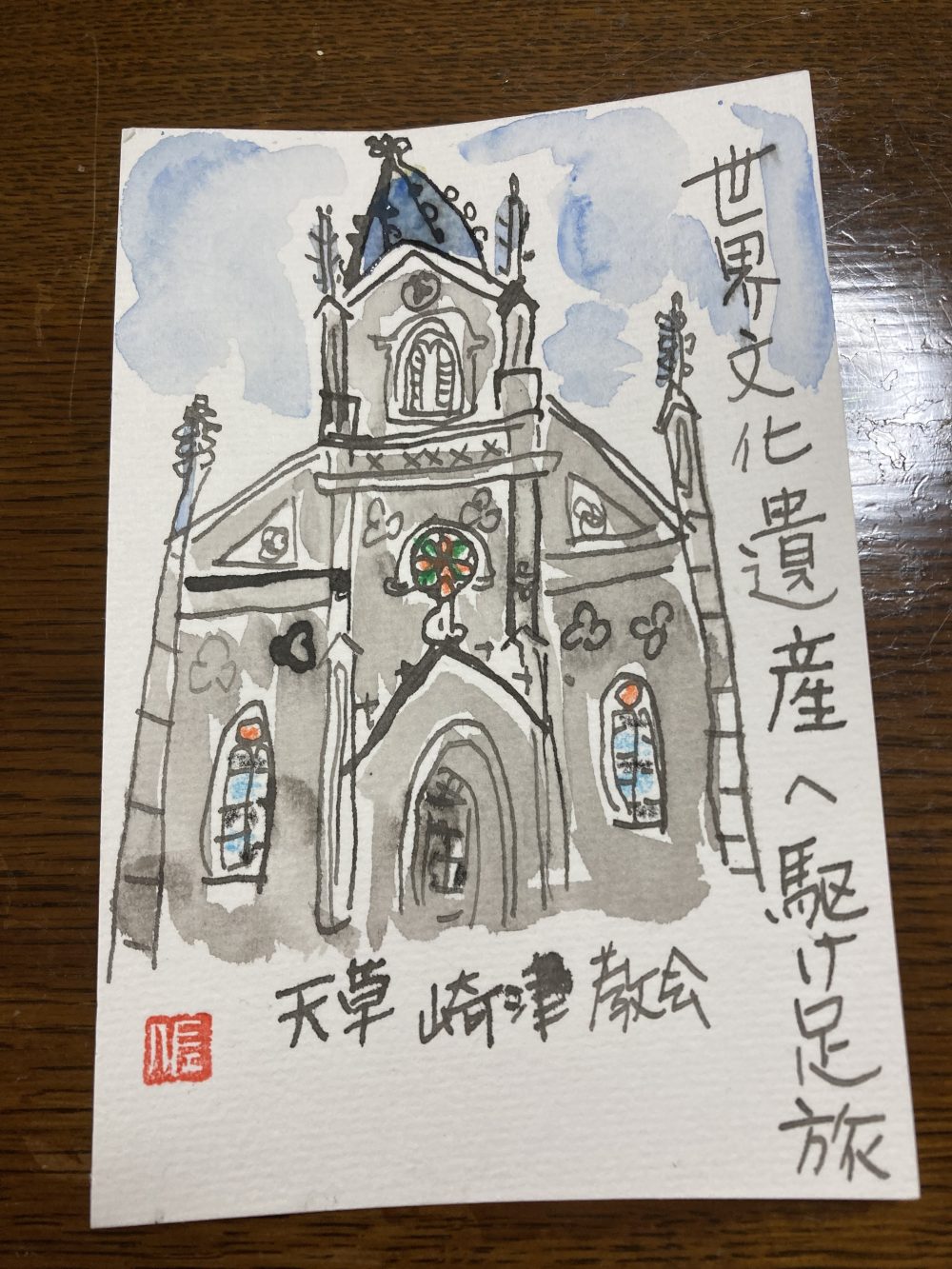

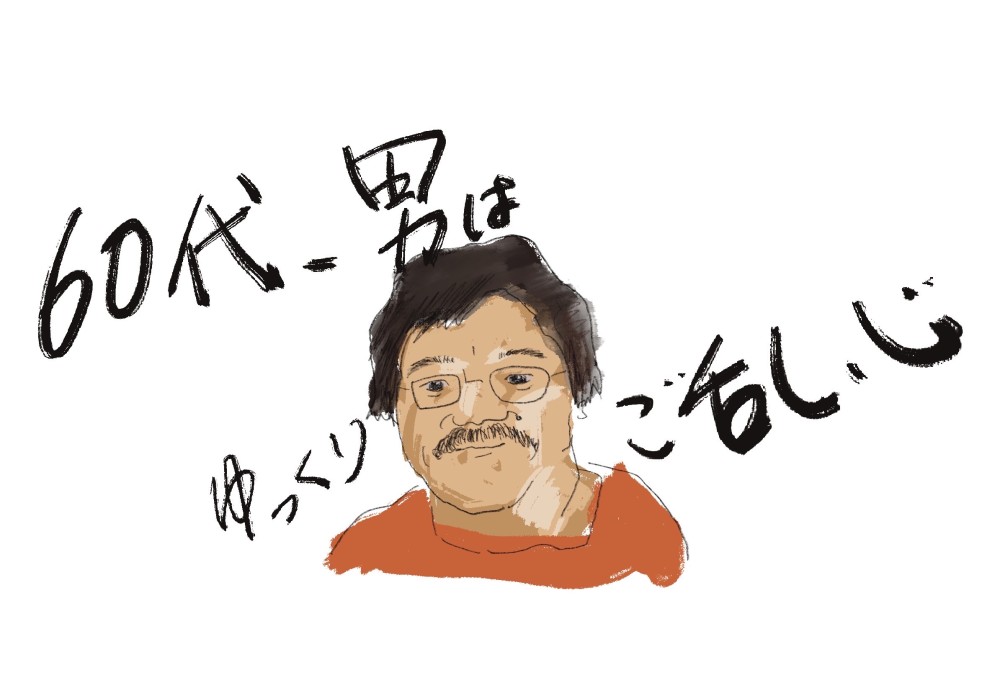
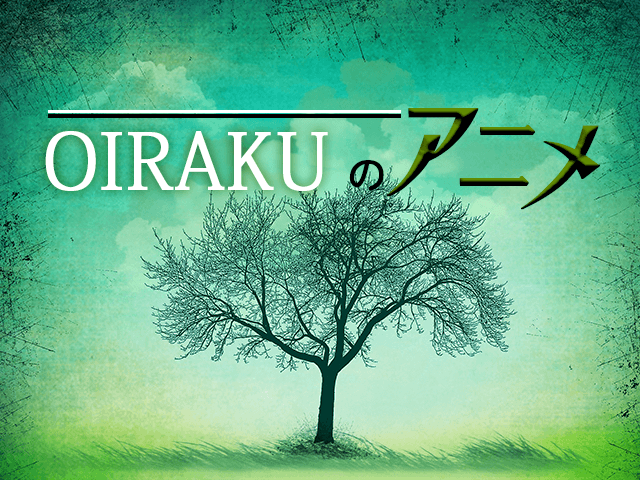


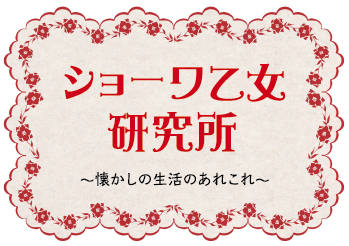

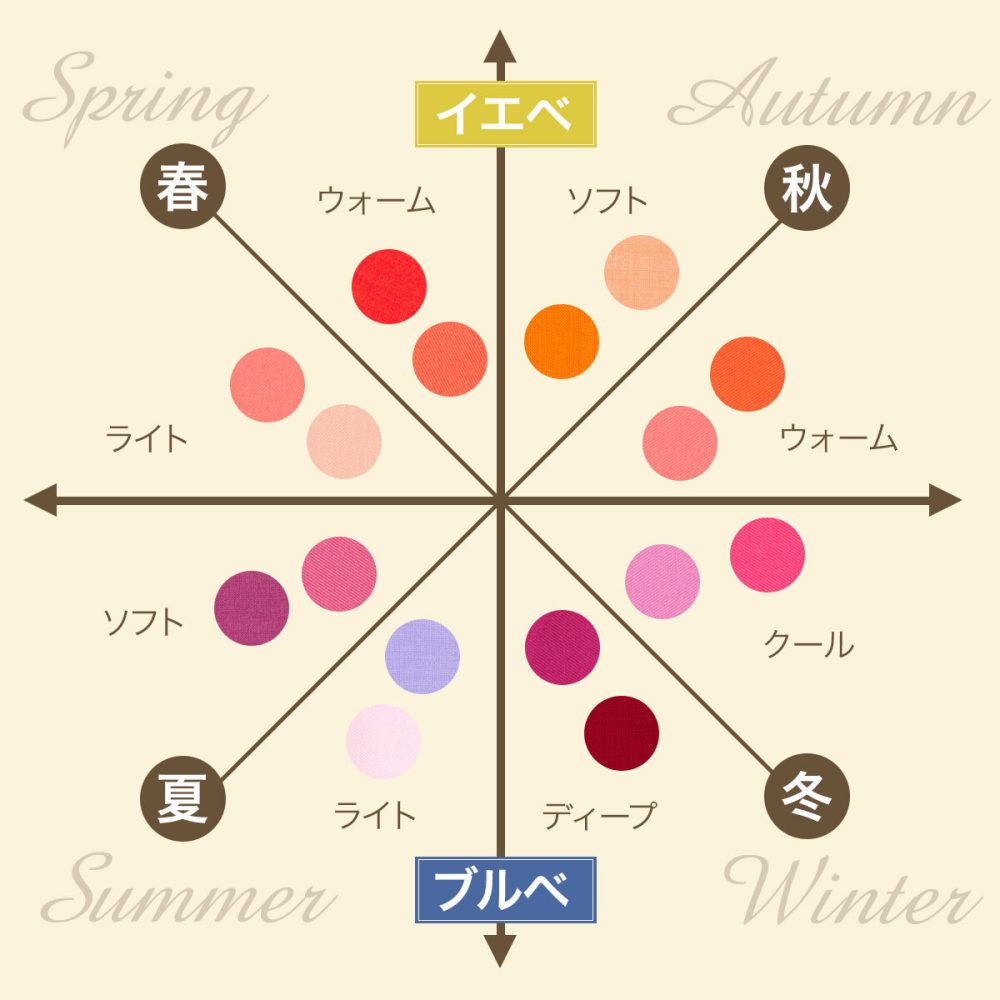
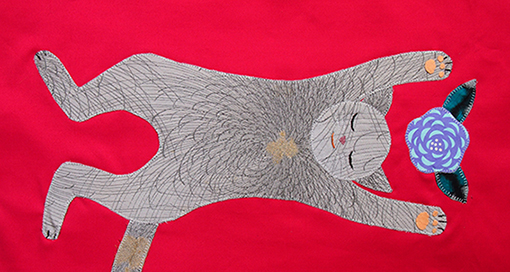






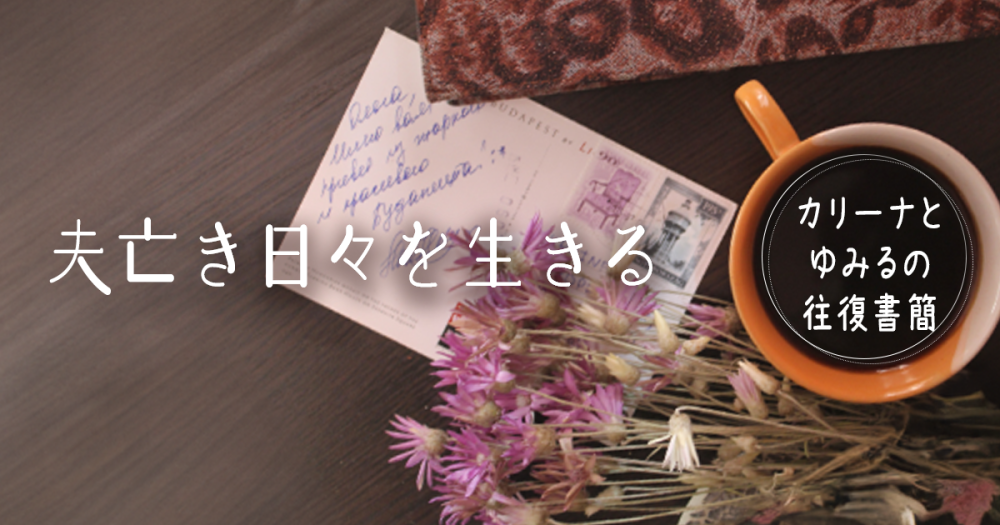
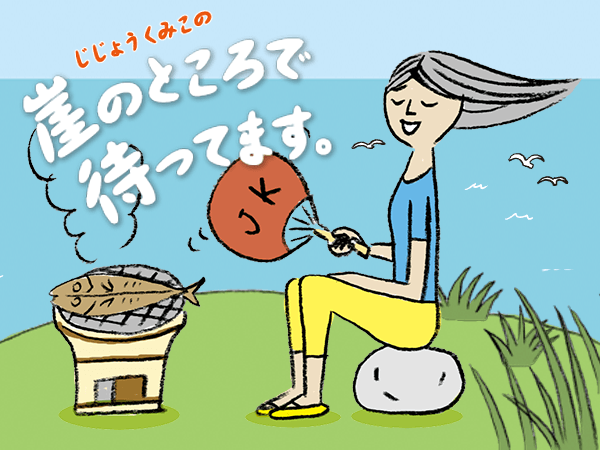

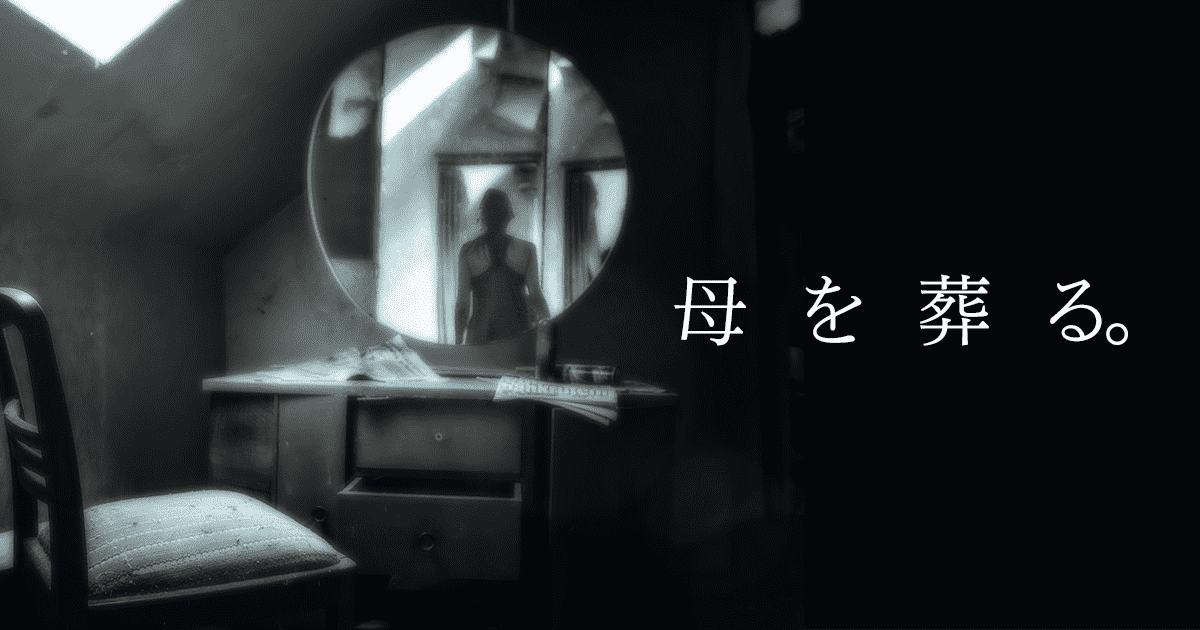


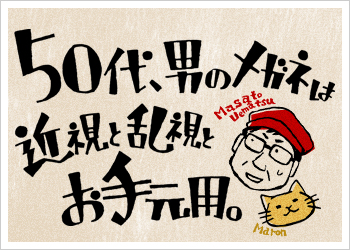









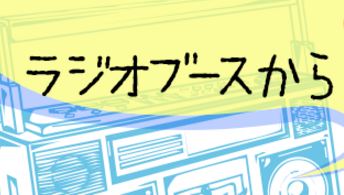








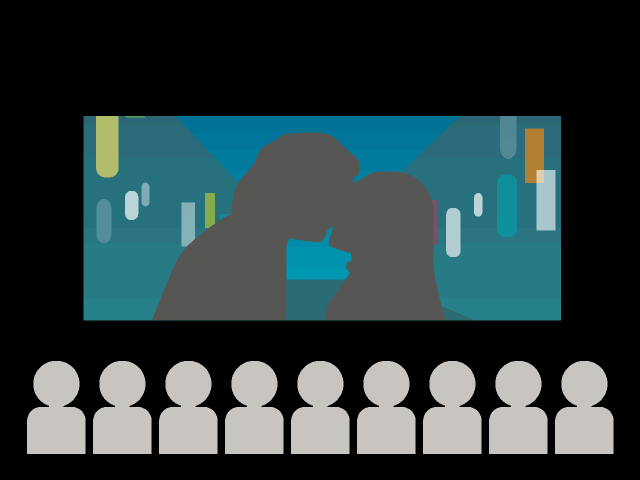
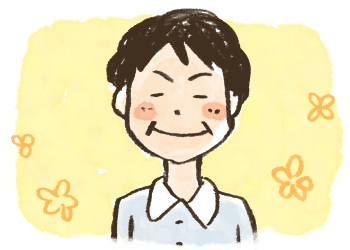
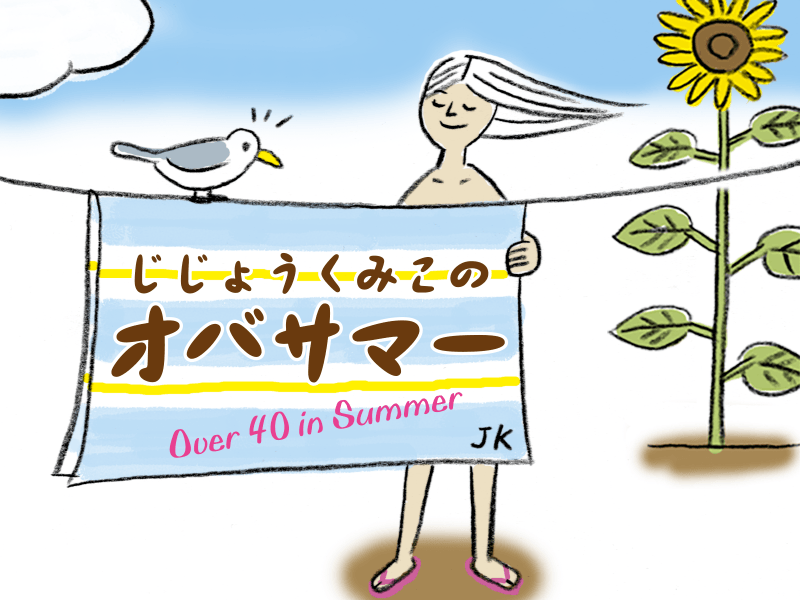





















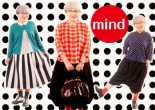

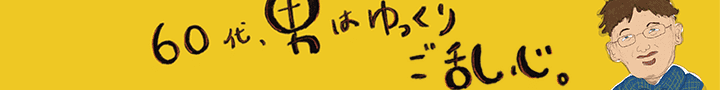


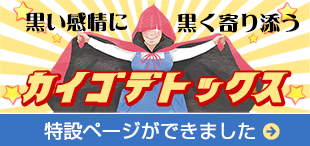


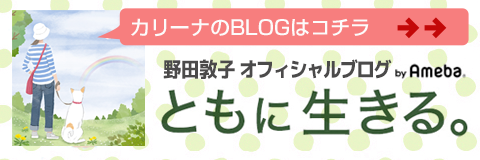
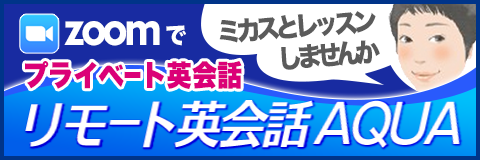
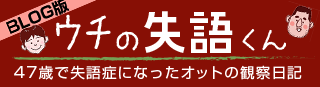
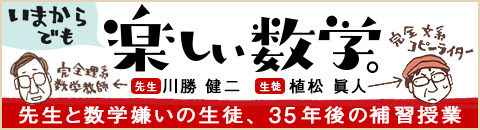

なな
数年前に黒澤映画を劇場で鼻息荒く観に行ってた息子を持つ母です。あれから映像関係の大学へ進み、制作のために多忙な日々を送っています。この映画は先輩からもおすすめされ、是非観に行きたいと言ってます。でも観に行きたい映画が多くて、時間もお金も足りないとのこと。優先順位難しいですね(^^)
uematsu Post author
ななさん
これは、ぜひ見たほうがいいと思います、とお伝えください。
黒澤映画のスペクタクル感はないですが、今を生きる人たちの出会いとか別れとかすれ違いを描いた作品として、本当によくできていると思います。
もし、見た時に「そんなに面白くない」とか「ピンと来ない」と感じても、きっと後から、あの時、見ておいて良かったと思ってもらえるはず。
と、僕は信じております!
ほんと、僕の勘でしかないですけど。