(16)一枚の絵
母が私の夫の鬱をあんなに嫌がったのは、道具である娘の価値が下がるからだと思っていたが、単に、自分の鬱を想起させるから、ということもあったのかもしれない。萩尾望都の『イグアナの娘』みたいに。
自分がイグアナだったことを隠していたのに、生まれた娘がイグアナだった(彼女にはそう見える)ので、バレてしまうと恐れて娘を邪険にする母親。私の母にとって、自分が何年も入院していたことは「黒歴史」だっただろう。その「黒歴史」が娘の配偶者として目の前に蘇ったのだ。
もちろん、カウンセラーなら必ずこう指摘するだろう。私がそんな人を配偶者として選んだのは、母の面影を追っているからだ、と。
虐待された人は虐待された経験しかないから、それ以外を知らない、だからよく知っているものを選んでしまうのだそうだ。急に具合が悪くなって陰鬱とした顔つきで寝ている夫の様子は、幼い日に私が目にしていた母の様子とそっくりだった。
とすると、私は母を癒す行動をしたくて、夫を選んだ、とも考えられる(なんて健気!)。
さらに言えば、私は母にとって天使だったのではないか?(突然何を)
私が、鬱で無職になった夫を否定しないということは、鬱で何年も入院し挽回するために何者かにならなければと必死になっていた母にとって、福音だったはずだ。本来は。何者かになんてならなくていいのだ、ありのままでいいのだ、と娘が肯定するのだぞ。しかし母にはそうは思えなかった。なんと、もったいない。それこそ神から授かったものであったろうに。
母の日記に一貫して書かれているのは、自己否定だ。自分はできそこないだ、優秀ではない、誰かに負けている、愛されていない、充実していない、幸せではない。不幸をぬぐうための道具である娘は、道具として機能しない、ますます不幸だ。
20代の母の日記には、詩や絵のほかに、戯曲の断片が書かれていた。何度も何度も書かれる戯曲の設定はいつも同じで、丘の上に建つプチブルな家庭、両親と三人の子、そして蔑まれる女中。あれ? 母は四人兄弟だったはずだが? なんと、主人公はいつも女中なのである。戦慄! やはり母は、自らを家族の中で一段下の人間だと思っていたことがわかる。
祖母はおそらく、ほかに取柄のない母に同情して、「お前は勉強ができる」と言い聞かせたのだろう。母はそれをよすがにし、自分は勉強ができる、特別な人間だと思いこもうとした。しかし、それは厄介なプライドをもたらしただけだった。
高校卒業時に、祖父への反発で家出をしたとは聞いていた。祖父の仕事は確かに、ベトナム戦争に反対していた母からしたら許しがたいものであったため、反発したことは容易に理解できる。しかし、家出をするほどだろうか? 当時の日記は現存せず、20代の日記を読んでも詳細は分からなかったが、ひょっとしたら祖父への反発そのものではなく、それをきっかけに家族から孤立したことが耐えられなかったゆえの家出だったのかもしれない。
いずれにしても、家族の中で自らを卑下する一方で、変に高いプライドを持ち(それらは表裏一体)、破綻から生じた鬱で何年も入院し、ますますドロップアウトした自分を肯定することなどできなかった。納得のいく仕事には就けず(これはプライドの高さのせいでもあるし、社会のせいでもある)、残された道は結婚のみ。結婚相手に贅沢は言えないと妥協。そんな相手との間に生まれた子どもは、やはり不良品。
できそこないは生きていてはいけない。自分ができそこないではないことを証明しなければ。人より上に位置しなければ。称賛されなければ。でもそうならない。なぜ。本来優秀で特別な人間であるはずなのに、できそこない扱いはなぜなのか。不遇だ。ひょっとして自分は優秀でも特別でもないのではないか。できそこないなのではないか。暗澹。いや、そんなはずはない。証明しなければ。
勝手に細い筒を作って、その中で上へ上へと無茶なボルダリングをしているようだ。ステータスの獲得に必死になっている。ほんのちょっとしたことでも上に行かなければならないと思い込んでいる。上に行けない自分を認めることができないから、下を見下すことでなんとか筒の壁面にしがみついている。
筒なんて、本当は存在しないのに。ただのフラットな地面なのに。
仕事で新しい知識を得たり、いろんな国の人と知り合ったりしただろうに、それでは全く満足できていない。幸せの基準が、自分がどう感じるかではなく、他人に賞賛されるかどうか、だからだ。 自分が死んでいくことを認められなかったのは、こんな人生では落第だ、このままでは死ねない、と思っていたからなのだろう。
何より驚いたのは、(これを書くことには非常に抵抗があるが、あえて書く)20代の母には複数の男性遍歴があり、旺盛な性欲を持ち続けていたことだ。なんと! 私が色気づくのを嫌悪していたのは、一体何だったのだ!? 自分の中のそうしたものを認めたくなかったということなのか??
私は子どもの頃から、山岸涼子の、女性の性を悲しきものとして扱う作品(『妖精王』とか)を好きだったのだが、それは母の抑圧を感じ取っていたからだったのだ…! 信田さよ子の本には、自らのミソジニー(女性性への嫌悪)にとらわれて娘につらくあたる母親たちが多数登場する。社会全体の(現代よりもさらに強い)女性差別を内面化して自らを嫌う女性たち。GHQの兵士に群がるパンパンを嫌悪していたのは、自らにそうした部分があると感じていたからだったのだ。
突然思い出したのだが、子どもの頃、テレビか何かで見かけたマリリン・モンローを母が褒めたので、本屋で写真集を見つけたとき母に「買おうよ」と言ったところ、「汚らわしい」と猛烈に怒られたことがある。「ついこないだ褒めてたのになぜ??」と本当にびっくりした。そうしたものへの憧れや衝動と嫌悪が混在していたのだろう。
母よ(と、はじめて呼び掛けてみる)、今は女性もストリップを観るようになったんだよ、女性の裸体によるパフォーマンスは素晴らしいよ。
「ネガティブケイパビリティ」という言葉を思い出した。ネガティブなことへの抵抗性、耐える力。母は、娘が授業参観で手を上げないだけで、おしまいだと思ってしまう。子どもが自然に成長するのを待つことができない。自らの過去を思い出させる人物(娘の配偶者)を毛嫌いする。自分の女性性を認められず、目の前のパンパンや、娘の女性性に極端に反応してしまう。全とっかえで、すぐにでも「問題ない」という状態を欲しがっている。
私も同じなのではないか? ふとそう思った。
私は母を忌み嫌っているが、その感情を完全に除去したがり、胃に手を突っ込みたいとまで思うのは、母への嫌悪に耐える力が少ないということなのではないか? 母が100%の充実とか優秀とか幸せを求めたことと、仕組みはそっくり同じではないか。なんと、こんなところにまで「母」が染み付いているのだ。
そう思ったら、これまでどうでもいいと思っていた、母の描いた数多くの絵が、興味深く思えてきた。
ほとんどが紙のコラージュによる抽象画だが、唯一、女性のヌードを発見した。小さな水彩画だ。女性が裸で鏡に向かって髪をとかしていて、窓の外には港町が広がっている。とても魅力的だ。自画像だろうか。一瞬でも正気に戻って、みずからの欲望を直視した瞬間があったということなのだろうか。
私はこの絵を自分の家に持ち帰ることにした。
愚かな一人の人間の形見として。











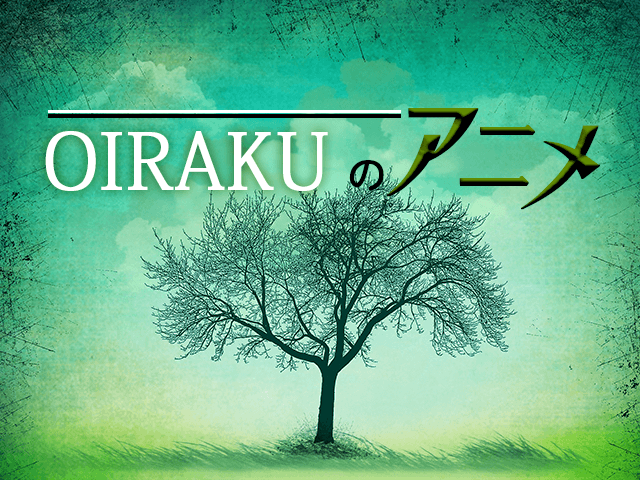



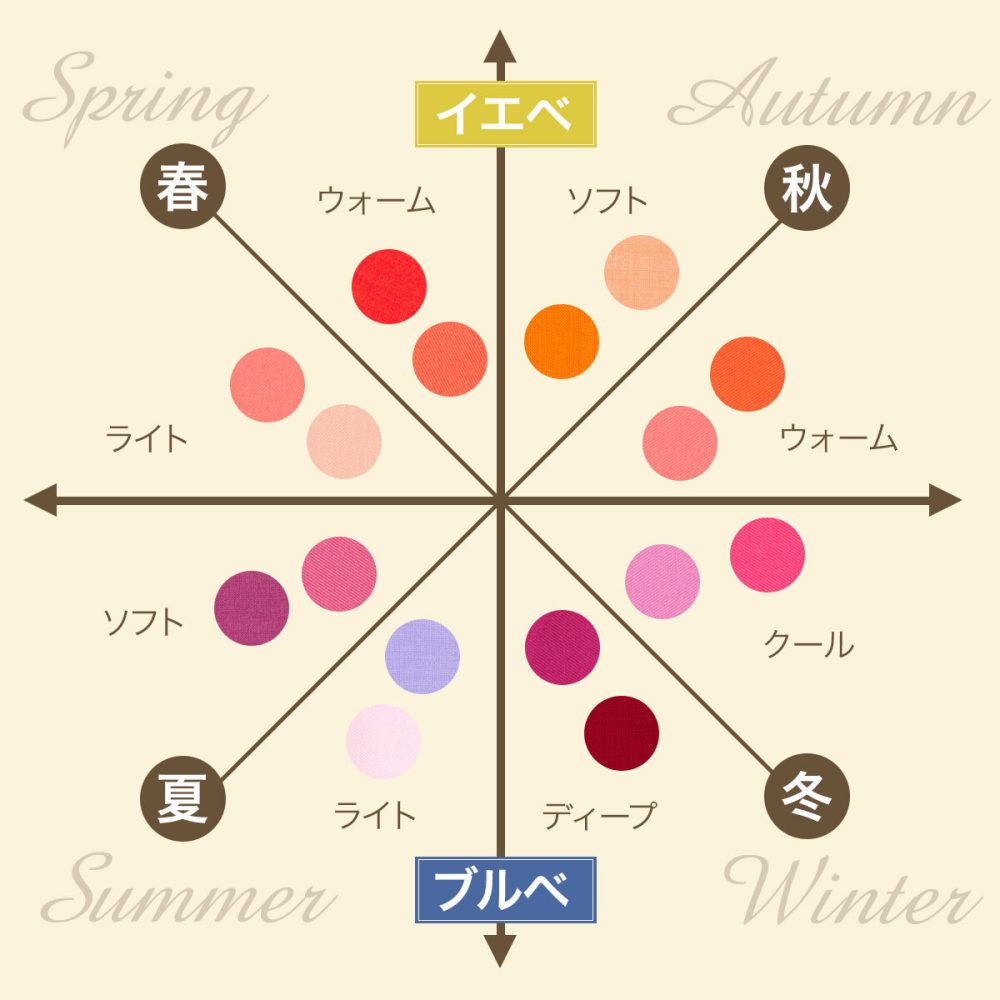
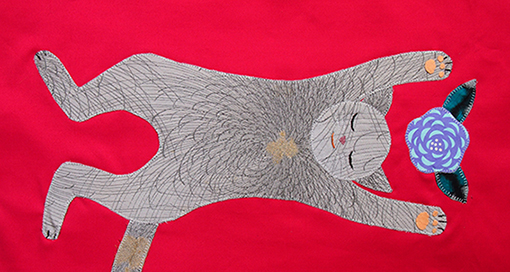





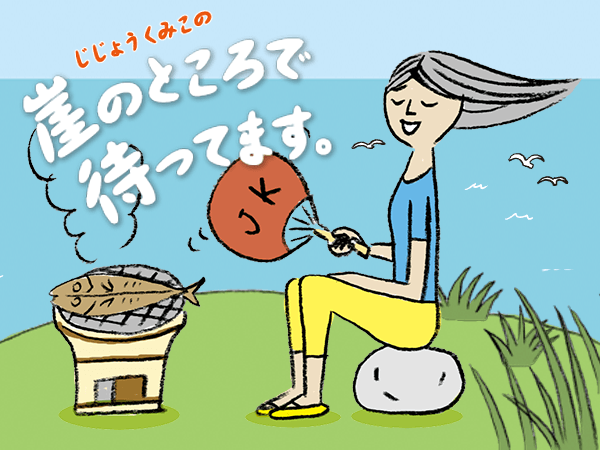
























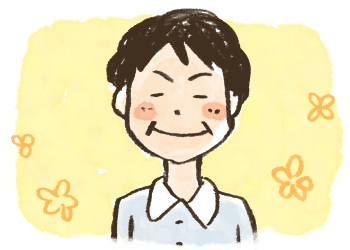
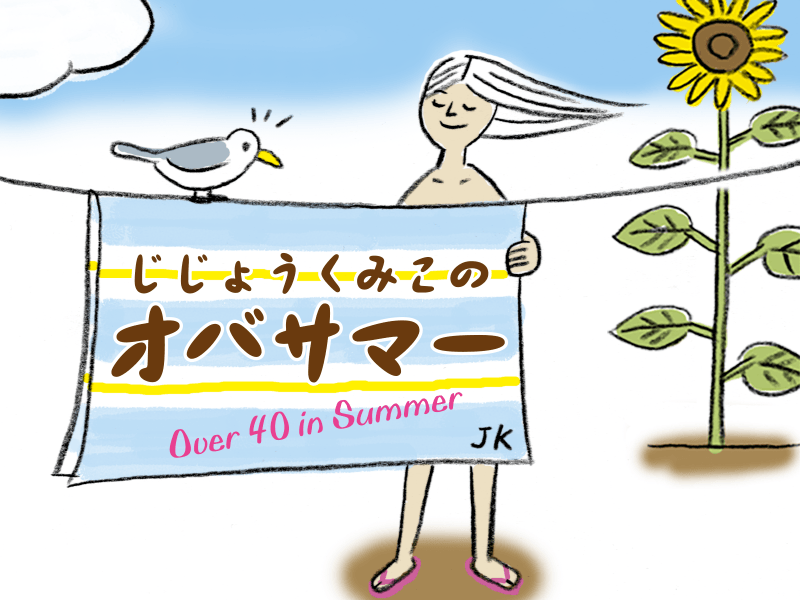























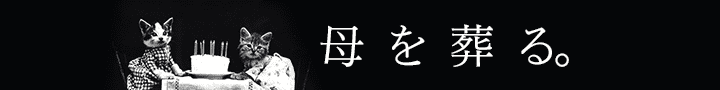











匿名
書くことで、すこしは気持ちが整理できたかな。お疲れ様でした。
クリスタル
最近このコラムを知って一気読みしています。
私の母93歳も似たようなところがあり、年をとり認知症の症状になり、本能のままに自分の感情を娘に発散します。
育てられていたころは二女の私はそれほど毒は感じませんでしたが、長女の姉は昔からやりにくかったそうです。
昔の母は自分の本心も、父の存在と理性で抑えられていたのかなと思います。
毎回毒を吐かれるのですが、それでも面会に行かなきゃとイカンかな、と心を無にして、気の毒な人だなと思って、行っています。
心の中で母をどう思おうと自由にしていいのだな、とこのコラムを読んで自分で自分に納得して許可しています。
ぜひ、書籍化してほしいです。
にゃがたちにゃ
私を含め、母親が嫌いだった女たちが「母のようになりたくない」とか「毒親連鎖をここで止めたい」「母性信仰やばい」などと思ってしまった結果がこの少子化、出生率低下なのかもねー。とても個人的なことながら、けっこう世代的にあるあるな気がするんですよ。
プリ子 Post author
匿名さん、ありがとうございます。書くことで、整理できるだけでなく、自分がこの事象をコントロールできているという安心感もありますね。もちろん、書かなかったことで、忘れてしまいそうなこともあるけど。あと、途中で日記を発見して、連載後半がだいぶ膨らんだのは、思わぬ幸運でした。
プリ子 Post author
クリスタルさん、コメントありがとうございます! 一気読み、書籍化だなんてうれしいお言葉、本当にありがとうございます。
お母様はずっと我慢してながらも、毒をお姉様にぶつけてしまっていたんですね。認知症になると、抑えていたネガティブなが感情がたくさん出てくるってよく聞きますが、周りの人からしたら、たまったものではないですね。。。
面会はどうしても行かなければならないものなのでしょうか。時には無視してもいいのでは。観察して面白がる、とかならいいですが、ご無理なさいませんよう。
おっしゃる通り、親を(もちろん自分以外の誰をも)どう思おうと自由です! 親だから敬わなきゃいけない、好きでいなくちゃいけないなんて、親子関係をもっとも小さな単位として、世の中を上下関係で構築しようとした昔の考え方で、ごく少数の人しか幸せではない思います。
と言いながらも、「美しい親の愛」みたいなドリームにすがってしまう部分は私にもまだまだあるのですが、少しずつ脱却していきたいです。
プリ子 Post author
にゃがたさん、ありがとうございますーー!! この連載で書いた最初のドタバタの頃にいただいたお菓子、心の支えでした。
たしかに! 子どもに自分のかわりに出世してほしいとか、そういうのにうんざりした人が、子どもを産むのを躊躇するのは、すごくわかります。気づいてしまった人がたくさんいるんですよね。
私は「子どもはほしくない」と特に強く思ったわけでもないのですが、もし自分に子どもがいたらと思うと、自分の母親のように子どもを支配しそうで、考えるだけでぞっとします。猫を動物病院に連れて行くときですら、いい子にしてるか気にしてしまうんですよ、やばいです。
同世代のいろんな人の話を聞いてみたいです。