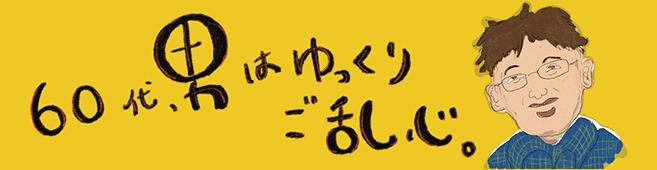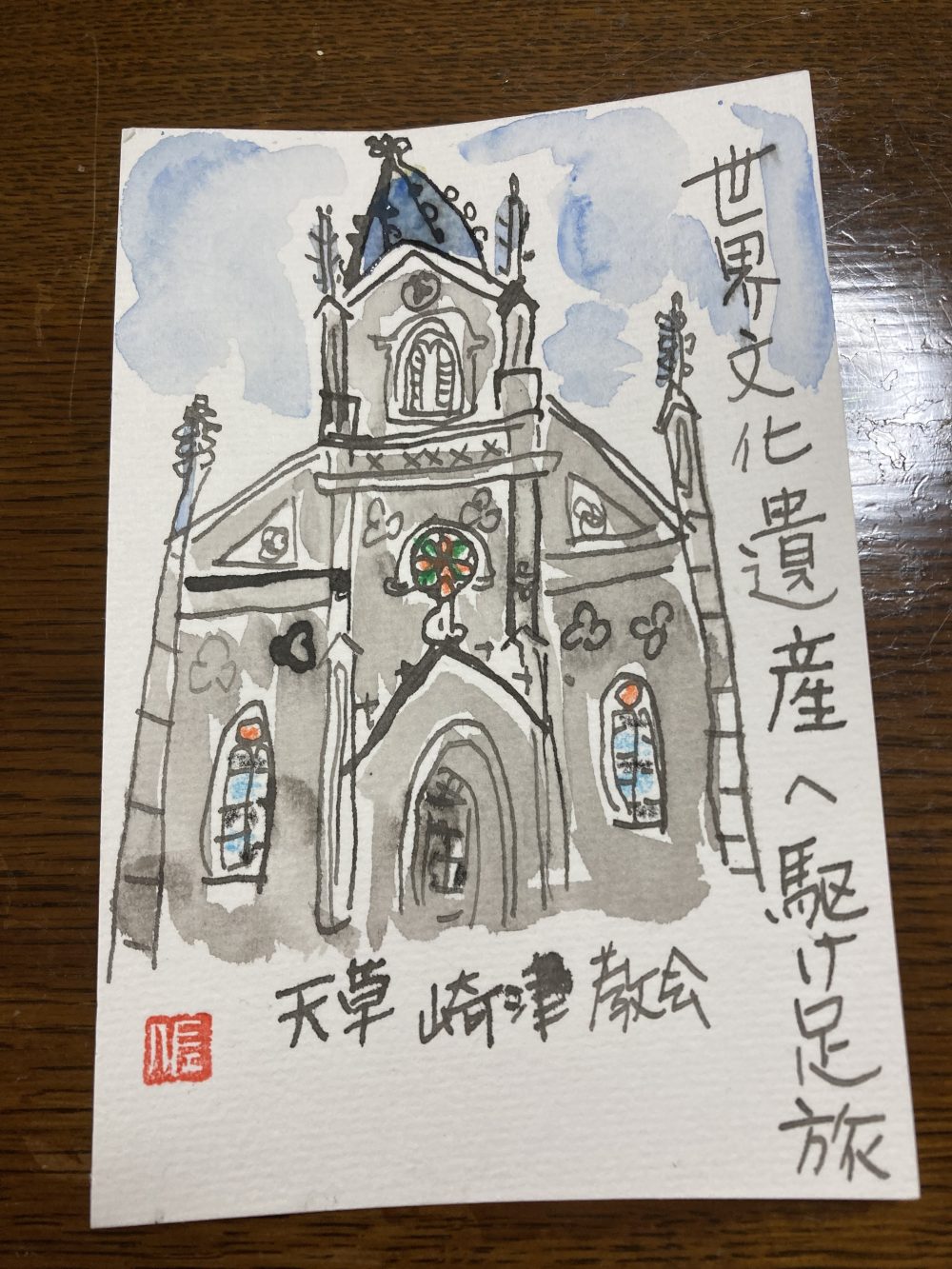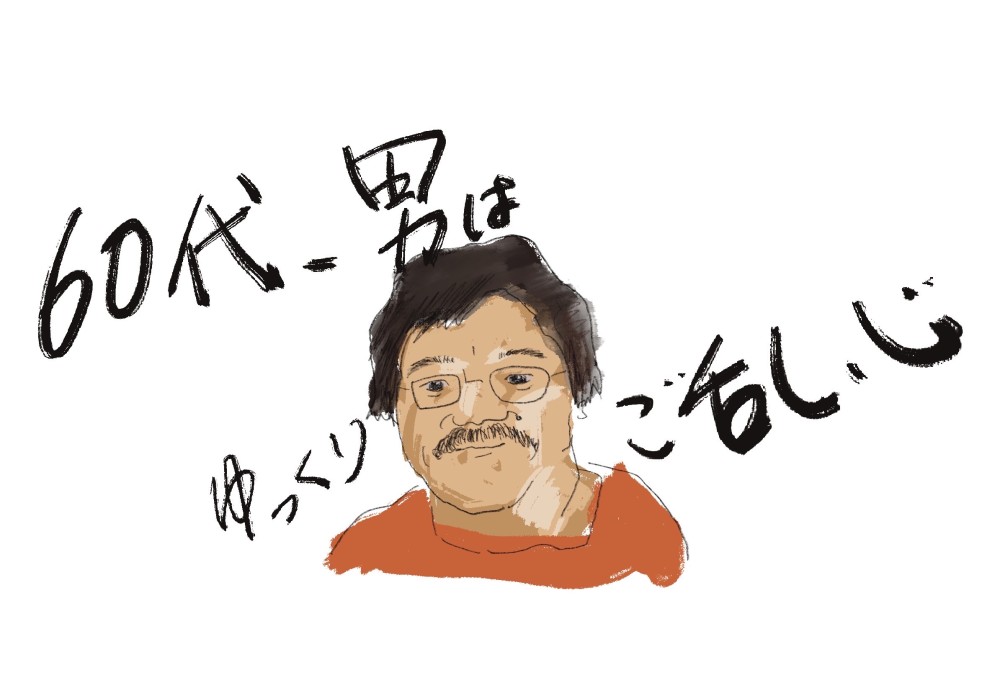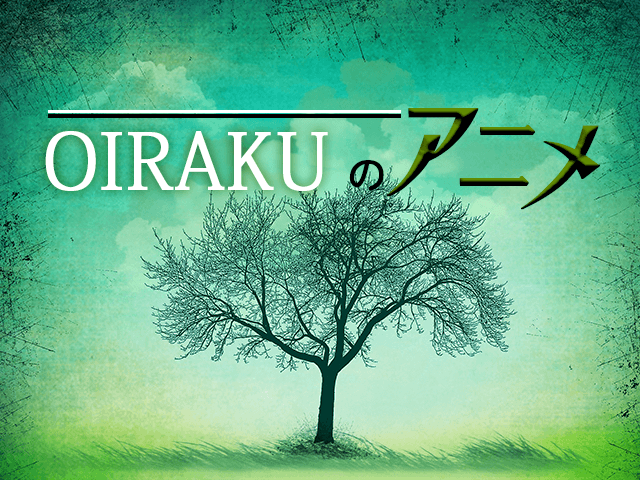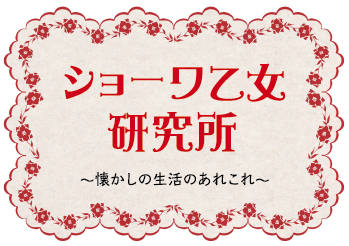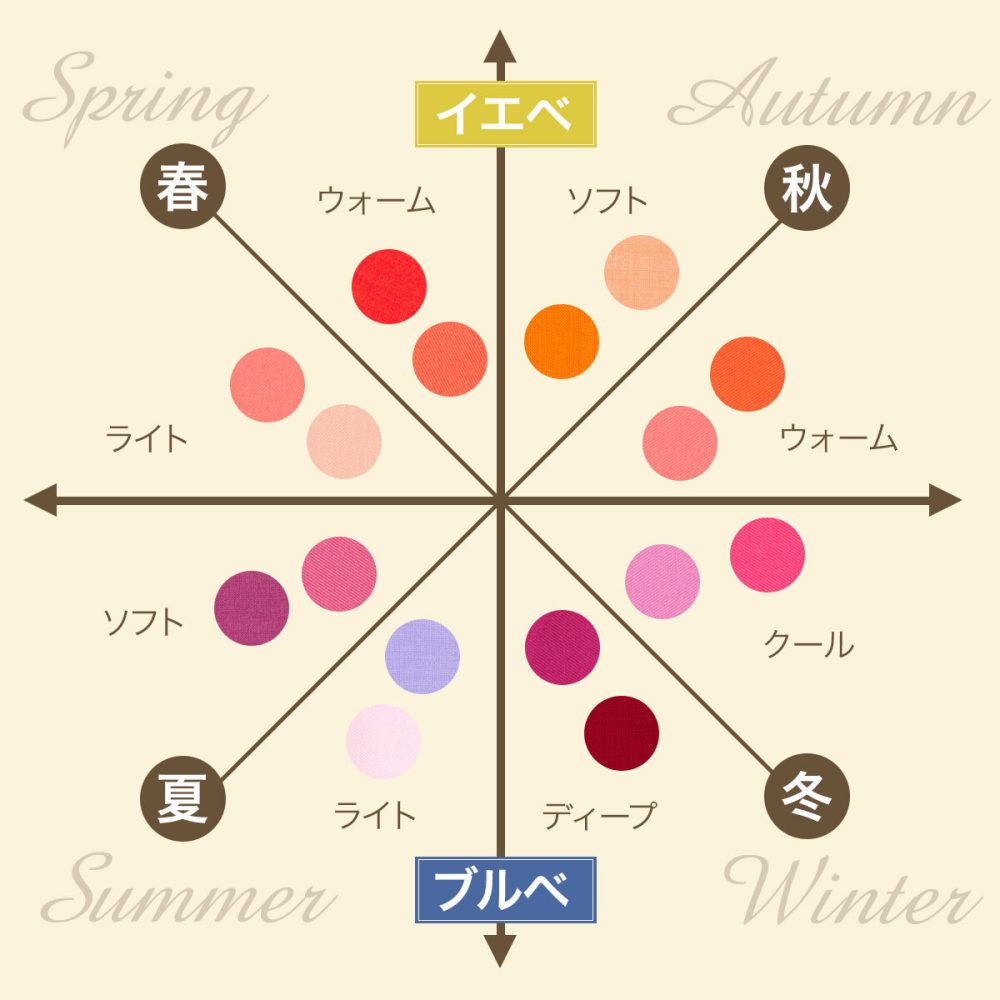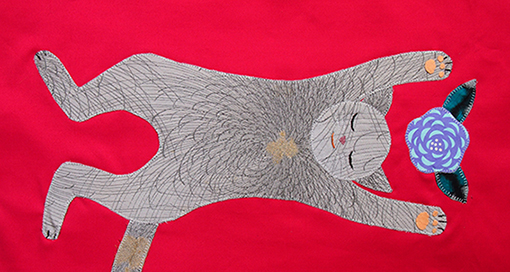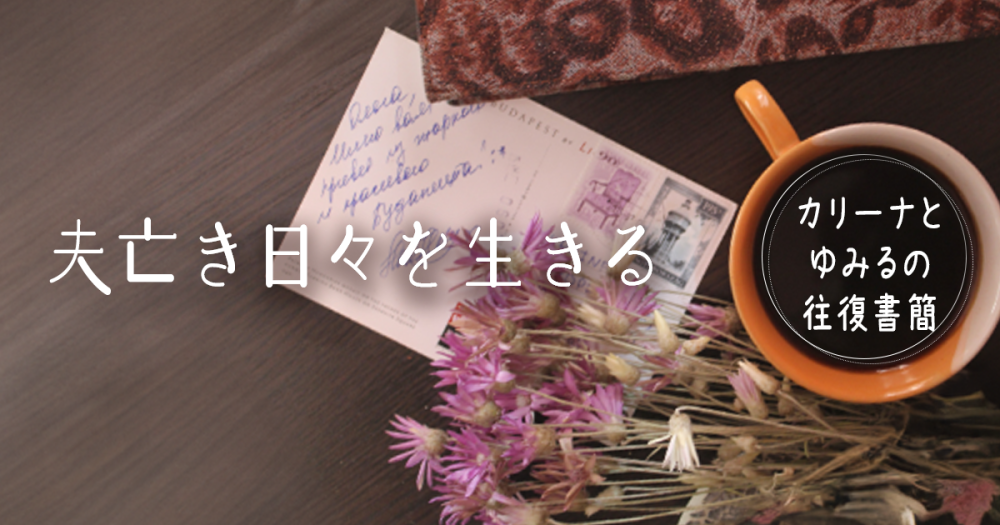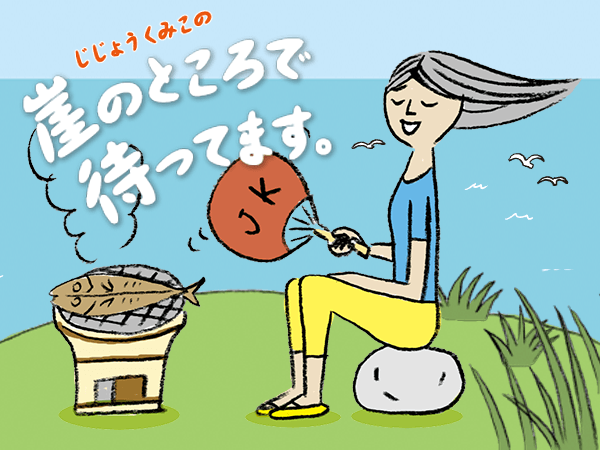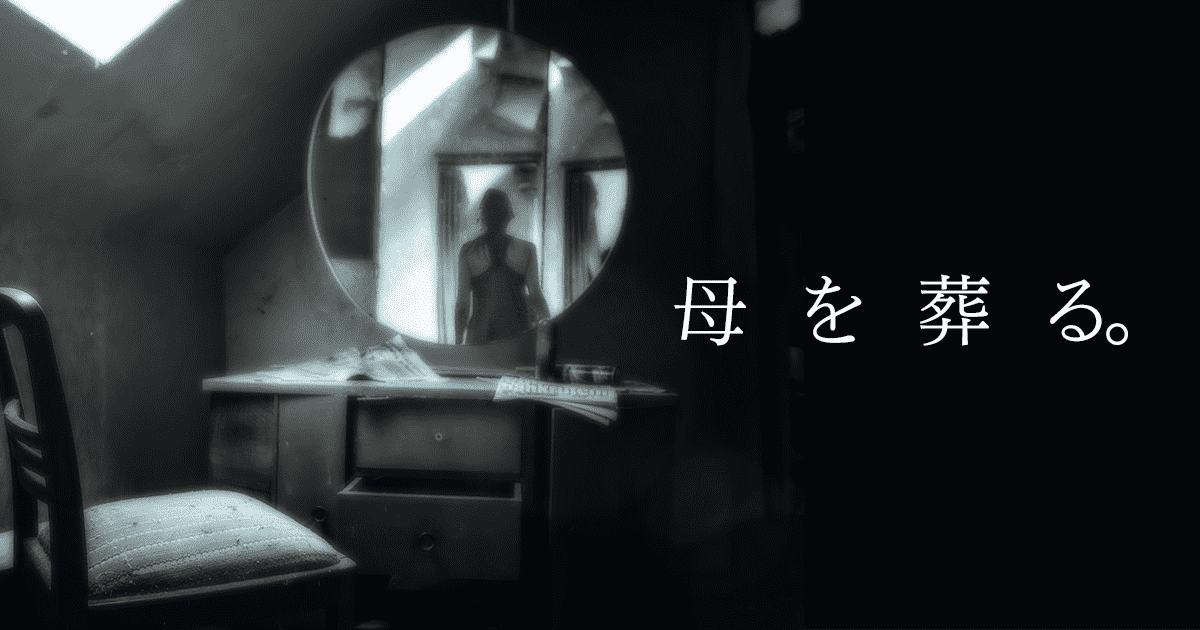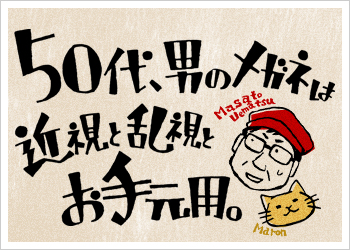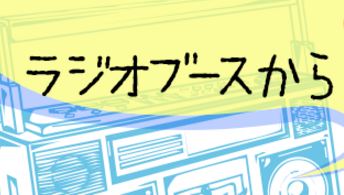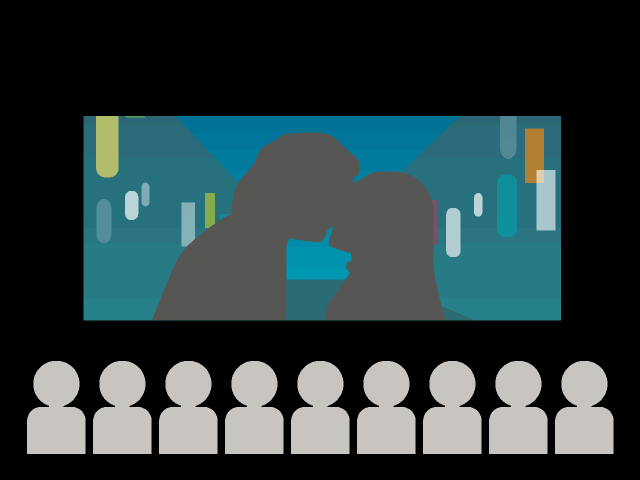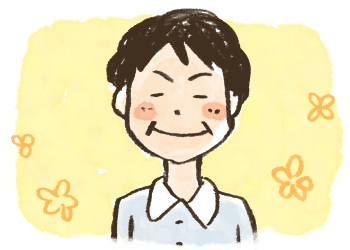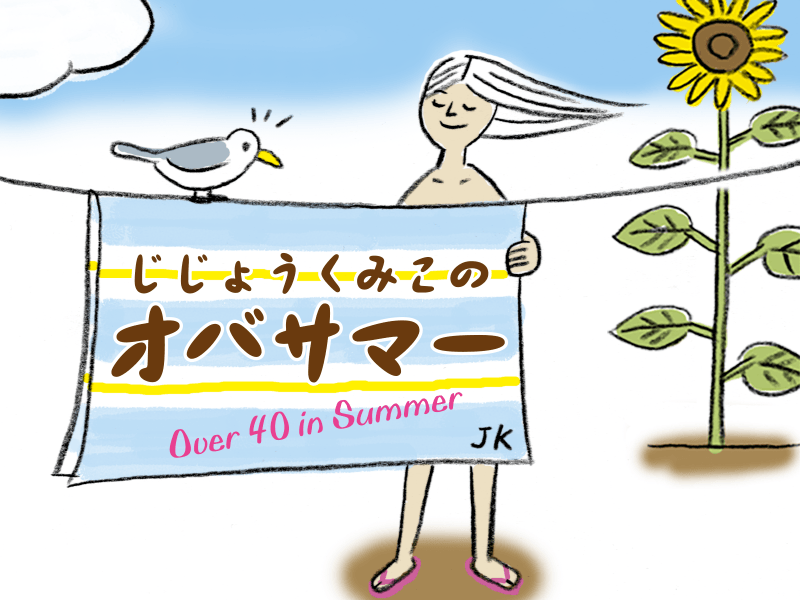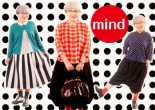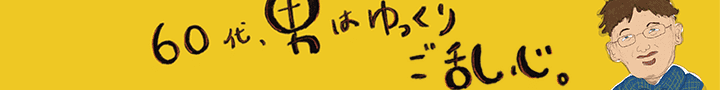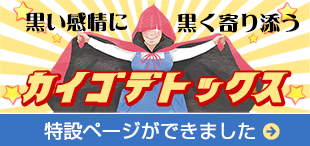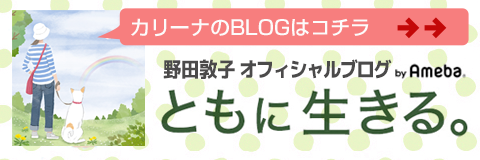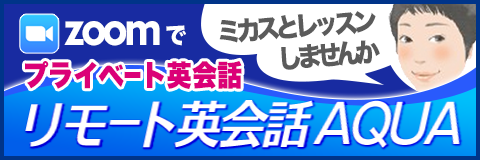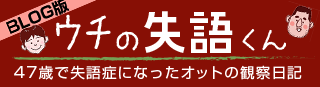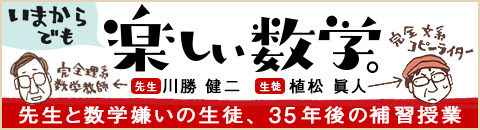喫茶店で隣の会話を楽しめるか。
ときどき、ここでも書いているように、僕はコーヒーショップで仕事をすることが多い。家で仕事をすることもできるのだけれど、誰もいない家の中に1人でいると寂しくなる。適度にざわめきがあるほうが落ち着いて仕事ができる。
ただ、隣に座る人によってはざわめきを通り越して、ざわざわしたり、いらいらしたりすることもある。
いちばん嫌なのは、隣のテーブルで、音を出してゲームをされたり、動画を見られたりすること。でもまあ、これは「スミマセン」と言えば、だいだいやめてくれる。
ややこしいのは、電話だ。携帯電話の時代になって、公共の場で通話する人が増えた。僕は昭和を引きずっている人間なので、店の中で通話することはないし、オンライン会議に参加することもない。でも、普通に電話に出て、普通に話はじめる人は、ここ数年増えているし、それに対して不快な顔をする人はどんどん減っている。
正直、馬鹿みたいに大声でなくて、手短に済ましてくれるなら、まあいいかとは思う。だって、大阪の街で隣のおっちゃん、おばちゃんが大きな声で笑って話していても別に気にならないんだから。でも、不思議なことに大きな声ではなくても、電話は気になってしまう。
なぜだろうと思っていたら、アメリカのコーネル大学で学術的な研究がされていたらしい。研究によると、電話の一方的な会話は、対話形式の会話よりも注意を引きつけるのだという。両方の会話が聞こえているといいのだけれど、片方だけが聞こえてくると、人間の脳は知らず知らず「次に何がくるのか」と無意識に続きを探ってしまい、雑音だとしてもこれを無視できなくなるのだそうだ。
なるほど、そんな記事をネットで調べて読んでいたら、となりにおばちゃんが座って電話で話し出した。よし、ここはコーネル大学も研究を活かして、乗り切るのだと、僕は実験に出た。
相手が話していることを想像して、勝手に会話するのだ。おばちゃんが「元気なの?」というので、僕は「元気なわけないじゃない」とおばちゃんの友だちを想像しつつ答える。すると、おばちゃんが「あら、どうしたのよ」と返す。おお、これはいい。「どうしたもこうしたも、入院しちゃったのよ」と僕が心で返す。すると、おばちゃんは大笑いしながら、「あんたいっつもそうなのよ」ときた。いっつもと言われても、いっつも入院している人もいないだろうし、と「いっつもって、そんなしょっちゅう入院してないわよ」と返すと、おばちゃんは「どうでもいいけど」と笑う。
(なにがどうでもいいのよ)
「ところで、頼んでたのは大丈夫」
(大丈夫、ちゃんと用意してるわよ)
「連絡さえしてくれればいいんだけど」
(連絡?誰に?)
「前も、忘れてたでしょ」
(忘れちゃいないわよ)
「とにかく、いまどこなのよ」
(だから、入院してるってば)
「はいはい、急いでね」
(急げないわよ)
と、おばちゃんが電話を切り、しばらくすると、入院しているはずの相手が喫茶店に現れたのである。
ああ、隣の会話を楽しむのは、なかなか手間がかかる。コーネル大学は隣の電話の通話を楽しむ方法も研究してくれないかね。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松眞人(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。