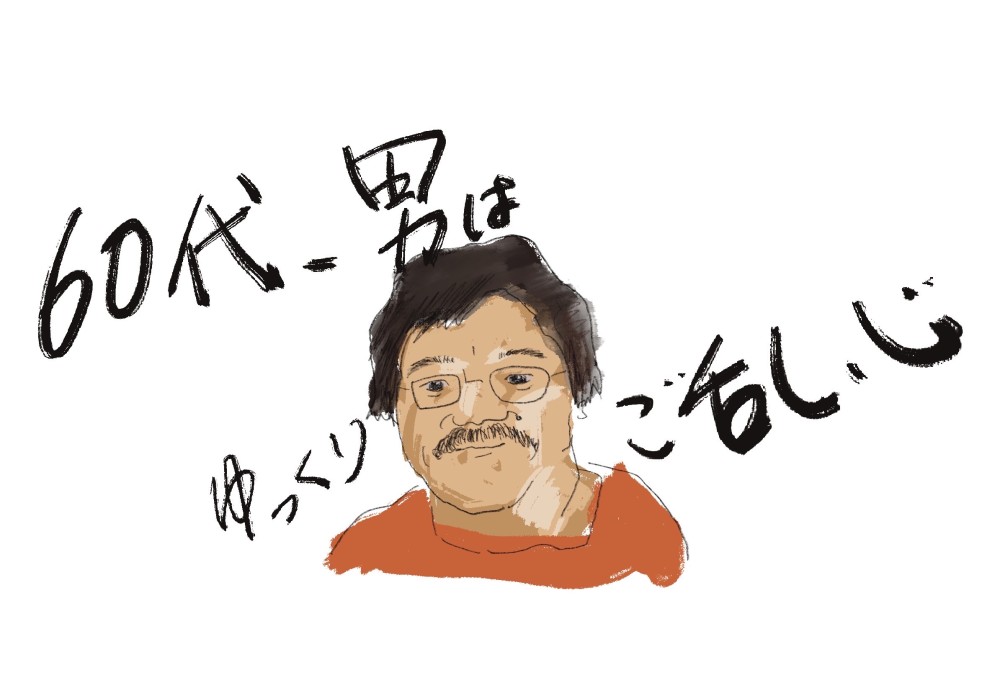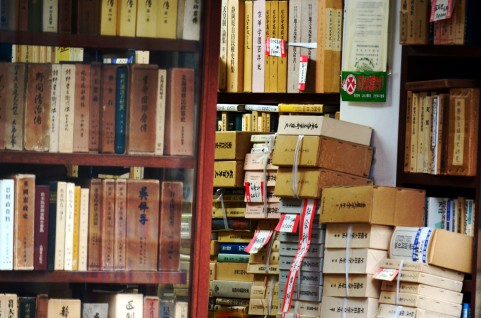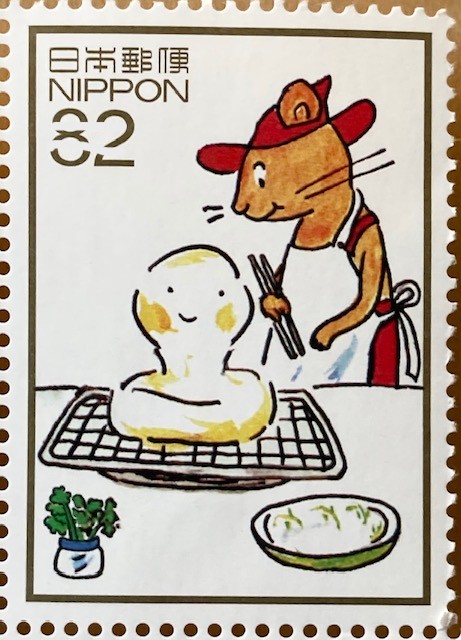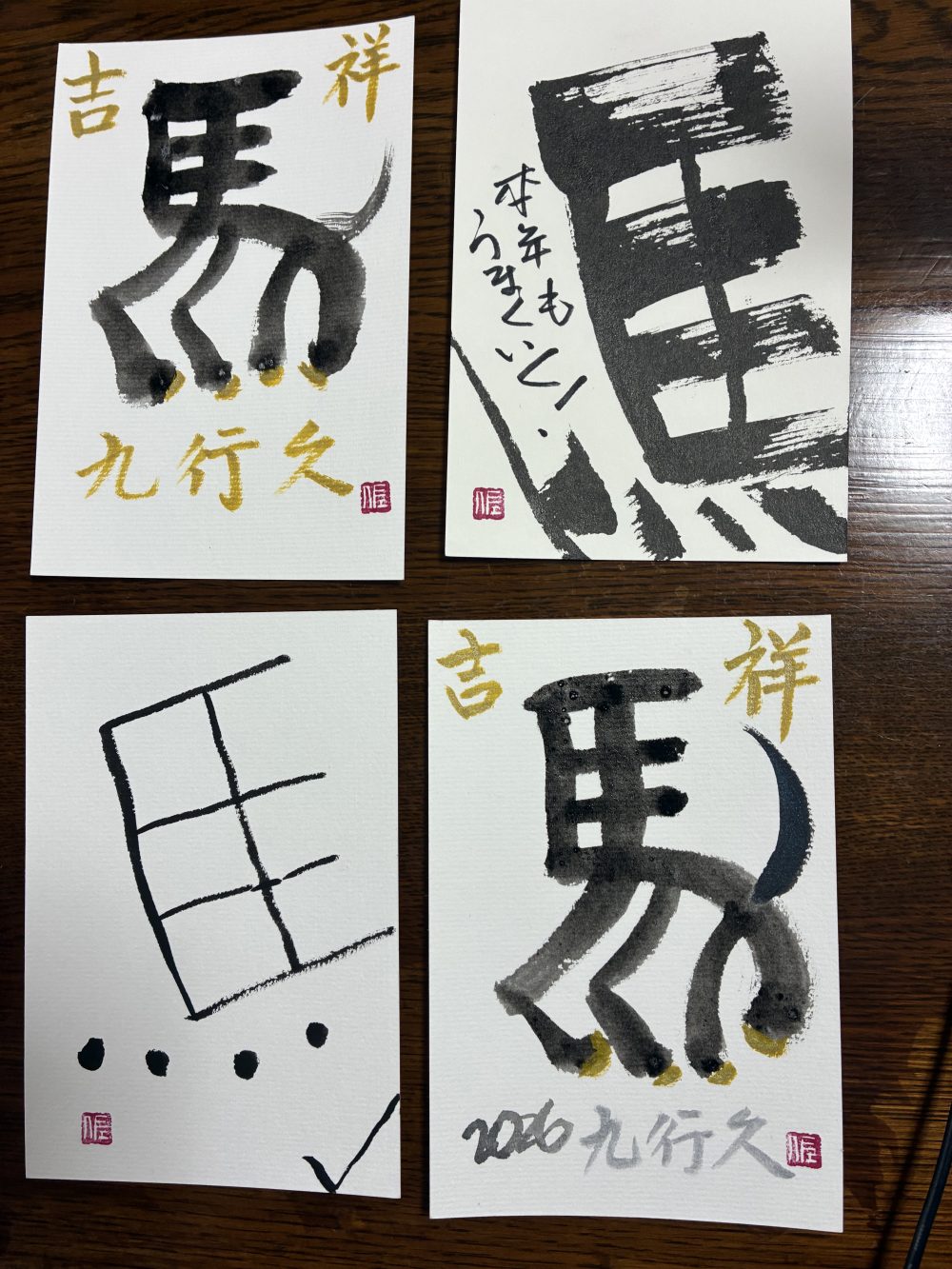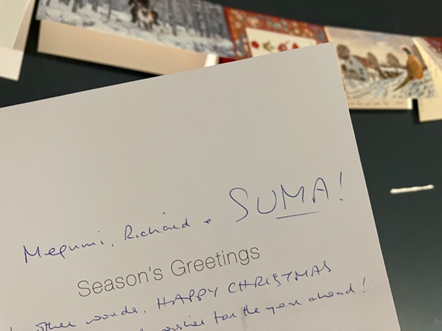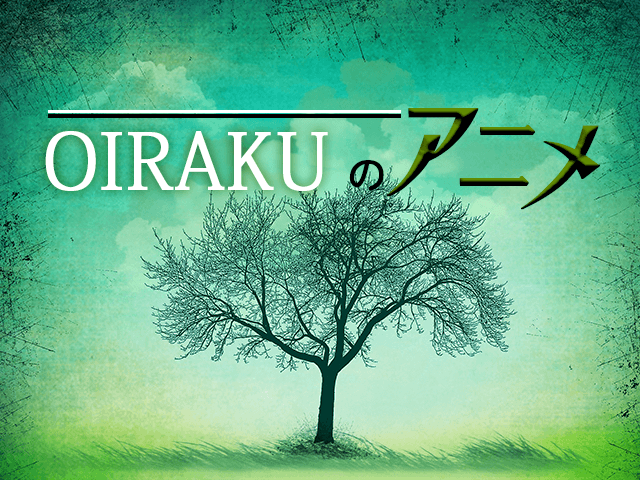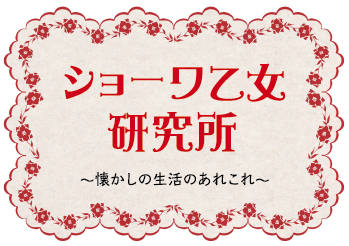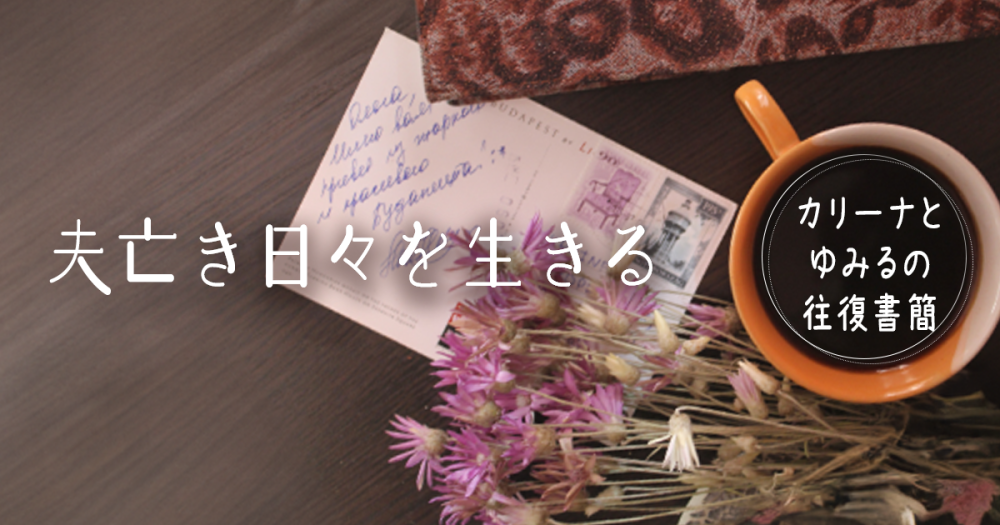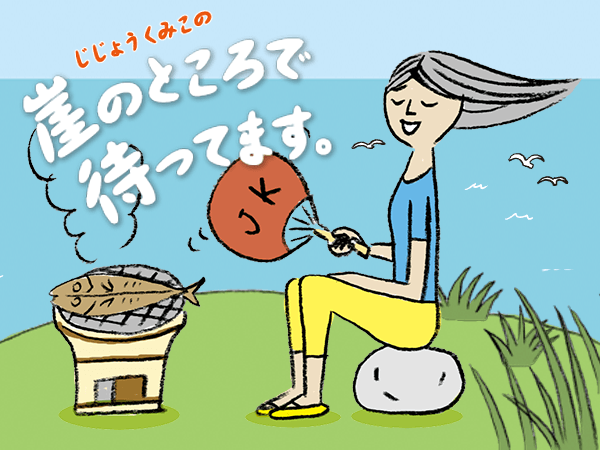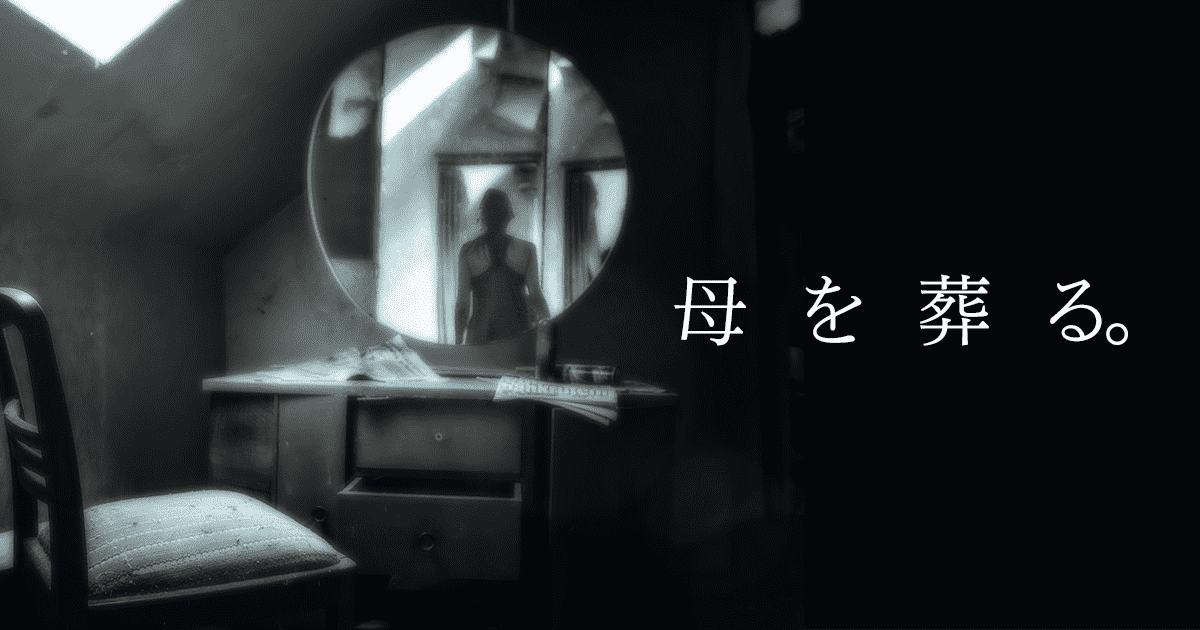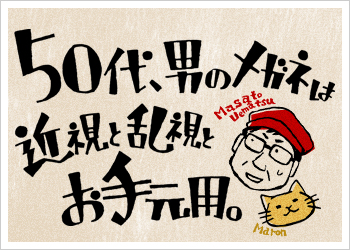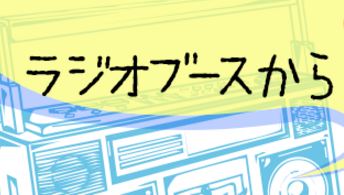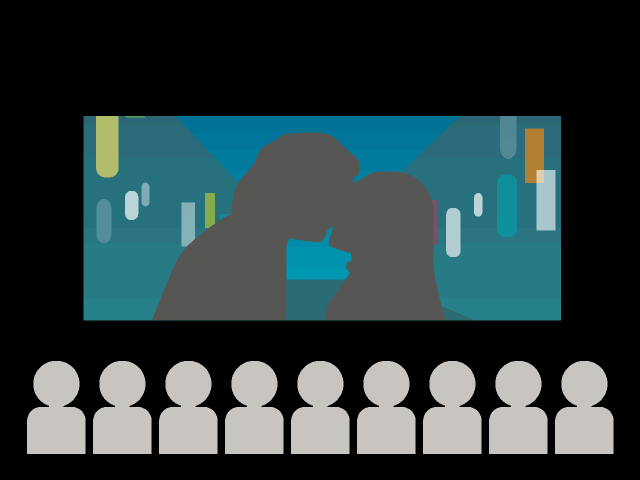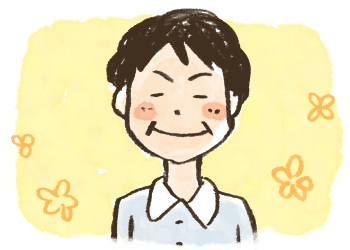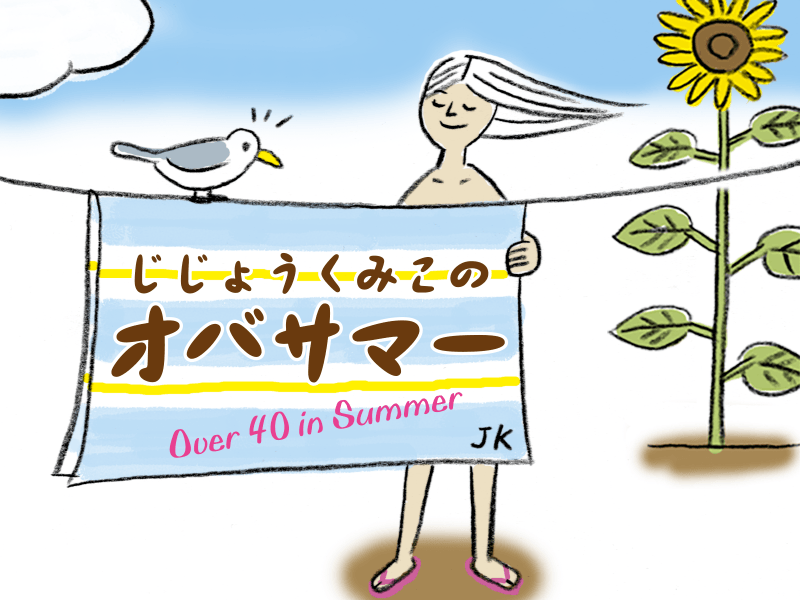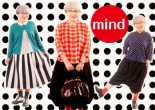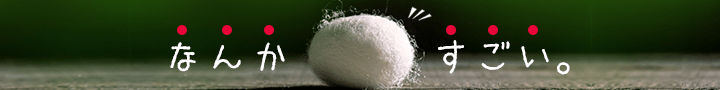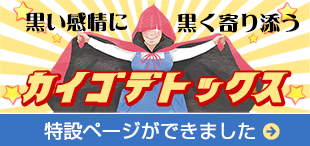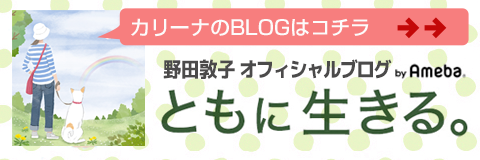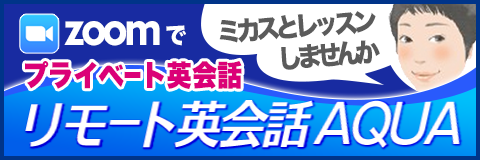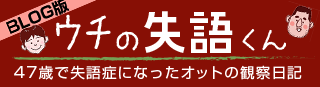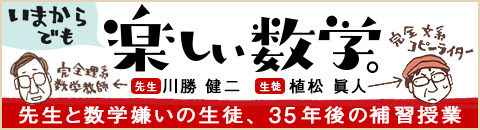デレク・ジャーマンの庭
夏休み、3週間の予定で姪が来ている。げんざい美大2年生の19歳。大学で出会った友人といっしょにやってきて、なんやかやと楽しくしている。
赤ちゃんのときから知っている、ちょっと前まで小さな少女だった姪がもう成人になろうとしていて、アルバイトで貯めたお金で飛行機の切符を買って、自分たちでちゃんとやってきた。なんだかすごいなあ。過去メガネをかけた叔母のわたしは、何かと先回りして世話をやきがちで、よくないおとなである。
考えてみたら、わたしがはじめてイギリスを訪れたのも、同じくらいの時期だった。1996年の11月、正味4️日滞在の、大学3年生のひとり旅だった。
イギリスに行く目的は、たったひとつで、ダンジュネスにあるデレク・ジャーマンの暮らした家、プロスペクト・コテージを訪ねることだった。
携帯もネットもなかった90年代、すべての情報は雑誌と本から得ていた。デレク・ジャーマンがなくなったあと、彼が晩年を過ごしたコテージと庭のある海辺の町ダンジュネスを特集した記事が雑誌に掲載されて、それを切り抜いてとっておいてあった。たしか、女性ファッション誌だったと思うけれど、どの雑誌だったか覚えていない。
「個人旅行」という黒い表紙のガイドブックで見つけたロンドンのホテルに日本から予約をしたのだが、申込書をファックスで向こうの郵便局に送って、それを向こうの郵便屋さんがホテルに届けてくれる、という方法だった気がする(ほんとうだろうか)。ガイドブックには、まず1泊か2泊くらい予約をとって、あとは気に入ったら現地で連泊を申し込めばいいと書いてあったのでそうした。
成田空港では、たまたまエレベーターに乗り合わせたロンドン駐在のおじさんが何かと世話をやいてくれ、空港のラウンジでジュースをもらった。おじさんのスーツケースは、日本食や缶詰がたくさん入っているらしくとても重く、受付カウンターで超過料金を払っていて、海外で暮らしていて日本食が恋しいなんてだせえな、と思ったりした。そしてなりゆきでこのおじさんとはロンドンでも会うことになる。
もうこの時点で、心配しかない感じである。
ロンドンのホテルは、たしかスローンスクエアが最寄駅で、治安が良さそうなわりに安かったので決めたのだが、びっくりするくらい小さくて古かった。洋服ダンスみたいなところにシャワーがついていて、栓をひねるとちょぼちょぼと真水がしたたりおちた。それでも、ホテルを移るのがめんどうくさくて(安かったし)延泊を申し込んだところ、すげなく満室ですと言われ(でしょうね)、翌朝別のホテルを探し歩くはめになったのだった。ガイドブックのいうことを鵜呑みにしてはいけない。
駐在のおじさんとは繁華街で落ち合って、おじさんは演目は忘れたがミュージカルのチケットを買ってくれ、中華料理をごちそうしてくれた。まじでやめとけというしかない。
そして3日目に、雑誌の切り抜きをにぎりしめ、南部の海辺の町、ダンジュネスに向かった。記事のすみっこには、ちいさな字でダンジュネスまでの行き方ガイドが載っていて、Ashfordまでいってそこで乗り換えだったか、そんなふうに書いてあった。
今地図で見ると、Ashfordはダンジュネスからずいぶん遠くて、そこからどうやって辿り着いたんだったか覚えていない。ともかく降り立った11月のダンジュネスは、風が吹き荒れて、世界の終わりみたいに荒涼としていた。
海からの強風と塩の影響で背の高い植物が育たず、岩とかわいた低木の茂みがどこまでも続く真っ平な風景に、一本だけ道があって、さびれた漁船や黒くタールで塗られたコテージが点在していた。すぐ近くに海があるはずなのだけれど、視界がわるくてどちら側に海があるのかもよくわからなかった。
でも、これこそがわたしが見たいダンジュネスだった。ときどき潮なのか雨なのかわからないのがふきつけてきて顔をぬらし、スカートがじっとりと重くなり歩きにくかった。この土地特有の穴の空いた小石を拾いながら歩いた。だれもいなかった。
プロスペクトコテージは、一本道沿いの、数十メートルくらい離れた場所にぽつんと建っていて、デレク・ジャーマンが長い時間かけてこの土地と育てた、石や苔や地衣類たちの庭にかこまれていた。コテージはこぎれいに手をかけてあって、海風にさらされた石や木片や有機物がほのかに黄色く、発光しているみたいに見えた。
コテージは無人に見えたけれど、雑誌記事には、彼の恋人が住んで管理していると書いてあったので、あまり家に近付くのははばかられて、周りを遠巻きにぐるぐるまわって、長い時間かけて眺めた。生きているものと死んでいるものとが、大気のあわいにとけあっているような不思議な場所だった。
どうしてこの場所にこんなに慕わしい気持ちを抱いたのかな。きっとここを訪れた多くの人たちも同じ気持ちだっただろうけど。映画も好きだったけれど、デレク・ジャーマンの書く日記や文章が同じくらい好きで、アイデンティティの定まらない若いわたしは、彼をとりまく家族のようなひとびとにも親しさを感じていた。子どものころにムツゴロウ王国に弟子入りしたかったことや、ドリトル先生と動物たちに家族の一員のように受け入れられるトミー・スタビンズ君にやきもちをやいていたのと、根っこは同じではないかと思われる。わたしは、優しくて寄るべのない人たちがつくる擬似家族が好きなのだ。

11月の陽の入りは早く、近くには一軒きりのパブがあるとこれまた記事に書いてあったので、そこに向かってふたたび歩き始めると、車が一台やってきて、男の人が顔を出し、
「誰か来てるって聞いたから。どこまで行くの?乗せて行くよ」
と言ってくれた。その顔にたしかに見覚えがあった。そこで、じゃあ近くのパブまで、と乗せてもらったのだが、ふつうは乗らないでください。
彼は2言3言何か聞いた気がするけれど、当時のわたしの英語力は、言いたいことはなんとか準備して言えるけれど、言われていることはさっぱりわからないレベルだったので、ほとんど何も話さずじまいだった。
パブで、わたしは酒が飲めないので、紅茶をもらって暖をとっていると、遠巻きにしていた地元のお客たちが心配して近寄ってきて、帰りはタクシーで帰んなさい、と諭され、タクシーにお金を払うときは、ぜったいに20ポンド以上払ってはいけない、と念をおされた。
そして、そのうちのひとりのおばさんが、タクシーの運転手に何か言い含めてくれて、無事に帰路に着いたのだった。
今思うと、車の彼といい、パブの常連といい、わたしのことをほんとうにあぶなっかしいと思ったか、自殺でもしにきたかと思ったのかもしれない。1996年、デレクの死から2年余りが経っていて、日本の雑誌にも紹介されたくらいだから、それなりに訪れる人も多くいただろう、そして、それを快く思わない地元の人たちもきっといたにちがいないけれど、おかっぱ頭に東南アジアの民族衣装みたいな服を着て、にこりとも笑わない東洋の小娘がとつぜん地の果てみたいなパブに現れたら、この国の人間なら看過してはおけないだろうと今ならわかる。
翌日は雨に濡れたせいかなんだか頭がぼうっとして、ふたたび駐在のおじさんから電話がかかってきたのだが、ふざけんじゃねえ、という理不尽な怒りがわきおこってけんもほろろにことわり、一日近所を歩き回って無為に最後の一日を過ごして旅は終わった。
親があらかじめ知っていたら、行くのを止められそうな無防備ぶりである。でも、当人は自分の判断にぜったいの自信があって、根拠もなく落ち着き払っていた。
前もっていろいろと詮索されずにすんで、ラッキーだったと思うけれど、それって無事に行って帰ってこられたから言えるバイアスみたいなものかもしれないなあとも思う。
姪たちがこんな隙だらけで行き当たりばったりの行動をしていたりしようものなら、今のわたしの心中はいかばかりか。
ふたりは見たところわたしよりもずっと分別があって、無軌道とは無縁に思えるが、おとなが知らないほうがいいこともある。
「可愛い子には旅をさせよ」がことわざになっているのは、それが存外むずかしいからだった。ついつい、限られた時間のなかで効率よく、ベストなものが見られるようにとあれこれアドバイスしたくなってしまうのが親心、しかしそれはだいたいアドでなくクソである。有益であってもなお、クソなのだ。
なんかもう、遅い気がするけど。ごめんふたり。おとなってやあね。
去年、30年ぶりに新訳がでて話題になった。原書の初版は1995年、当時洋書版はけっこういろんな本屋さんで手に入って、わたしも持っていたけれど、いつの時点かにどういうわけか処分してしまった。もういちど買い直そうかな。
Byはらぷ