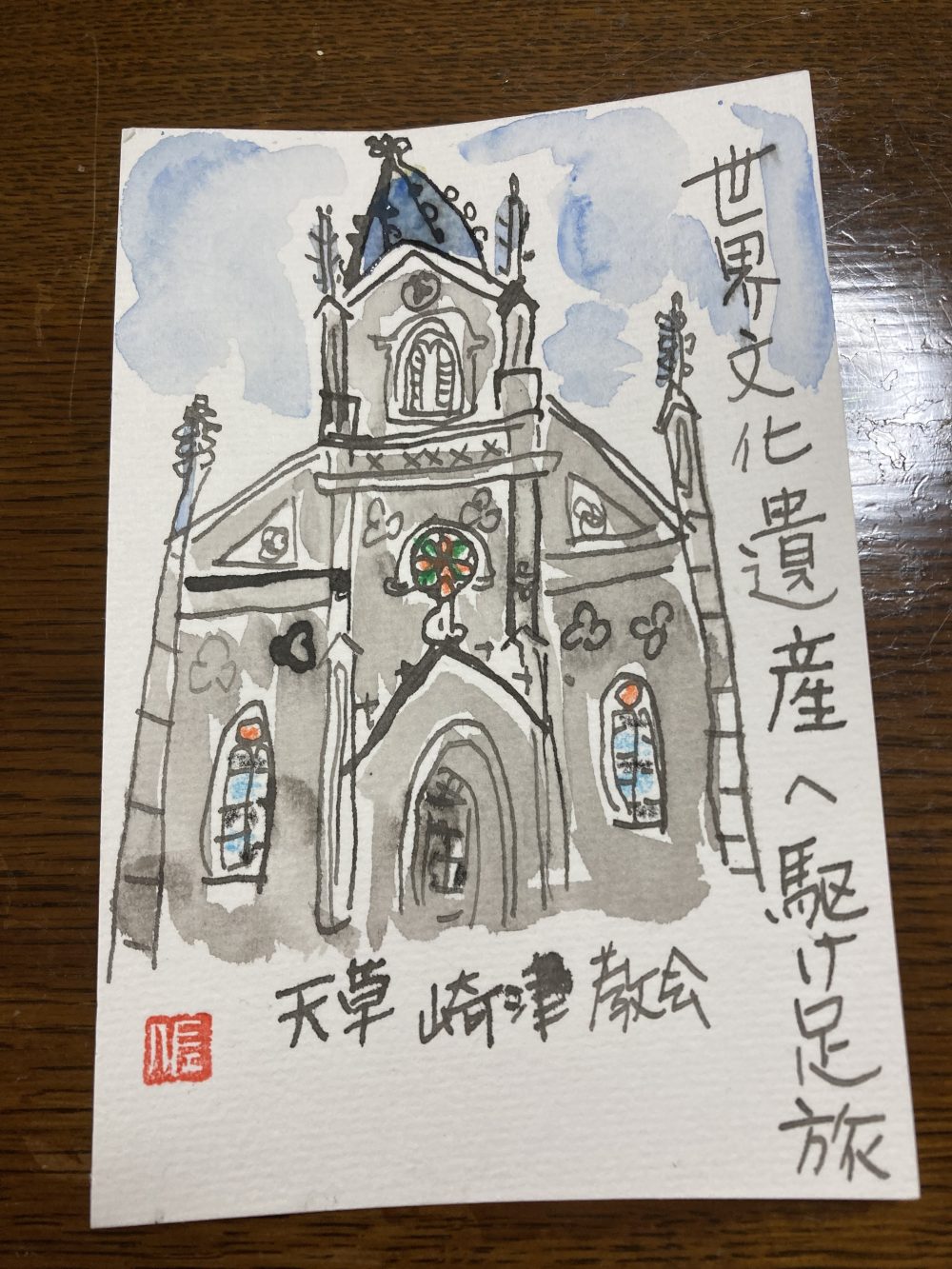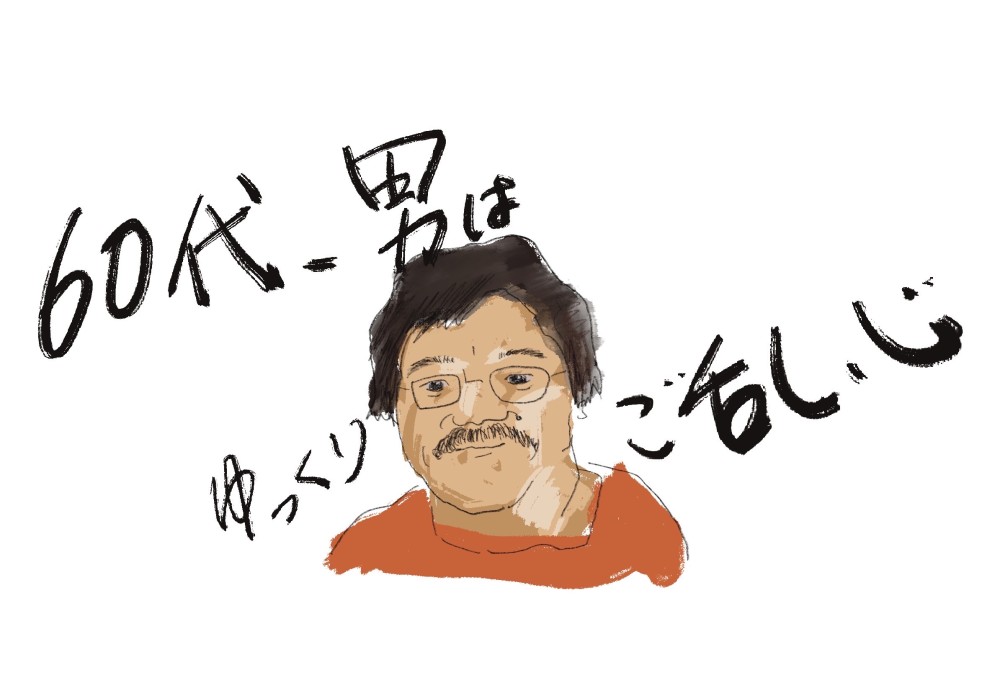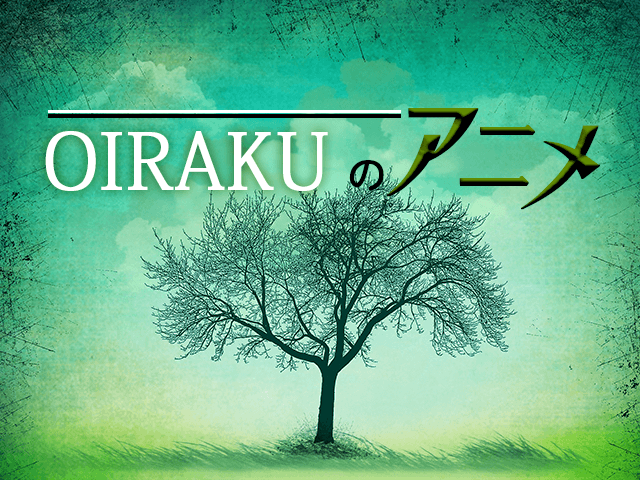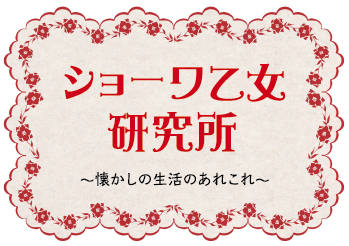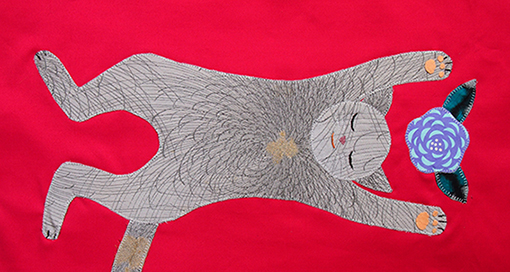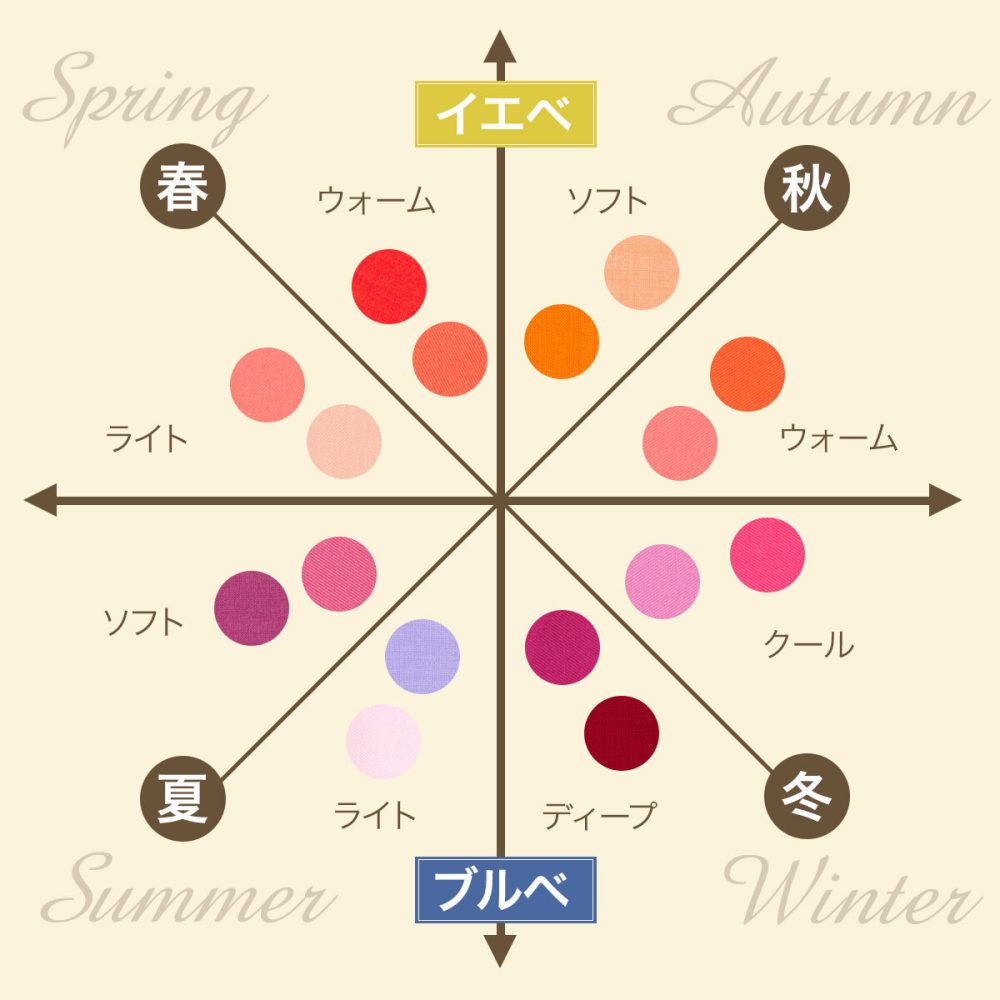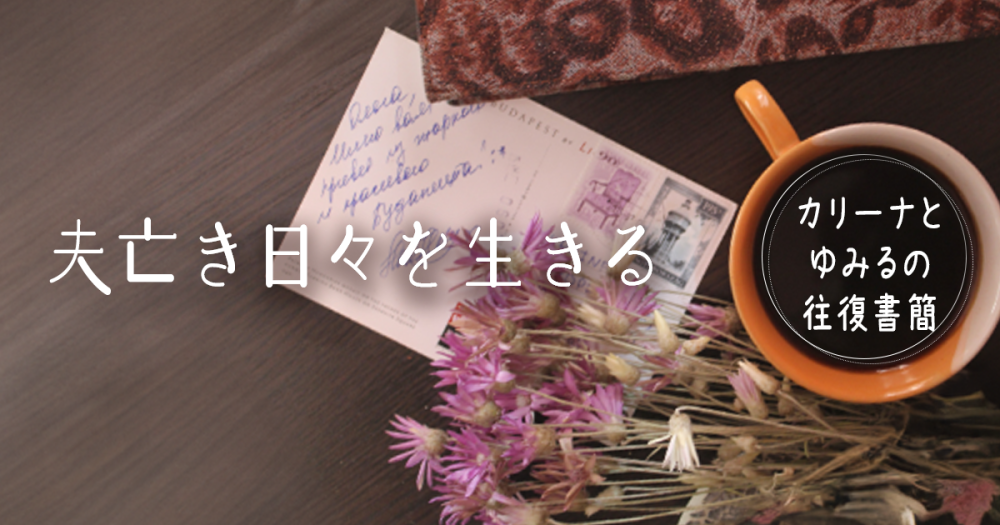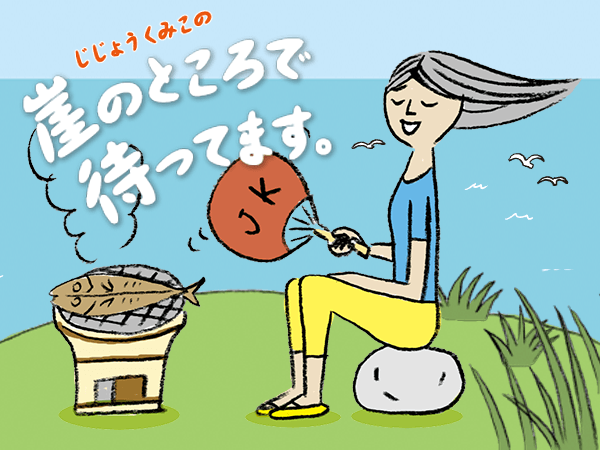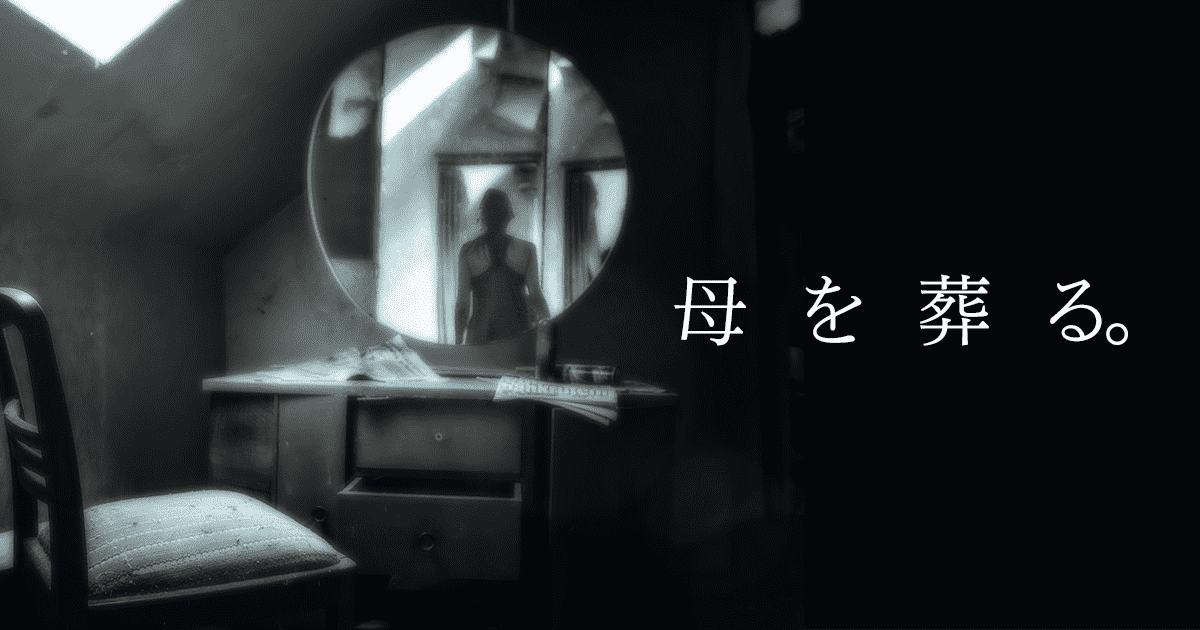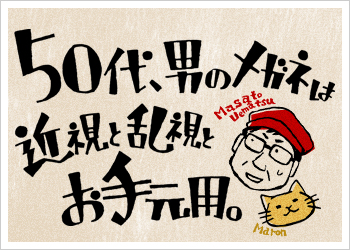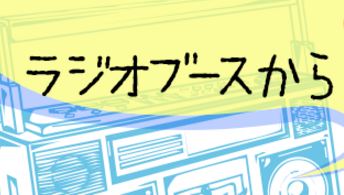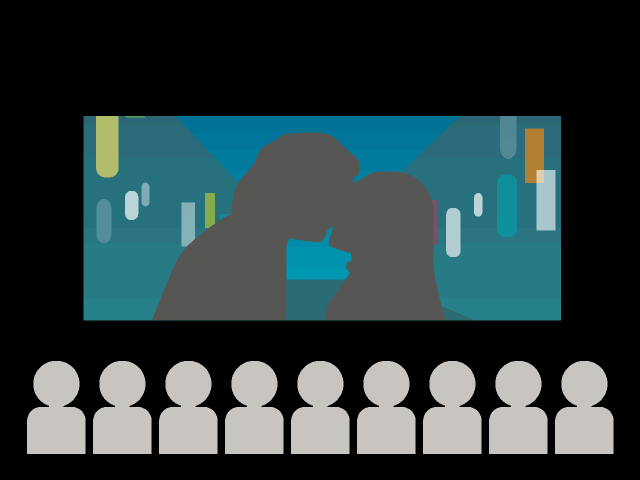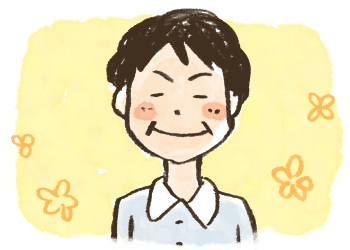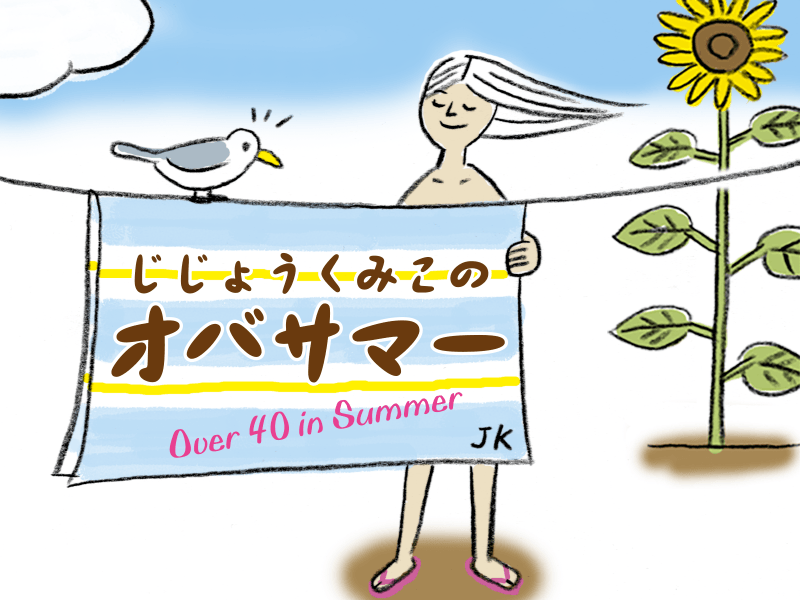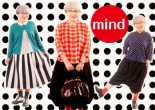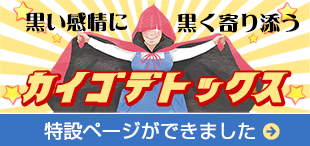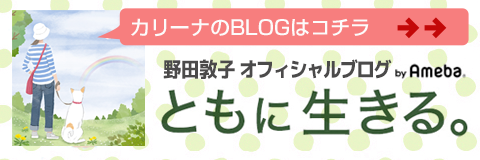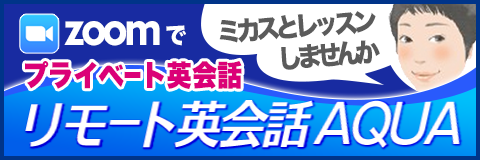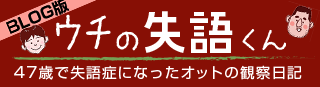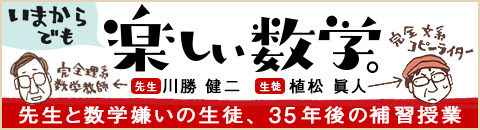◆◇やっかみかもしれませんが…◆◇ 第80回 「新しい図書館の思い出」本を選ぶの巻
15年前、新しい図書館の立ち上げをしたときにつくづく思い知った。わたしは吟味や厳選ができない人間だと。
「年末に新しい図書館をオープンさせるんだけど、建物をつくること以外の準備はぜ~んぶあなたたちがやりなさいね」と上の人から申し渡されT図書館開設準備係になったのは2010年の春だった。新しいT図書館は東京の東の外れに位置し、最寄り駅からは遠く、川からは近かった。ふつう、自治体が図書館をつくるとき、場所が決まったらそこを中心に半径1キロぐらいの円を描いて利用エリアを想定するのだが、われわれが作らんとする図書館にその方式を当てはめると、利用層の半分は川に棲むいきものたちになるのだった。

T図書館開設準備係へ異動するまで5年近く勤務したのは、同じ自治体のやはり当時新館だったH図書館だ。そこにはオープン2ヶ月前に送り込まれたのだが、図書館をオープンさせることの大変さを痛感した。並べる本も、館内のレイアウトも、絨毯やイス選びもすべて済んでいる状態で配属されてさえそうだったから、まっさらな状態でT図書館準備係に抛り込まれたわたしとはらぷとよっちゃん(遅れてうさみーる合流)が開館まで怒涛の日々を過ごすことになったのは至極当然のことだった。
8カ月後の12月のオープンを目指し最初に着手したのはもちろん本選びである。新館に置く本はすべて新規で購入せよとのことだったので、3人で、ひとりあたま3万冊近い本をひと月程度で選ばなければならなかった。正直、腕まくりより裾をまくって逃げ出したかった。
そもそも3万冊の本のイメージなどいっかな湧かない。1年間で読めるのは多くてもわたしは百冊。10年間で千冊。3万冊読むとしたら3百年かかる計算だ。鶴か亀か仙人にでもならなければムリだ。果てしなさ過ぎる。しかも選ぶ本の分野は多岐にわたる。自分が少しは知識のあるエリアだけ選べばいいってもんじゃない。わたしは文学と哲学、社会科学、自然科学、技術あたりを担当したものの、大きな声ではいえないが、文学以外は素人以下だ。文学だってさほど造詣が深いわけじゃない。どうやって選んだらいいのだろう。知識を増やす時間などない。タイムリミットは迫るばかりである。

で、どうしたかというと、わたしは対象を自治体の居住者、それも図書館利用者に絞った。そこに「区民だけじゃなく同業者や上の人のおめがねにも叶う(適う)選書」とか「今まで図書館に縁がなかった人々にも来てもらう」というオプションは混入させなかった。させる余裕がなかったのだ。
まず、居住区内の他館の貸出データと所蔵データをExcelに落とし、知っている関数を根こそぎ駆使してつき合わせ、よく利用されている系統の新しい本をかたっぱしから選んだ。知識に欠ける分、とにかく「まんべんなく本を選ぶ」を心情にした。分類の3桁の数字の本をどれひとつとして取りこぼすまじ、の勢いで、他館の分類ごとの所蔵図書の比率などを見ながら、見境なく選んだ。見境ありで選んだのは、文学(900~)と、以前看護学校の図書室に勤務していたから若干の知識がある医学(490~499)ぐらいである。
出版社名や著者名で、あれ?ちょっと怪しくね?と思うものがあれば(分類159「人生訓」あたりが怪しさの巣窟だった)これまたExcelのフィルターでふるいにかけた。今だから言えるが(今も言うな)ピンポイントで特定の著者名を除いたりもした。あとは冊数を稼ぐために買い物カゴに入れまくった。最初の頃は、カゴが膨らむごとにドキドキしたが、3万冊選ばなければならないのである。四の五の言ってられない。

鼻息荒く、はあはあ言いながら選書数を増やしていき、最初のドキドキもなくなり、妙な快感物質すら脳内に出てきた頃、ふと、お隣とお向かいさんはどうされているだろうと目をやれば、はらぷとよっちゃんも眉間に皺を寄せながら鋭意選書中である。おっ!やってるやってる!やり方は三人三様‥っていうか、事前に選書方法の相談はほぼおこなわなかった。なのでふたりが実際、どんな方法で本を選んでいたかは知らなかったし今も知らない。ただ選ぶ分野だけ割り振って始めたのだった。で、おそるおそるその時点での選書冊数を聞くと、驚いたことに二人とも私の半分も選んでいない!
えーーー!?早くこれを終わらせないと次に進めないし、とにかくやることが目白押しじゃん!なのになのに、その数!?と実のところふたりの肩を揺さぶりたくなった。
が、しばらくして気づいて冷静になった、肩を揺すっても無駄だと。
ふたりは、わたしのような本選びはしないのである。わたしだって最初はわたしなりの方法論(?)で、雑とはいえ気をつけて選んでいた。特に文学は、できれば来館した人に「けっこういい本を揃えてるじゃん」と言ってほしいというちょっとしたスケベ心もあるわけで(後日、すべてムダになるような「実は隠していた古い小説が千冊あるから全部引き取れ」という大事件が勃発したが)、この作家は遡って全作そろえよう、などとやったりもしていたのである。
でもそれより、早く選ばないと間に合わないという恐怖にも似た、使命感とも違う、お尻に火をつけられた状況を一刻も早く終わらせたい気持ちが上回った。苦痛脱出願望が、納得のいく選書をすることより上位概念。
思えばわたしはなにかにつけそうだ。仕事の契約更新や医療機関での各種の説明、高齢家族の施設入所手続きやスマホの機種変などなど、時間がかかることは途中から必ず「早く終わらないかなあ。そのためならなんでもする」になる。選書もそうだったのだ。貴重な経験だったのにもったいなかったと今なら言えるが、そのときは終わらせることしか考えていなかった。
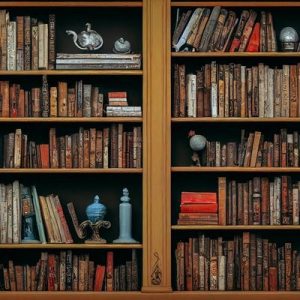
その点、ふたりはちゃんと「選んで」いた。新館の選書担当として正しいのははらぷとよっちゃんである。正しい、という言い方はナンだが、代替語が見つからないので使う。その証拠に、ふたりが選んだ分野の本棚は素晴らしかった。基本は押さえ、深掘り本も並べ、ちょっとした遊び心もある本棚。知る人ぞ知るマニアックな本もあるけれど、それがイヤらしくはないバランス感覚。
わたしが担当した本棚は凡庸。突貫工事の産物。中規模の公共図書館ならまあこうだろうね、の無難な本が並び、時折、ふるいにかけ忘れたトンデモ本も混入されているのがご愛敬。でもまあ、あんなに大雑把に選んだわりには思ったほど見劣りしてもいないかもとそっと胸をなでおろした。分母が大きいってそういうことだ。木は森に隠せだな(隠すな)。
どんなに「早くやらねーと間に合わないよ!」と上司に脅されても(H図書館の元上司がこっそりわたしを脅すので「みんなに言ってくださいよ!」とキレたら「だってオレ関係ないも~ん。新館の館長苦手だし」ってコドモかっ!)、どうせ近々民営化されちゃうんだからテキトーでいいよと悪魔が耳元でささやいても、自分のペースでちゃんと本を選んだはらぷやよっちゃんのような図書館員にわたしもなりたかった。もう遅いけど。
このあともオープンまで本当にほんとうーにいろいろなことがあったけれど、それを書くかは未定である。ずいぶん忘れてしまっているしなあ。
by月亭つまみ