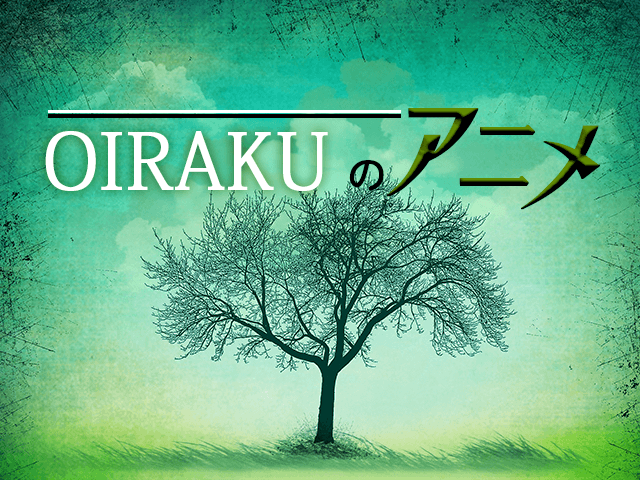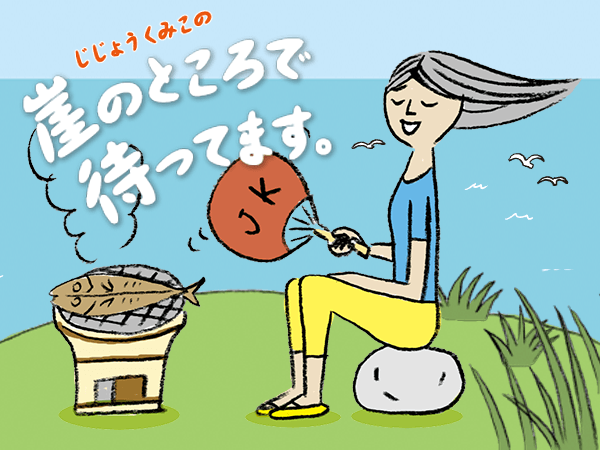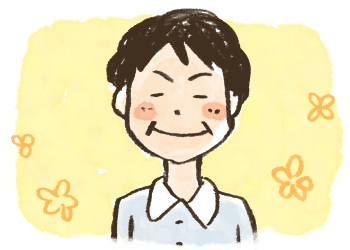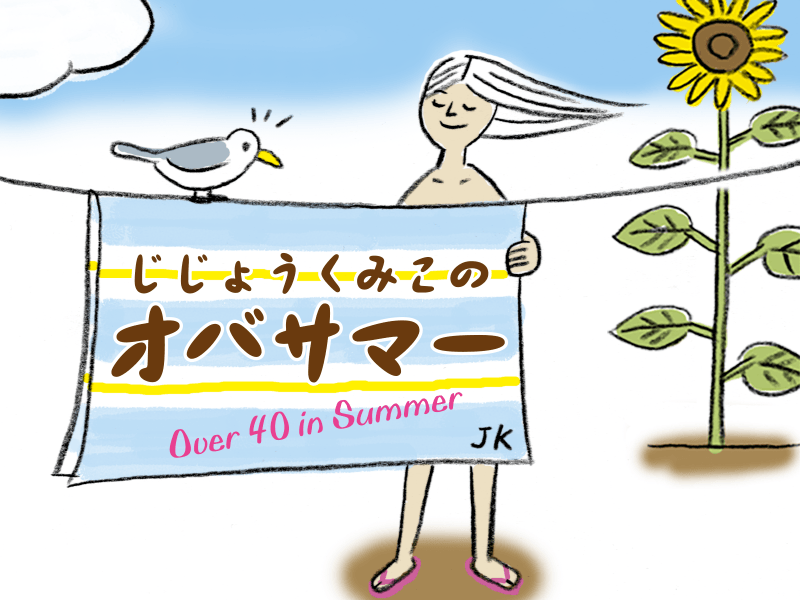「先生」にほめられて、思いのほかうれしかった話。
こんにちは、カリーナです。
昨年秋、「文学学校へ行きます」と入学して、それからポッドキャストなんかでは「いやあ、モチベーション上がりません」とか「忙しくなって、もう、辞めちゃいそう」とか弱音ばかり吐いてきました。
今も、それは変わらないんですけど、昨年、課題の2作品はなんとか提出。どちらも本当の締め切り(ちゃんと学校の本に掲載されて、みんなで合評する)には間に合わず、「チューターからの講評は送られます。でも本には載りません」のほうの締め切りに何とか間に合わすかたちで提出しました。
いろんな講座もあるのにまったく出席せず、学費のもともとれないダメ学生。いいんだ。そういう怠惰さも、やってみなければわからなかった(ということにする)。
でも、1回目の提出原稿にもらったチューターの講評はとても心のこもったすばらしいものなのだったので、それだけで十分。もう一度、もらえるのが楽しみ。提出しただけでもよくやった、と満足していたのですが…先週、「あなたの作品をチューターの推薦で本に掲載することになりました。つきましては、原稿をデータでお送りください」と事務局が連絡をくださったのです。
先生(チューター)が推薦してくれた。…ということは、褒められたということではないだろうか。
こんな経験、いつぶりでしょうか。小学校高学年のとき、父親に戦争体験を聞いて書いた文章が社会科の先生の推薦でコンクールに出された時以来じゃないでしょうか。
だとしたら、半世紀以上ぶり!!
うれしかったです。作品は、初めて「まったく自分が経験したことのないこと」を書いたので「こんなの読む価値なし」と言われるんじゃないかとビクビクしていたこともあり、その意味でもうれしかったです。ま、スクーリングの講評でみなさんに酷評されるかもしれないんですけどね。(でも、前回出席したとき、皆さん、大人で優しく、フォローしつつ批評することがわかったので、メンタルは大丈夫)
先生がいるっていいな。
というのが今回の結論。
先生を慕う(私より年下の女性です)というのも、なんだか、すごく新鮮な気持ち。(入学式でのお話が魅力的だったので、「先生のクラスに入りたい」とわたしから申し上げたのです)
物語を書こうとすると、エッセイ以上に自分の偏見や偏狭な世界観が紛れ込むことに気づくので、もう少し書いてみようかな。
すぐに調子にのるなー。笑ってやってください。
今週もオバフォーは、コツコツと更新します。お時間のあるときに遊びに来てください。待ってます。