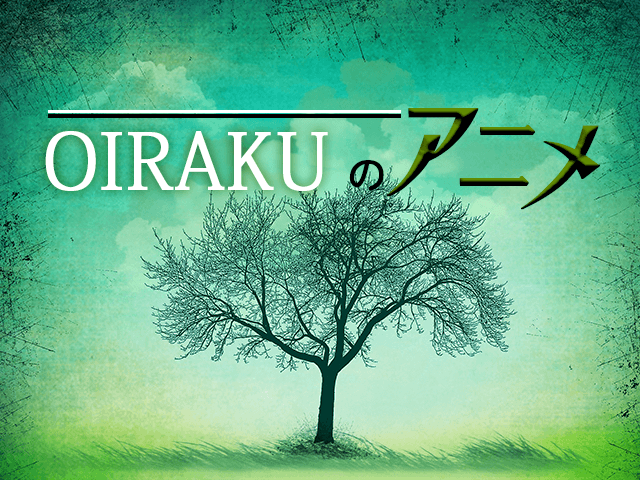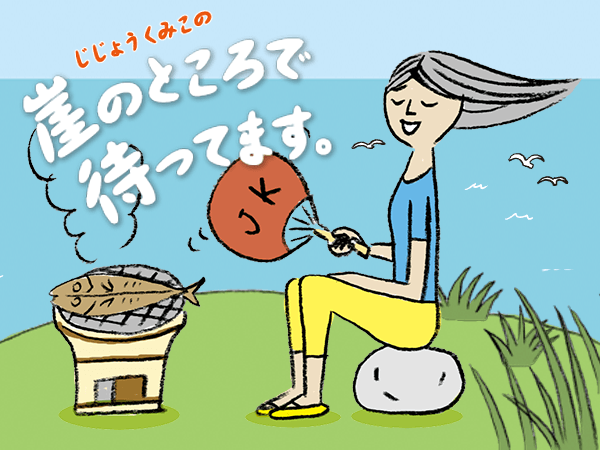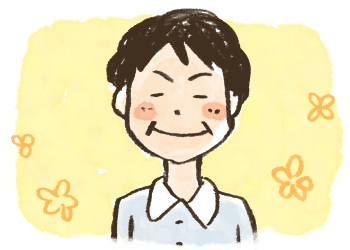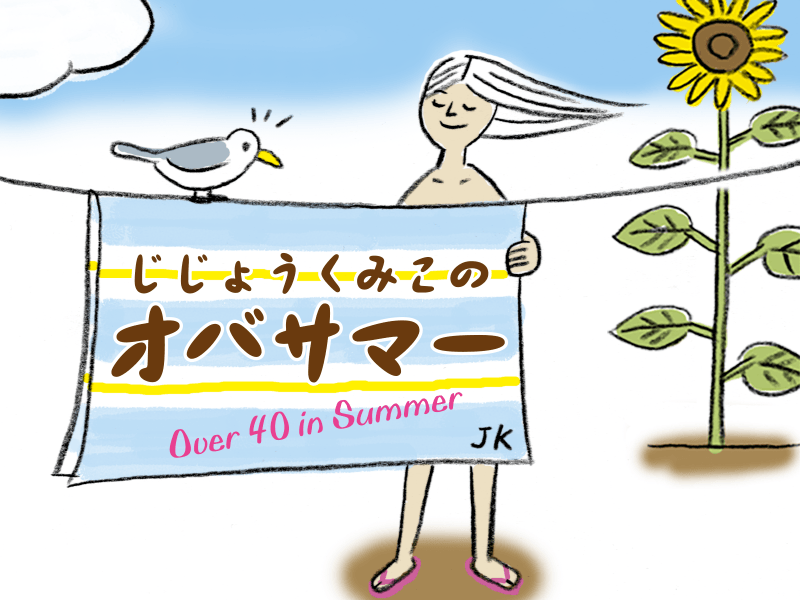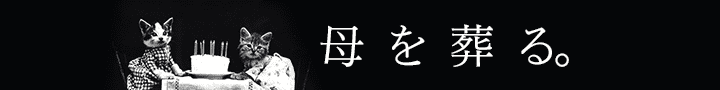(18終)父を葬る(下)
「私は親に愛されたことがない」と散々書いたが、乳幼児のころ父に可愛がられていた記憶がある、そういえば(←それだけ印象が薄い父)。母が厳しくしつける分、父のことは優しく感じられたものだ。
しかし、長じてくると、母のおかしな理屈と戦うこともせず、嫁姑問題で姑の味方ばかりする古い価値観の持ち主であることがわかり、父のありがたみは無くなっていった。
それでも、乳幼児のときの記憶は消えない。
父が老人ホームに入居する際に、ケアマネージャーから、父の性格や趣味、どのように過ごしてほしいかを聞かれると、「好きなお酒を飲んでのんびり過ごしてもらえたらと思います」などと口走る。どこの親思いの子なんだよ、というセリフ。
そこで感じる、「親に愛されている子」を演じている感覚。そうだったらいいな、そういう場合はこうするんだよね、と何かをなぞっている感覚。
私にとって唯一の「親に愛された(かもしれない)」と認識できる記憶に、私はすがっているのではないか。母に愛されなかった分、その代役を、父に求めてしまっているのではないか。
キモ!
実家の片付けをしながら母の日記をむさぼり読んでいるところに、別の部屋を片付けていた父がやってきた。咄嗟に私は日記を隠した。なぜだろう。母という異常な人間に苦しめられたもの同士として、この日記をネタに宴会をしてもいいぐらいなのに。
この行動を見ていた夫が私に、「100年の恋も冷める」と言う。母親の虐待は直視して、あれだけ断罪したのに、なぜ父親にはそうしないのか。虐待を傍観していた人間も同罪ではないか、無かったことにしようとするなんて見損なった、と。
それは、「親に愛された自分」という、ほんの少しのとっかかりであってもそう思い込みたい役柄を演じることができなくなるからだ。
父は私を守らなかった。幼いときだけでなく、私が母と絶縁していたときも、「親とは仲良くしなさい」と言うだけで、母がいかに異常かを説明しても理解しようとしなかった。「苦手な人ともつきあわないといけない」などと言う。加害者と仲良くしろと被害者に言うなんて、最低だ。
今でさえ、私が母の遺骨を実家に放置していることを、「持って帰りなさい」としきりに言う。父は「施設には置く場所が無いから」と主張するが、だったら散骨でもなんでもすればいいわけで、単に私に「親孝行な娘」をやらせたいだけ。
それでも私は父に、「私を守らなかったのはひどい」と真剣に詰め寄ったことがない。破綻して「親に愛された自分」という役柄を演じることができなくなるのが怖いから。日記という確たる証拠は、偽りの関係性を破綻させてしまうから、隠しておきたいのだ。
なんという欺瞞。
毒親を拒絶できない人は、おそらく、「親に愛された自分」に執着しているのだと思う。そりゃそうだ、「親に愛されなかった自分」なんて悲しすぎる。そう自覚するたびに、体中の力が抜けて、生きる意欲みたいなものがまったく無くなってしまう。
母にされたほどの虐待なら絶縁しやすい(少なくとも私は)。しかし、父はそこまで強烈ではない。ただ、何もしないだけ。このじんわりとした拒否。本当は守ってくれなかった。本当は私の言っていることを理解しない。本当は私の行動を、自分の価値観に沿わせたいと思っている。しかし、さしたる強制力はなく、やんわりと、やんわりと私を否定する。そして幼いころにかわいがってくれた記憶。
あーもう、めんどくせーーーーー!
母を葬るなら、父も葬らねばならない。いや、葬りたい。
いっそ、父に、母の日記を見せよう。見せてみよう。自分と娘の罵詈雑言が書かれた日記を目にすれば、私の傷みを理解するのではないか。であれば、真に私は「親に愛された自分」になれる。
母に罵倒されたもう一人の仲間である夫が、日記の要所要所、私を口汚く罵っている部分だけでなく、父がショックを受けそうな部分、父が知らなかった母の秘密(たとえば、不貞につながりそうなこと)を選んで、嬉々として付箋を付けていく(彼なりの復讐なのだろう)。
90歳の老父に、母の日記をこんな目的で読ませるというのは、ものすごく悪趣味だと思う。しかし、父を母の代役にしようとする浅はかな気持ちを葬りたい。それに、人はいくつになっても、自分のしたことに責任を取らなければならない。
その夜、いつものように実家の片付けの後に和食屋に父を連れて行き、酒を飲んでいる父に、私は意を決して母の日記を見せた。「私たち、仲間だよね? あんな異常な人に大変な目にあったよね? 私がされてきたこと、わかるでしょ? 私たち、こんなふうに罵られてるんだよ」と。
神妙な顔で日記を読む父。顔色が悪くなる。これは効果あったか!?
しばらくして顔を上げた父いわく
「こういうことは誰にでもあることだと思う」
「亡くなった人のことを悪く言うのは良くない」
「ネガティブなことを書いたら固定されそうなので、自分は日記には書かず、すぐ忘れるようにしている」
以上。
えーーー! それだけーー!?
昔、罵られて手が出てたよね? ネガティブなことに向き合わないからそうなってんじゃん? 死んだ人の罪は帳消しって、無責任すぎない?
「ということは、私がされてきたことはいまだに理解できないわけ?」
「ひどいことをされていたとは全く思っていない」
えーーー! こんな罵詈雑言が記されてるのにー!? これは傍証にすらならないの?
あっっそ…。
予想していたとはいえ、ちょっとしたひび割れさえも入らなかった、鉄壁の鈍感力に脱力する。これらのことは脳内から消去するのだろう。ただただ自分の平穏さを保つために。
「わかりました。遺骨は大事にはしません。あなたが私の味方でないなら、好きにさせてもらいます!!」
そう宣言した。
父の目の前にいる私は、ただの「自分の娘」であって、一人の人間ではないのだろう。母親の虐待から生き延びた、個性ある人間ではない。「自分の娘」として、老人となった自分の手伝いをしてくれればいい。それだけ。悲しいけれど、そうなのだ。
二兎社の芝居「こんばんは、父さん」は、いい気になって落ちぶれた父親と、父親に強制された人生を歩んで、結果同じように落ちぶれた息子が、かつて充実していた彼らが過ごしていた町工場の廃墟で再会する話だ。男社会の嫌さ加減がいい感じに詰まっている。ラストに父親が「好きなことをさせてやれば良かったな」とつぶやくと、息子は、幼いとき、憧れの父親を見ていた同じ場所に座って、乾杯する。
私の人生には、この結末は存在しなかったんだなあああああ。
悲しいとき、さみしいとき、しょんぼりしたとき、誰かにいいこいいこされたい、抱きしめられたいなあと思う。子どもだったら、普通は親がそうしてくれたものなんだろうか。今も昔も私はそれが叶わないから、猫を抱きしめようとしたり(先代猫はしぶしぶさせてくれたが今の猫たちは拒否)、夫にわがままを言ったり(そして喧嘩になる)、散財したり、いわゆる「推し」に依存したりしてごまかそうとする。
私は母に愛されなかったし、父にも本当の意味では愛されなかった。「親に愛されなかった自分」、それでいいではないか。と思いたい。
そもそも、無条件に愛してくれる人なんて、いないだろう。どんなに良い親だって、子どもを100%愛するのは無理なはず。そんな神様みたいな人、いるわけがない。
だったら、本当の意味で、無条件に自分を愛せるのは、自分だけなんじゃないか。
そうひらめいた瞬間、幼い私がふかふかの白いベッドの上で笑っていた。