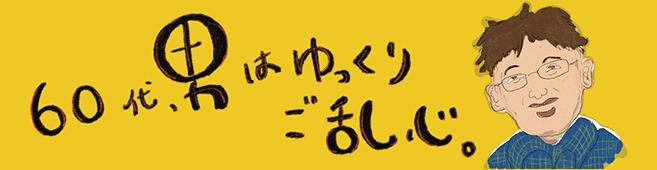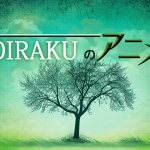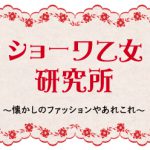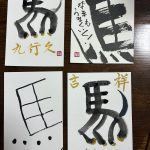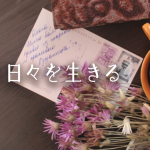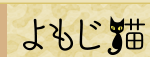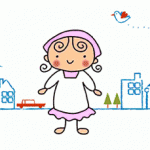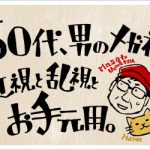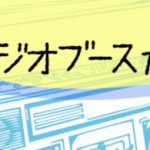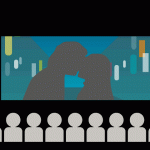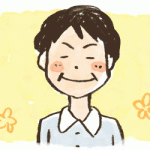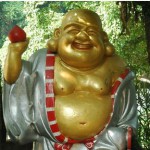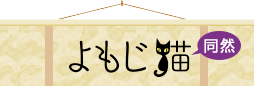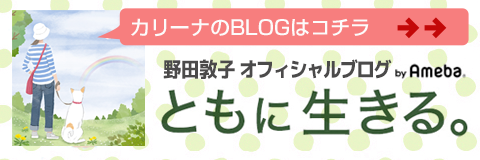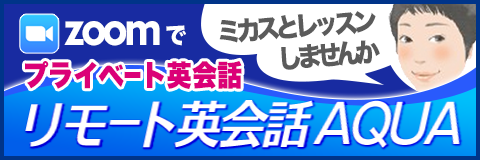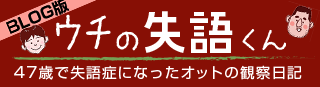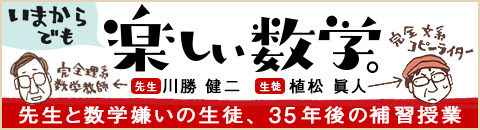Posted on 2025年5月14日 by uematsu
「生きづらい」がデフォルトになったらしい。
気が付くと、映画も小説も歌も、言葉を使う表現のすべてのテーマは「生きづらい」だ。昭和の時代は、価値観も優しさもすべてが偏狭で、仕事だって遊びだって、やりにくいやりにくいと言っていたはずなのに。男女同権が叫ばれて、飲みニケーションを撲滅して、産休だって育休だって取りやすくなって、もう令和になったら、みんなが幸せになるはずだったんじゃないの? なんて思うんだけど、そうはならなかった。
まるで、昭和の町角の小さな医院の待合室で、爺さん婆さんが集まって「ここが痛い」「あそこが曲がらない」と病気自慢をしていたころより、ひどい。なんせ、心が病んじゃってるんだから。便利な世の中になったはずなのに、なぜか生きるのがしんどい。人付き合いも、働き方も、老後も、何かと不安がついてまわる。
で、それに気づいた人が、マウントを取るかのようにSNSで「生きづらいですよね?」と問いかける。すると、「いいね」がつく。共感が集まる。別に優しさが集まるわけじゃない。声も聞こえず、顔も見えない場所から、無責任に「いいね」をクリックすると、それだけで、なんだかSNSが機能して、人と人とが結びついてる気がするから、あら不思議。
「生きづらいなら一緒にご飯でも」なんて言葉、どこにもない。あるのは、「私もそうです」と言っておきながら、あっさりスクロールして可愛いネコの動画を見ている人々の姿だけだ。どうやら、生きづらいことに共感することが、生きづらさからの解決策になってしまっているらしい。万一、「一緒にご飯でも」と誘う人がいたら、きっとそいつは悪い奴に決まっている。
そもそも、「生きづらい」ってのは、そんなに便利に使っていい言葉だったのか。昔の「生きづらさ」は、もっと泥臭かった。上司が理不尽で、親がうるさくて、駅のホームの公衆電話には行列ができていたし、週休1日で、土曜日は半休。満員電車はいまよりひどかったし、飲みに行くと、飲めないって言ってるのに無理矢理飲まされて、トイレで吐いて、道ばたで気を失ったこともある。あの頃の方が絶対に生きづらかったに決まってる。でも、文句を言って、酔っ払って、転んで、気を失った翌朝には、少しだけ気持ちがマシになっていた。
今は、誰も文句を言わない。文句の代わりに「いいね」のボタンをクリックして、そっとフェードアウトする。それを「優しさ」と呼んでいるけど、正直、薄味のまま煮詰まっていく味噌汁のようなものだ。人間てもうちょい濃い味わいのものだった気がするんだけど、それは単なる思い込みかもしれない。
それにしても、「いい人だね」「優しいね」と言われて育ってきた人間ほど、この社会では、見事なまでに潰れやすい。いや、潰されやすい。気が利く。場を読む。空気を壊さない。そういういい子たちが、いつの間にか、何も言えなくなって、何も頼めなくなって、最後には誰にも助けを求められなくなってしまっている。
でも、そういう人たちは、あまり「生きづらい」とは言わない。言わずに、なんとかしようとしている。僕はそういう人が好きだ。不器用だけど、努力を惜しまず、繊細すぎる自分を恨むことはあっても、決して人を恨まない。そういう人に僕もなりたい。
反対に、そう言う人を笑うやつほど、「生きづらい、生きづらい」と声に出しながら、それをぜんぶ人のせいにする。そっちはそれが、生きづらい時代のサバイバル術なのかもしれないけど、こっちはほぼ遭難中だ。本当に努力している人たちが潰される一方で、「生きづらいんですよね」と同情を引くための涙をどこででも流せる奴に「わかるよー」と声が集まり、そんな奴らからは、やらなきゃいけないはずのことも、うっすら免除されていく。
「生きづらい」と言っておけば、全部の仕組みはそいつらを守る方向で稼働する時代だ。まるで、「生きづらい保険」時代だ。使えば使うほど、自己肯定感がカバーされる。そして、根本は腐って、希望はどんどん光を失っていく。だけど、やっぱり、「生きづらい」がデフォルトの時代なんておかしい。
とりあえず、カーテンと窓は毎日開けないといけない。とにかく、光を部屋に入れないといけない。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。