Posted on 2025年9月17日 by uematsu
読書を聴くのは、どうだろう。
Amazonが、聴く読書『Audible(オーディブル)』を日本でスタートさせてから10年経つのだそうだ。最初の頃、サービス期間として無料で使えた時期があったので加入してみたのだが、すぐに離脱してしまった。小説を聴くことには、それほど違和感はなかったのだけれど、声がダメだった。現状は知らないのだけれど、当時は、声優さんやナレーターの人たちがこぞって朗読を担当していて、なんとなく演技過剰で話がまったく入って来なかった記憶がある。
僕は以前から、新潮社が出していた朗読のCDが好きで、よく聴いていた。特に好きなのは、俳優の橋爪功が朗読する『泥の河』だった。橋爪功の柔らかな大阪弁で読み上げられる少年たちのもの悲しい物語は、心に響いた。
でも、これは橋爪功だからいいのであって、例えば、ハキハキといい声で朗読されても、感動は半減してしまう。初期のAudibleを試した時には、そこに馴染めず有料期間に移行する前に退会してしまった。
もちろん、いまはもっと朗読者の幅も広がり、耳馴染みのいい作品も多いのだと思う。後は、小説を読むのと、聴くのとでは、どんな違いがあるのかということだ。ビジネス書なら、必要な情報が得られればいいのでAudibleも有効だろう。ただ、それでも、聴くことと読むことの違いは歴然とあるはず。
僕はラジオやポッドキャストを就寝前によく聞いている。これは読書と違い、もともと声と話している内容がひとつになっていて、自分が好む声と内容を選べばいいのだから話が早い。たとえば、僕もよく聴いているOver40の「That’s Dance」なんかは、話題と声の質がピタリと一致していて、とりあえずその日一日の嫌なことを忘れることができる。声のトーン、間の取り方、言葉の選び方、そして話題の選び方と運び方……全部がその人の表現であり、だからこそ聴いていると心地いいのだろう。
でも、小説は紙に印刷された段階で一旦「完成」している。それを読むスピードやリズムは読み手に委ねられていて、読む人の数だけ受け取り方がある。ゆっくり味わう人もいれば、疾走するように読み飛ばす人もいる。その自由さこそが、小説における「読者の存在」の大切さなんだろう。小説家が、ちょっと仕掛けたリズムを崩した書き方に、読み手はスピードを落として、注意深く展開を楽しむ。そんな、読者それぞれの楽しみがプロの読み手に委ねられてしまうと、もしかしたら、小説の楽しみは半分以上、失われてしまうのかもしれない。
逆に、読み手の解釈が入り込む分、そこに気づけるという楽しみ方が生まれるかもしれない。還暦を過ぎ、なかなか集中力が続かない。そんな時は、思い切って、誰かの解釈を楽しむつもりで、小説を聴く、というのもいいかもしれない。そんなことを思い出している、まだまだ暑い、秋の夜長。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松眞人(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。



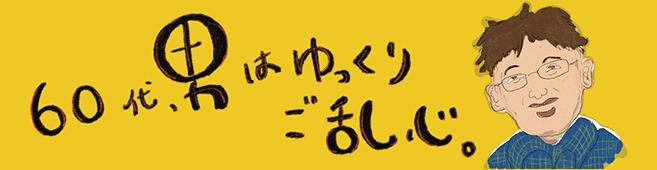


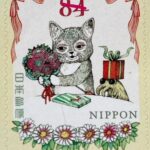







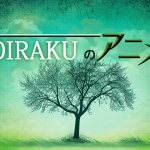

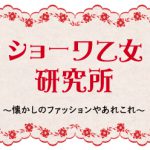




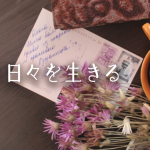

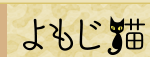

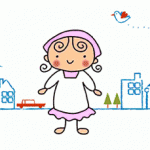

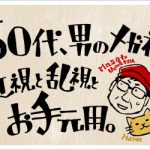









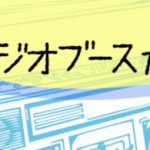








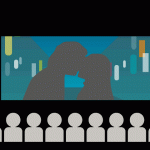
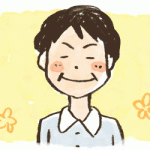



















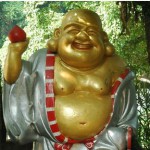




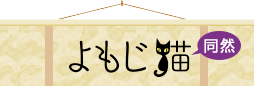




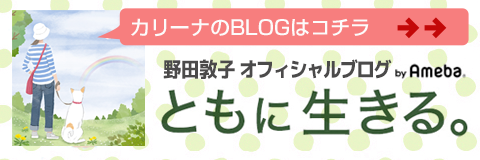
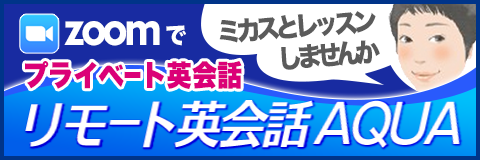
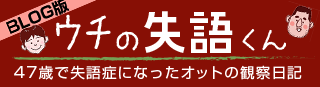
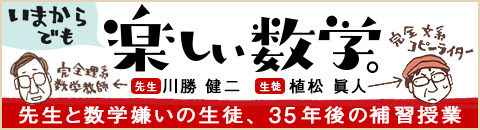

kokomo
植松さん、Audibleの声との相性ってとてもよくわかります。
私もAudibleのお試し期間中にいくつか聴いてみたことがあるのですが、声の質、読み方、スピードがなかなかしっくり来ず、途中でやめてしまうことが多かったです。
自叙伝をそれを書いた俳優さん自身が読んでいるものを試したことがあります。
本人が読むんだからこれは確実だよね、と思っていたのですが、妙に生々しくて聴くことに集中できなくなってしまい、結局は脱落してしまいました。難しい...
とはいえ、集中力がぶちぶち切れる今日この頃。「ながら聴き」できるのは大きな利点なので、大きくは期待せずに再度試してみるのもよいかな、と植松さんのように思っていたところです。
植松さんが書かれているように、「That’s Dance!」って声の質と話題が一致しているんですよね。三人の声は雑談向きの声(笑)!
uematsu Post author
kokomoさん
そうなんです。しっくりこないんです。
その点、新潮社の朗読のシリーズは、宮本輝の『泥の河』を橋爪功が朗読したり、太宰治の『斜陽』を奈良岡朋子が朗読したり、向田邦子の『父の詫び状』を渡辺美佐子が朗読していて、どれもしっくりくるんです。
そのあたりのディレクションがきちんとできてないと、なかなか難しいと思うんですが、もしかしたらビジネス書なんかはAIに読ませる方がいいのかも。いや、もっと気持ち悪いかな。NHKが実験してるとこまで完成していれば、妙なアニメ声よりはいいかもしれません。
爽子
オーディブル、「国宝」はとてもよかったです。
それで、はまって、まだ解約できずにいます。
国宝は3回聞きました。
来月解約。。。とおもってたのに、ドリアンロロブリジーダさんが、オーディブルの
録音をしたと、今日インスタで見てしまい。
解約できなくなりました。
朗読者の声との相性はたしかにあります。
あんまり感情移入せず、さらっと読んでもらえるほうが聞きやすいですね。
カフネの中谷美紀さんはよかったです。
uematsu Post author
爽子さん
「国宝」、聞いてみたくなりました。
声がハマれば一人舞台みたいでいいかも。
サブスクの解約に関しては、僕は動画配信を入ったり、やめたり。特にDisney+は「Shogun」とか話題作があるたびに、加入して、解除忘れて、やっと解除したと思ったら、また入ってを繰り返しておらず。