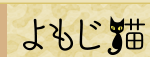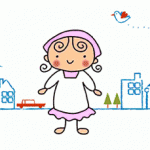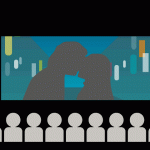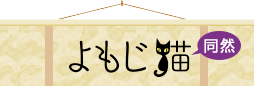Posted on 2026年1月8日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.101 頼もしくて誇らしいひと
2026年、中島京子さんはどこに行こうとしているのだろうか。
ふつう、誰かについてこんなふうに書くのは、迷走しているとか、そっちに行かない方がいいんじゃないか、みたいなネガティブな気持ちになった場合が多い。でも今回はそうではない。稀代のストーリーテラー(とわたしは思っている)中島京子、たとえ最新作に作者と見紛うような「書けなくなった小説家」が登場して、小説の書き方を忘れてしまったと泣き言をほざこうが、こっちはなんの心配もしない。泣き言からの~!?と、どこに行くのか楽しみでいっぱいになる。
なんとなれば、中島京子さんはもう、方向性とか書き方なんぞにこだわる段階を超え、自身が設定した小説という鋳型からすら解き放たれようとしているのかもしれない。一昨年から昨年にかけて読んだ『うらはぐさ風土記』『坂の中のまち』 『水は動かず芹の中』でそう思った。
三作に関連性はまったくない。でもなんとなく似ている。それが要するに「解き放たれようとしている感じ」ってことなのかもしれない。過去と現在を同じ俎上に乗せ、自在に、時に破天荒に行き来する脳内宇宙の自由さを、本人がなにより驚き楽しんでいるように見える。そこが似ているのかもしれない。
中島さんはいままでも、過去の名作をモチーフにした作品を複数書いてきてどれも面白かったが、以前よりギアを上げているように映る。齢を重ねて、よりギリギリのところを攻めている感じ。そのスリリングさとチャレンジャーなところが、世代的にはわりと近いわたしには、頼もしくて、誇らしい。頑張れ、中島京子!思う存分やってくれ!と思う。
『うらはぐさ風土記』は、長い海外生活を終え帰国し、東京は武蔵野の伯父宅で暮らすことになる50代のシングル女性が主人公だ。この地での、派手さはないが個性的な人々との交流が、ただアットホームだけではなく、地に足のついた、それでいてフットワークの軽い筆致で描かれていて落ち着く。一見淡々としているが油断できない展開で、いつのまにか読み終わってしまった。
『坂の中のまち』は、同じく東京だが、文京区小日向の坂道が舞台である。こちらは『うらはぐさ‥』よりファンタジー色が濃い。そう、坂道は異界と通じているのだ。名だたる文学作品が登場し、それに呼応するように、自分の内部がじわじわ深みにハマっていく怖さと心地よさ‥うん、やっぱりこの作の真骨頂はこのあたりだ。
そしてそして、最新作『水は動かず芹の中』である。
まさか、こんな話だとは思わなかった、とページをめくるごとに思った。なんなら口にしていたかも。書けなくなった中年の女性作家が気分を変えるために唐津を訪れ、導かれるようにしてとある窯元に陶芸体験に行くことになる。不意打ち感丸出しで歓迎のそぶりも見せない、決して初対面には愛想のいいタイプではない窯元の主人サワタローだが、小説家は彼とその妻から「水神夜話」を聞くことになる。
水神ってなんだ?
完全な神様ではない。水の中に棲む、人間と神の境い目のような存在だそうだ。ここでは要するに河童なのだった。いわくありげなサワタローと妻の話はどんどん拡がり、秀吉の朝鮮出兵にたどり着く。ここからが本番。小説家は引き込まれ、この窯元に東京から幾度も通うことになるのだった。
現実と妄想の境い目のような話好きであることはこのサイトで幾度も書いているが、『水は動かず芹の中』はまさにそれ。「境い目ファンタジー」ジャンルの中でも(そんなジャンルがあったとして)、突拍子のなさでは、かなり上位に入ると思う。まさか、朝鮮出兵のそこここに河童がいたとは。
もちろん豊臣秀吉が登場し、河童にも猿と呼ばれたりするし、利休に「きゅうり」という名をもらう水神も登場するが、サワタローの話の中では、小西行長の造形がダントツで秀逸だ。行長は元は河童だったのではないかという匂わせもあり、その証拠に、彼は彼に近づく河童を素早く察知し、己の戦法どころか誰にも口にしないであろう本心まで語って聞かせるのだ。朝鮮の最前線で戦い、飢え、欺き、心身を病んでいく行長の闇が凄絶だ。
と、読んでいて、あれ?わたし、秀吉の世紀の悪手である朝鮮出兵のことを案外知ってるなと思ったら、8年ぐらい前、敬愛する飯嶋和一の『星夜航行』を読んだのだった。あの小説の朝鮮出兵の描写も凄かった。今回の入れ子の中の歴史小説も相当凄い。歴史の汚点は後世の書き手の筆力と想像力の源になるのかもしれない。
中島京子さん、これからも気の向くまま、心が動くまま、縦横無尽に脳内宇宙を駆け回って小説にしてほしい。読むから。
by月亭つまみ