◆◇やっかみかもしれませんが…◆◇ 第39回 極私的死生観?
振り返れば、あれが最後だったなあと、後々思い起こしたりすることは、ままある。
知人やその親族の訃報に触れると、条件反射のように「最後に会ったのは…」と思う。長く闘病していた家族に対しても、亡くしてから「最後にちゃんと話した(意思の疎通ができた)のはあのときだった」と振り返って涙することがある。
学校や仕事や住まい、パートナーとの合意の上での別れなどは、最後を認識しやすいし、最後=人生の節目 になりがちなので強く印象付けられるが、物件の数的には、無自覚に通り過ぎる方が多数派なのではないか。
…というようなことを考えたのは、一昨日のミカスさんの記事を読んだからである。母親と手をつなぐ、というエピソードから思い出したことがあったので、Twitterで以下のようにつぶやいた。
母が存命で、でもかなり年老いてきた頃、一緒に歩いていて道を横断する際、前に水溜まりか何かがあったので前を行く私が「ちょっとこの先」という気持ちで手を出して母を制したら、勘違いしてその手を繋いできたことがあった。正直、少し嫌だった。でもそれが歩く母と手を繋いだ最期だったと今思った。
当時の自分の、母に対する一筋縄ではいかない気持ちは、罪悪感や贖罪方面を行使してもスッキリとは処理されないし、逆に「ずっと『母親の呪縛から逃げなくちゃ』と思わされる娘だったのだから、手を繋がれてとっさに嫌だと思ったのも致し方なし」というベクトルでも完全に折り合いがつかない。今もってなお、消化も昇華もされ切っていないのだ。
母が死んで20余年になるというのに、いまだにそんなことを言っている私はどうかしているのだろうか。
手を繋ぐこと同様、秋になって柿を見ると胸が騒ぐ。

50歳間近で離婚し実家に戻った母親は、それから70代なかばで亡くなるまで会津で暮らした。福島はフルーツ生産県としてわりと有名だが、同じ福島県でも、会津のくだものと言えば絶対的に柿なのだ。みしらずと呼ばれる柿。
自分の身の程も知らずにたわわに実をつけることから、その名がついたという。甘くて、大きくて、種がなくて、つるんと円形で見た目もよい「みしらず」は皇室への献上柿でもあり、会津の自慢なのである。
母は亡くなる前年まで、この柿の豪華木箱ヴァージョンを、東京に「嫁いだ」娘に送り続けた。自分の母親から引き継いだ細々とした商店経営を70歳直前まで続け、その後は子どもからの仕送りと少ない年金でかつかつの生活をする母親にとっては安くない贈答品である。でも一度として途切れることはなかった。依頼するのはいつも同じ、今はなき喜多方市の八百吉青果店だ。

八百吉の三男坊と私は、高校時代の終わり頃に付き合い始めた。彼、ヨシヤマ君は、バスケット部のキャプテンをしていたので校内では有名人だったが、その肩書からイメージしがちな、シュッとしたりクールでかっこいいタイプではなく、お調子者の熱血漢で、お勉強もそんなに得意ではなかった。
高3の秋、隣同士の席になった初日に、彼は私に「ノートを写させてくれないか」と言った。私が、自分の字は読みづらいから他を当たってくれと言うと「月亭さん!欠点は隠しちゃダメだ」と意味不明なことを言った。
その年の大晦日の「三時のあなた」で、年末の帰省の混雑を実況したとき、上野駅のホームで帰省客としてインタビューされたのは、近日中に受験する大学の下見に行った帰りのヨシヤマ君だった。インタビュアーに「実家に帰ったら何が食べたいですか?」と聞かれた彼は「カツ丼!」と即答した。それから卒業までのわずかな期間、彼は全校生徒どころか先生方からも「カツ丼のヨシヤマ」と呼ばれた。
ヨシヤマ君のおとうさんと母は幼なじみで、母は、あのヨシヤマさんの息子と私が親しくなったことを歓迎した。娘は高校を卒業したら東京に行くことになったが、ヨシヤマさんちの息子と付き合っているならいろいろな意味で安心、と思ったようだった。
ヨシヤマ君は受験した東京の大学を全部落ちた。私とヨシヤマ君は、離れて生活するようになり、付き合いはフェイドアウトした。数年後、私が別のひとと結婚した秋に、八百吉経由で初めて母から柿が送られてきて、無性に母に腹が立った。「おかあさんのそういうところだよ!」と思ったりした。
柿が本当に好きになったのは令和になってからだと思う。毎年見続けた木箱の中身を、当時の私はさほどうれしいとは思わなかった。母が「子どもに迷惑をかけないように暮らそうと思ってる」と口癖のように言うたびに、だったら柿なんて送ってくれなくていいのにと思っていたし、直接言ったりもしていた。
母にとって娘に柿を送ることの意味を、私は母が死ぬ間際まで考えたことがなかった。
母は梅雨どきに亡くなったが、まだ会話が成立していたとき、「今年は送れるかなあ、みしらず」と私に言った。自分がどう答えたのかは覚えていない。でも、母がそう言ったこと、柿を送ることが母には重要なことだったのだと気づいたこと、はありありと覚えている。母の口が「みしらず」と言った最後は間違いなくあのときだ。

今、柿を食べるときに押し寄せるせつない感情は、憎らしいほど経年劣化しない。その生傷っぽい感触の長きにわたる痛みに、しょっちゅう泣きたくなる。そして、こんなに長い年月が経ち、こんなに遠くまで来たのに、自分はどこにも行けず、母はどこにも去らないことに、絶望と安堵を覚える。
同世代の友人知人の親が健在だと聞くと、少しだけやっかむ。まだ、絶望と安堵の比率を変えられる可能性があることがうらやましいと思う。実際は、悪しき方、不本意なベクトルで変わってしまうかもしれないが、それでも可能性があることが、ただうらやましい。
同時に、亡くした者だけが味わう境地を彼らは知らないのだとも思う。それは、乱暴に一言で括れば、自分の本当に近しい人は、自分が死ぬまで死なない、だ。
by月亭つまみ







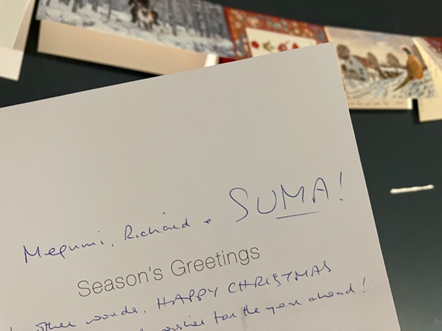


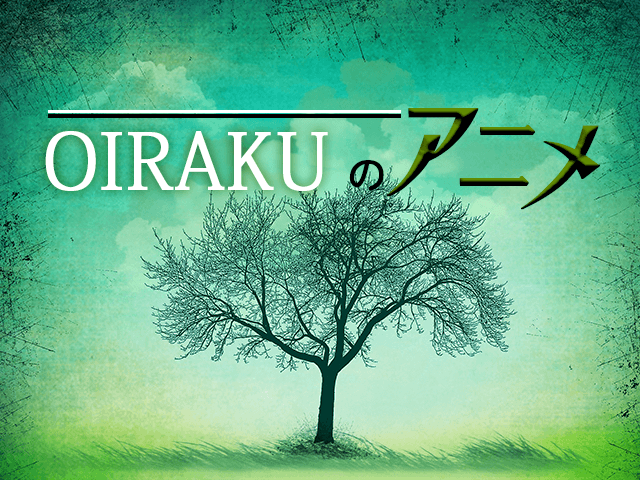








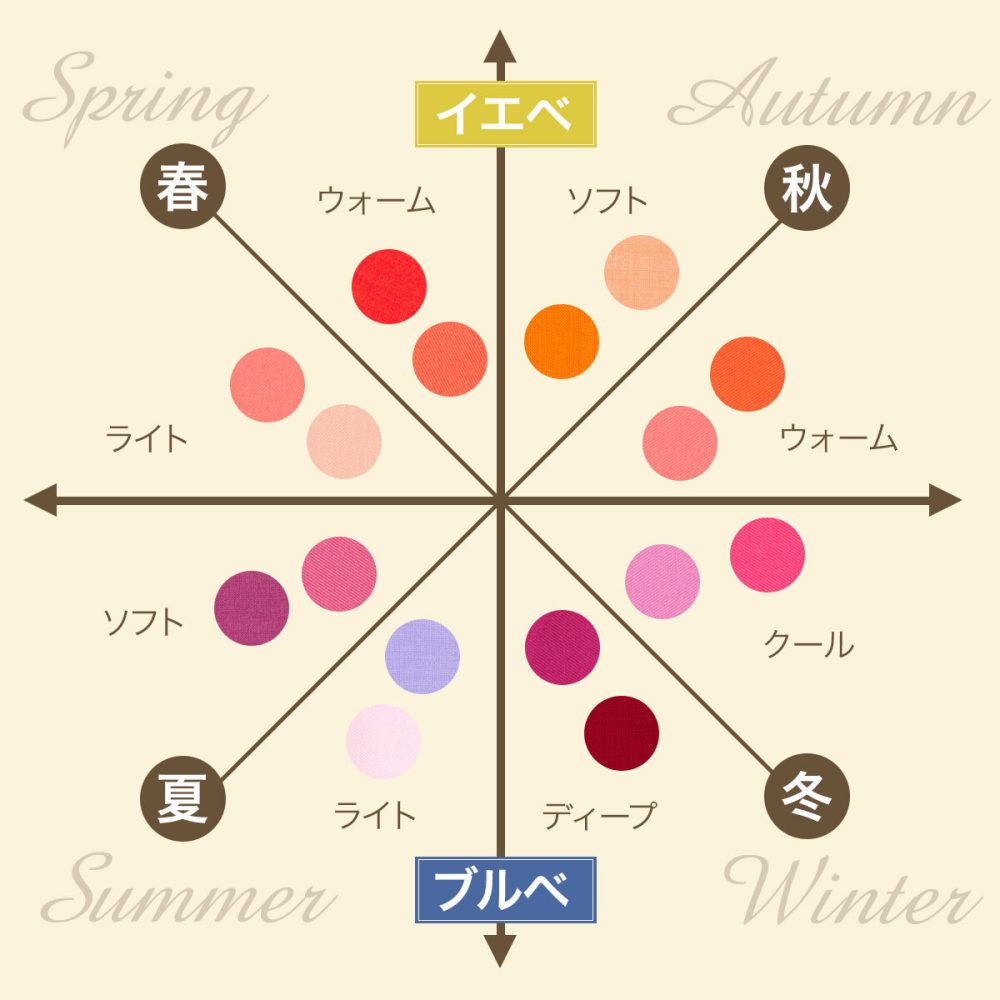


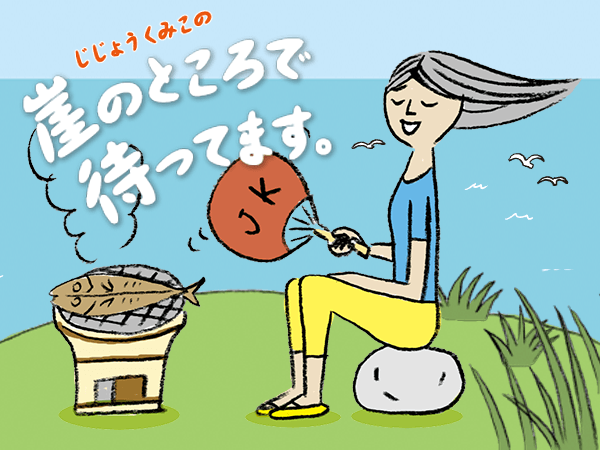
























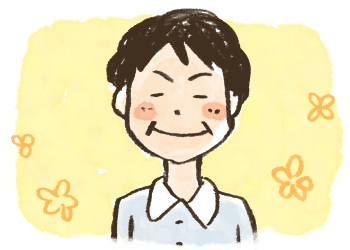
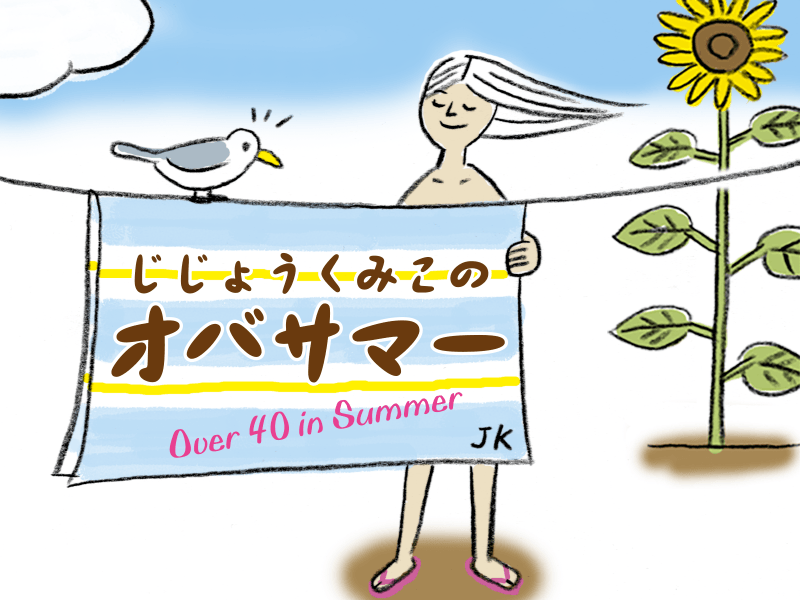



































あんな
あああ………85でまだヨロヨロしながらも一人で住む母は、毎月、段ボールいっぱいの野菜を送ってきます。実は半分は腐らせている、冷蔵庫に入りきれないたくさんの野菜たち。私は決して買わないであろう、季節や地方の野菜たち。そして毎回、感想を言わされるまでが一連の儀式。。この有難いとも迷惑ともなんとも言えない甘酸っぱいような、何かで古い血に繋がれているような呪縛感は、きっと母が亡くなったとしても処々で思い出させられるだろうな、と思っていましたが、まさしくミカスさんがおっしゃられる通り、私が死ぬまで止むことはないのですね。あまりにタイムリーなので、ついコメントさせていただきました。まだ玄関脇に置かれた今月分の段ボールを見ながら。。
いつも楽しみにしています。
ありがとうございました。
つまみ Post author
あんなさん、コメントありがとうございます。
母親からの、生鮮食品の詰まった箱にはどうしてせつなさがあるのでしょうね。
確かに、甘酸っぱいがしっくりするような。
老いと母親、それだけでも、鼻の奥がツンとする素材(?)ですが、不随する正負がカオスのように入り混じった感情、もう言葉にできません。
楽しみにしています、とおっしゃっていただいて、本当にうれしいです。
これからもよろしくお願いいたします。