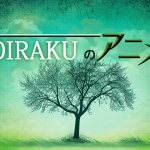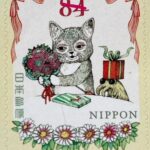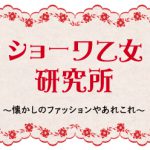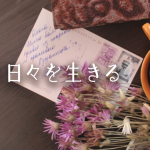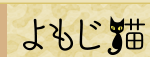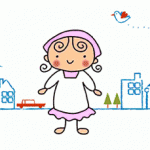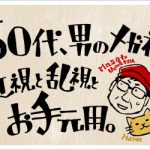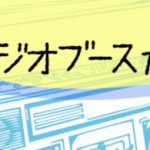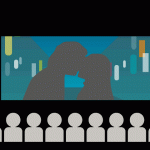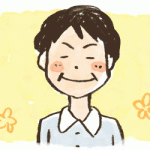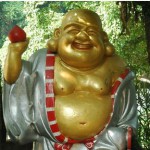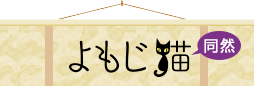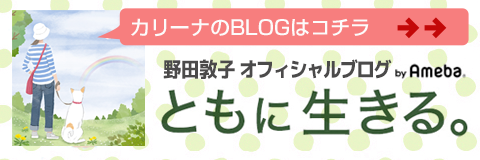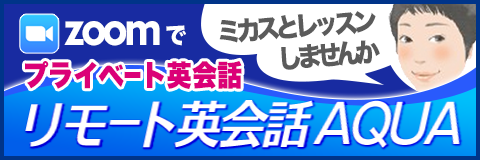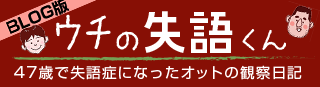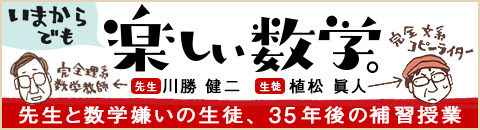Posted on 2025年7月24日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.97 女優ライトをぶっ壊せ!
人生に武器が必要だとしたら、そのツートップはユーモアと知性だと思っている。
勉強ができるとか、知能が高いことが知性なんかじゃないのは言わずもがなだ。お勉強ができるバカ、知能が高いすっとこどっこいは山のようにいる。謎の上から目線。だが、せっかく高性能な知能や学力が標準装備されていてもイコール知性とはならないのは、オプション装備の余地を存分に感じておもしろい。知力にしろ体力にしろ財力にしろ、量より質、要するに、何にどう使うかを的確に判断できること、それが知性なのかもしれない。
2019年に刊行され、このたび映画化され来年公開予定の『急に具合が悪くなる』宮野真生子・磯野真穂/著(晶文社)を読み、その圧倒的な知性に玉砕感にも似た心の震えを感じた。ほんの少し(ホントに少しだけですよ)の不満とともに。

哲学者の宮野真生子氏と文化(医療)人類学者の磯野真穂氏の往復書簡の書籍化だ。宮野さんはこの書簡の8年前から癌を患い、病と共存しながら精力的に活動を続けてきて、身体と食べ物のつながりを文化人類学的見地から考えるワークショップが縁で磯野さんとメールのやりとりをするようになる。そんなある日、宮野さんは磯野さんに「急に具合が悪くなるかもしれない」と表明するのだ。
病気のことは聞いていた磯野さんだが、そんなに悪い状況だとは思っていなかったのでその言葉に驚き、一度は「多発転移」や「余命」というワードを検索するものの、自分が深掘りする場所はそこではないと考え直す。「急に具合が悪くなる」という言葉の意味、宮野さんがそれを自分に伝えた理由、自分がすべきことをとことん考えるのだ。この往復書簡はそんな磯野さんではなく、宮野さんからの提案だという。魂の選択だ。
書簡は2019年4月27日から同年7月1日まで10往復続く。あらためて期間の短さに驚く。宮野さんは本当に急に、そしてどんどん、具合が悪くなってしまったのだ。とはいえ、ふたりのやりとりは最後まで冷静なトーンだ。ユーモアがあってネガティブな気配はあまりない。雑談からはじまり、病、生きること、死、医療、学問、言葉、愛などについての思索が自然な感じで綴られている。
この往復書簡の書籍化はわりと早い時期から決まっていたようだが、宮野さんが自身の執筆分の校正を最後まで終わらせることは叶わなかった。7月22日に亡くなったのだ。

病を得、いよいよ死から逃げ切れないところまで来たことを知ってからの宮野さんは、月並みで雑な表現だが、強くてかっこいい。併走する磯野さんも胆力が抜きんでている。宮野さんのご指名を受けたことの意味と自分の役割を腹の底から理解していてさすがだ。
わたしはこの書簡でのふたりしか知らないが、知性に置いた軸足がブレたりふらつくことがない。宮野さんに関しては、肉体的な苦痛が一気に増し、自分の残り時間がどんどん削られていくのが明らかな中、生が終わる直前まで、この完成度で文字を紡ぎ出したということにただただ圧倒される。その矜持を支えたのもやっぱり知性だと思う。この往復書簡の存在、そのパートナーを選ぶ際の慧眼が彼女の軌跡の奇跡を生んだことは想像に難くないが、読み終わって一週間経った現在もまだ畏怖のような尊敬のような、まさに畏敬の念が、ありありと自分の中に残っている。
この本で心にヒットした箇所を挙げるとキリがないが、宮野さんの文章を一箇所だけ引用する。
【私が「いつ死んでも悔いがないように」という言葉に欺瞞を感じるのは、死という行き先が確実だからといって、その未来だけから今を照らすようなやり方は、そのつどに変化する可能性を見落とし、未来をまるっと見ることの大切さを忘れてしまうためではないか、と思うからです。】
最近、亀石みゆきさんのZINE『死ぬのが怖くて死にたくなった日記』を読んでとても励まされ、深く心に響いた理由がこの文章で腑に落ちた。

誰にとっても死という行き先は確実だ。このサイトの主宰者カリーナさんのPodcastでの言葉を借りれば「人間、死ぬかトシとるか、どっちかしかないんやから」だ。そして、病の出現や進行によってどうしても病以前より死の輪郭は鮮明になる。でも、だからといって、病を得たら否応なく死の輪郭内で生きる人にされて当然なのだろうか。そっちに引っ張られる自分になす術は何もないのだろうか。
病が出現しても、リアルタイムのその人にまぎれもなく存在する、必ずしも生死に限らないものも含めた陰影に満ちた各種の可能性を、死が照らし出してくる強力な女優ライトで一網打尽にされるのは、悲しいとか淋しいとか残念とかいうより安直でもったいない、と思いたい。女優ライトにはそりゃあ目も眩むだろう。でも、だからといって、生きてきた自分、生きて行く自分から発せられたすべての光とその影のかけがえのなさを根こそぎ絡めとられる筋合いはないと思いたいのだ。
とはいえ、自分も死という女優ライトを当てられたら、あっけなく、なんなら一瞬で自分の可能性を見失い放棄してしまうかもしれないという恐怖はある。だから、死の輪郭に現在の生を凌駕させない、でも拒絶というのではなく「共に在るもの」としながら生活や仕事や趣味や思索に舵を切った、女優ライト デストロイヤーの宮野さんや亀石さんに勇気づけられるのだ。
この本の「ほんの少しの不満」は、磯野さんが「不運」と「不幸」を混在させ使用していた箇所があったことだ。宮野さんがそれに対する違和感を表明し、磯野さんが謝罪し、そうなった理由も書き、それがきっかけで「不運は点、不幸は線」と定義づけるにいたったのでケガの功名と言えなくもないのだが、若い頃からこのふたつの言葉の違いにわりとナーバスだったわたしとしては、どんな理由があるにせよ、ほんの少しの不満が残ったのだった。昔、自分が日記に「不運は二次元だが不幸は三次元だ。三次元にしてたまるか!」と青さ丸出しで力強く書いた(単に筆圧が強いだけ)記憶をここに記し、ちょっと溜飲を下げてみる(そんなところで下げるな)。
by月亭つまみ