Posted on 2025年8月7日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.97 読後に浮かぶもの 『奇のくに風土記』を読んで
現実なのか夢や妄想なのかわからないできごとがある。それは、まだ物心つくかつかない頃の記憶に似ている。
2~3歳のとき、わたしは福島県双葉郡富岡町に住んでいた。そこで、のちに桜の名所と知った夜ノ森公園で花見をした記憶がある。でもそれが自力で生成した記憶なのか、写真を見たり親から聞いた話で覚えているつもりになっているのかわからない。なんなら、あのときの人々の喧騒や自分の視線の動きまで脳内で再生可能なのだが、もしかしたらそれも後付けかもしれないと思ってしまう。考えれば考えるほどわからなくなるのだ。
他にも、この「物心つくかつかないか」という人生の黎明期(?)の記憶or記憶もどきはいくつかある。「物心」という、文字にすると汎心論とかアニミズムを思い起こすこの時期は、似ているどころか現実と夢の境目そのものなのかもしれない。
木内昇の『奇のくに風土記』を読んでそんなことを考えた。
この小説は、江戸時代、徳川御三家の地である紀州に実在した本草学者・畔田十兵衛(のちに翠山)の人生を取り上げた作品だ。木内昇は骨太の時代(歴史)小説の印象があるが、今回は『剛心』『雪夢往来』あたりとは少し趣きが違う。誰もが知っているというより、「知る人ぞ知る」歴史上の渋い(!)人物にスポットライトを当て、本筋は史実を描くものの、それ以外は想像力を自由に広げて描いているところは共通している。が、『奇のくに風土記』は想像力の部分が際立って幻想的なのだ。
それが作品の魅力に直結していると思う。彼岸と此岸、夢とうつつ、空想と現実‥の境界線があいまいであればあるほど、史実に則った小説も(だからこそ?)おもしろくなるという「事実」をまざまざと見せつけてくれて楽しい。そして、こういう作品を読んでいる最中の気持ち良さには若干の背徳感も含まれていて、それがまたたまらない。本当は触れてはいけない、見てもいけない聖域をこっそり覗き見している感覚。やはり野に置けレンゲソウ‥それはわかってるけどね、みたいな。今回は本草学者だけによけいにレンゲソウだ(意味不明)。

身の丈に合う、分をわきまえる‥などという言葉を未来ある若者に発すると、まるで可能性の扉を閉ざす料簡の狭い人間のようだけれど、時空や現実を飛び越え、妖怪や魑魅魍魎の類の垣根すら外した存在が語ると、説得力がいや増す不可思議さ、わからなさや幻惑感が、逆に「なんでもあり」と現実の世界を拡げるような感覚もすこぶる面白い。それもこれも、ど真ん中の人物(今回は畔田翠山)の人物造形が絶妙だからなのだろう。主軸がブレなければいくらでも遊べるし戻って来れるのだ。
『奇のくに風土記』を読んだら、すでに2回ずつは読んでいる梨木香歩の『村田エフェンディ滞土録』と中島京子の『イトウの恋』が読みたくなった。どちらも、「梨木香歩の作品、中島京子の作品ではなにが好き?」と聞いたときに返ってくるといちばんうれしいタイトルだ。
うん、夜ノ森公園の桜の記憶の謎もそうだけれど、読後に浮かんだもので、その作品の良さや深さがはっきりわかるものだな。
by月亭つまみ










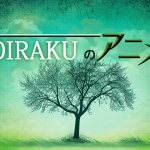





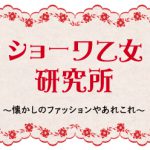




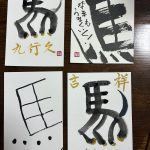


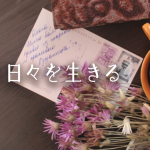

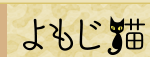

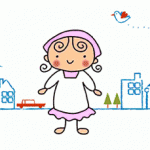

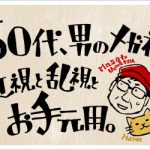









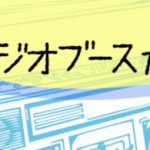








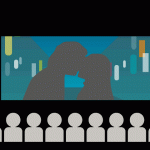
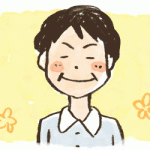



















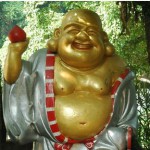




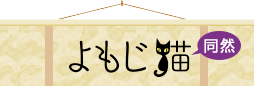




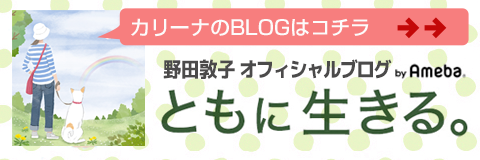
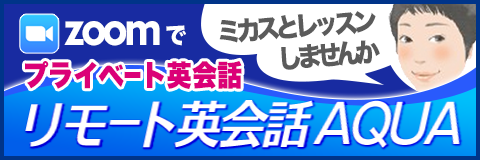
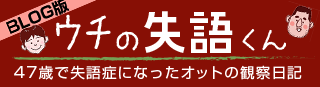
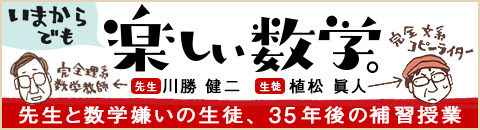

nemu
こんにちは。
素敵な本のご紹介,ありがとうございました。
こちらの作家さんのお名前も,全く知らなかったのです。
図書館に予約して、読んでみたいです。
この記事を読みながら、梨木さんの「家守綺譚」を思い出していました。
それなので後半に梨木さんのお名前が出てきた時はとても嬉しかったです。
「村田エフェンディ・・」は、ラストが悲しすぎて、再読してもラストまで読めなかったりします。
「家守・・」の方にも少し村田さんの話題が出てきたりしますよね。
中島京子さんも大好きです。
でもどれが一番好きかって選ぶのは難しいですね。
一番最近読んだのが「夢見る帝国図書館」です。上野の図書館に、行ってみたくなりました。
つまみ Post author
nemuさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
梨木香歩さんと中島京子さんがお好きなら、ぜひぜひ!
私も『家守綺譚』を再読したくなりました。
『夢見る帝国図書館』もいい小説ですよねえ。
上野の図書館(児童館)で以前、中島さんの講演会を聴いたことがあります。
それを思い出しつつ読みました。
最近の中島さんの『坂の中のまち』もちょっと不思議な小説で楽しかったです。
木内昇さんに話を戻しますと😅「木内昇にハズレなし!」です。
『よこまち余話』あたりからぜひ!
mikity
つまみさん、
「奇のくに風土記」よみました!とてもよかったです。最近の木内昇さんの「惣十郎浮世始末」や「剛心」などもよかったけど、わたしはダントツで「奇のくに風土記」が好きです。やわらかであわあわとした文章が心地よくいつまでも読んでいたいと思う本でした。あちらの世界とこちらの世界を行き来する、そんなとらえどころのなさが、現実一辺倒の厳しい世界から逃避させてくれるような気がします。逃げ場って必要ですよね。
あ、この本とは関係ないのですけど、わたしの最近の一押しは、
メリッサ・ダ・コスタの「空、はてしない青」です。余韻がすごくて今もピレネー山脈を旅している気分です(笑)
つまみ
mikityさん、こんばんは。
木内昇にゾッコンですが、私も最近の中では奇のくに風土記がいっとう好きかもしれません。
今見えているのが世界のすべてではないかも、と思わせてくれる小説が好みですが、この世とあの世の境い目があいまいって、その究極です。
mikityさんのコメント、それそれ!と読みました。
最近、海外モノをあまり読んでいないのでオススメ本、読んでみます!