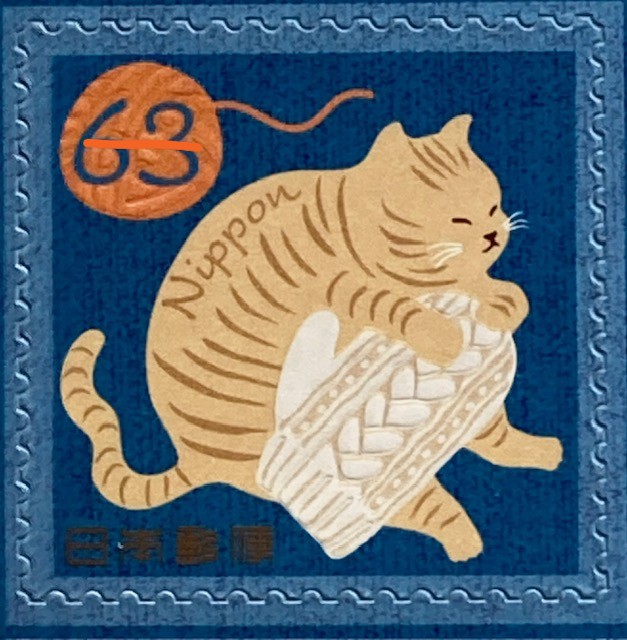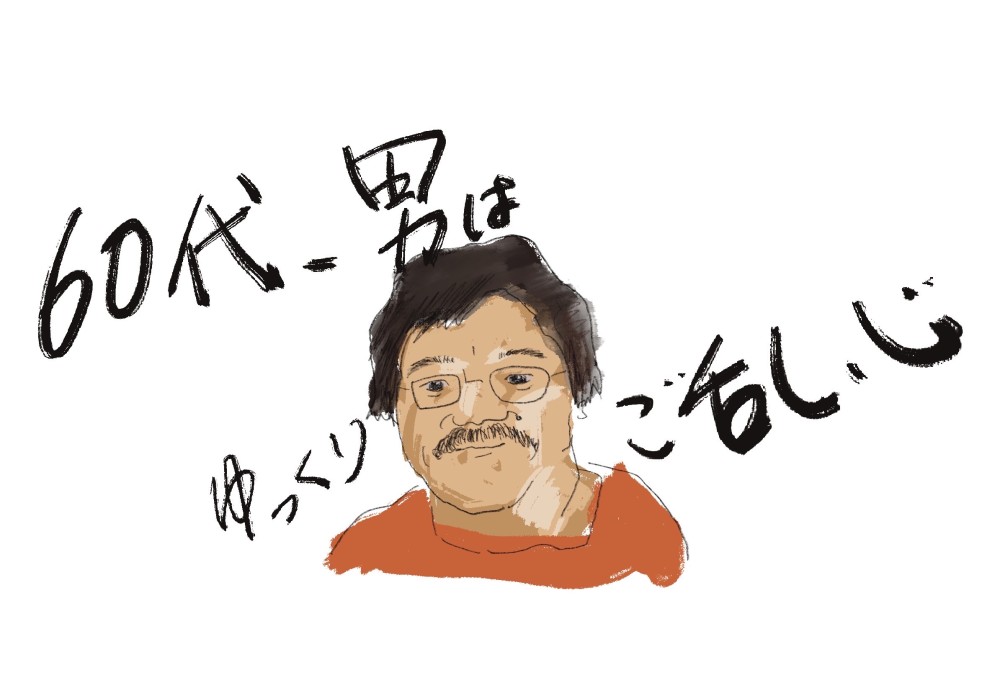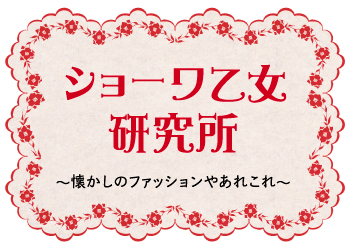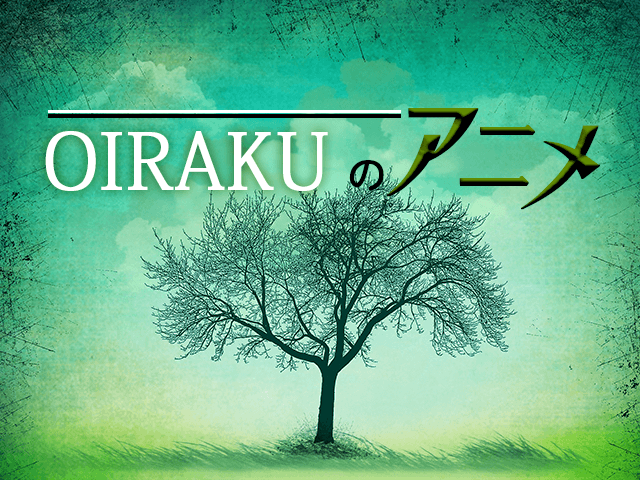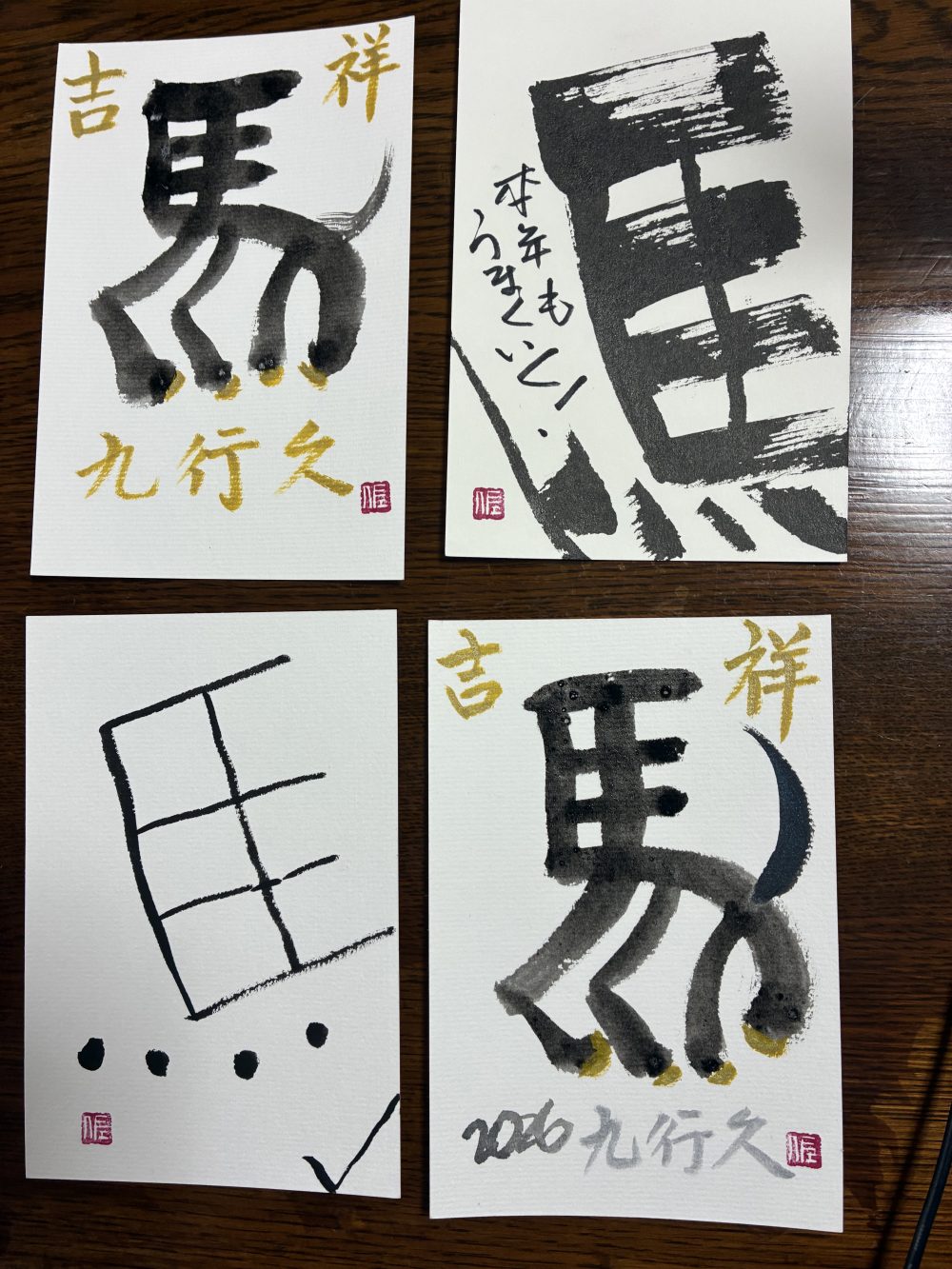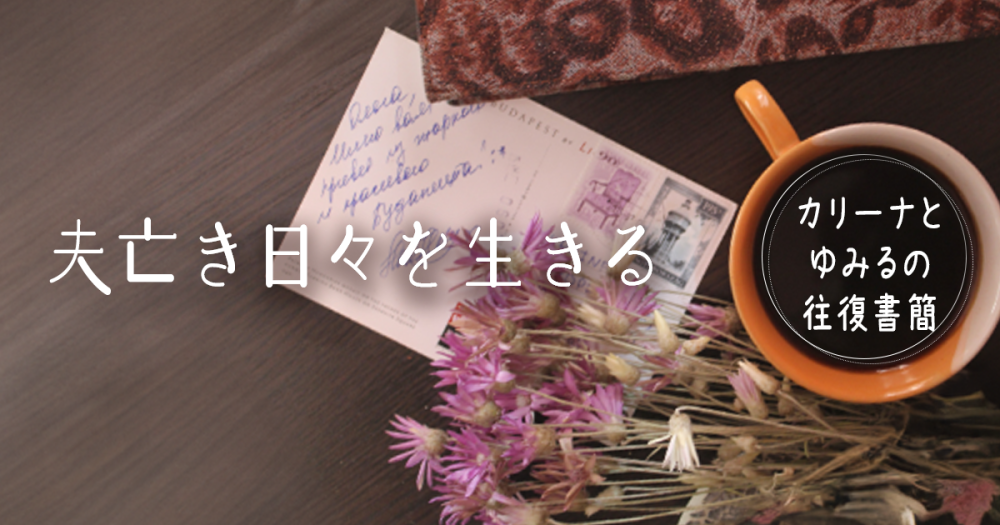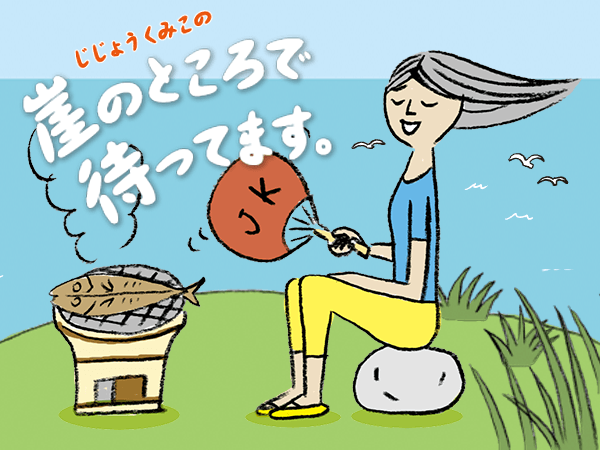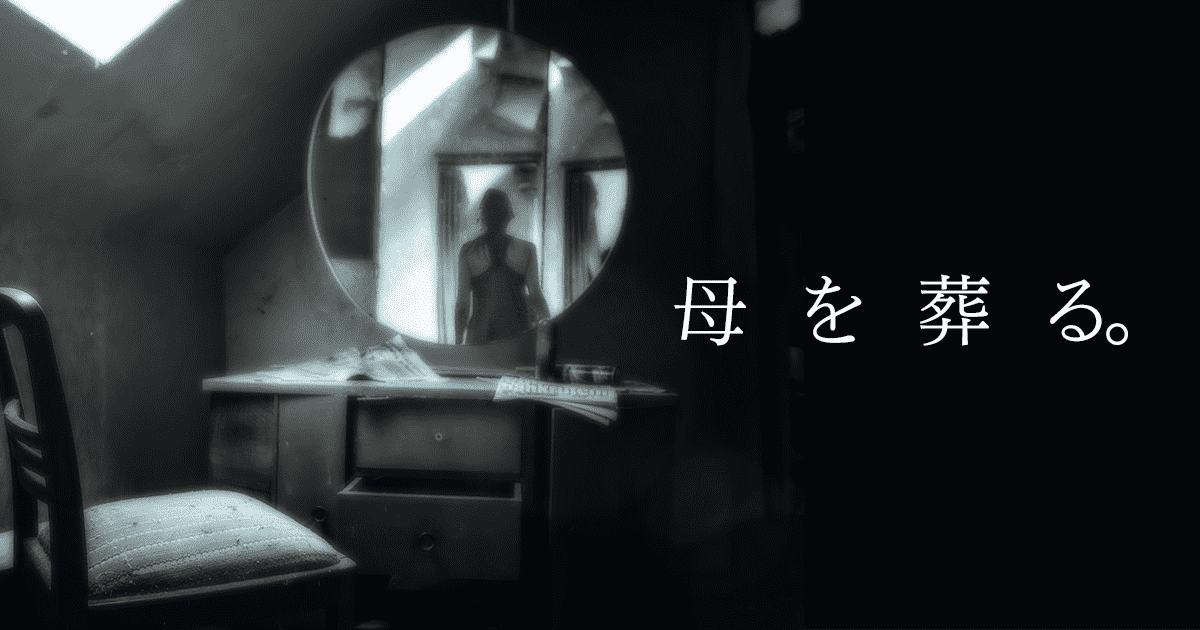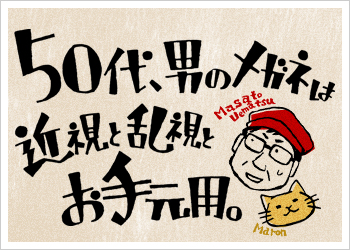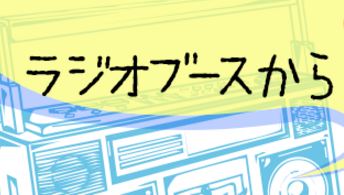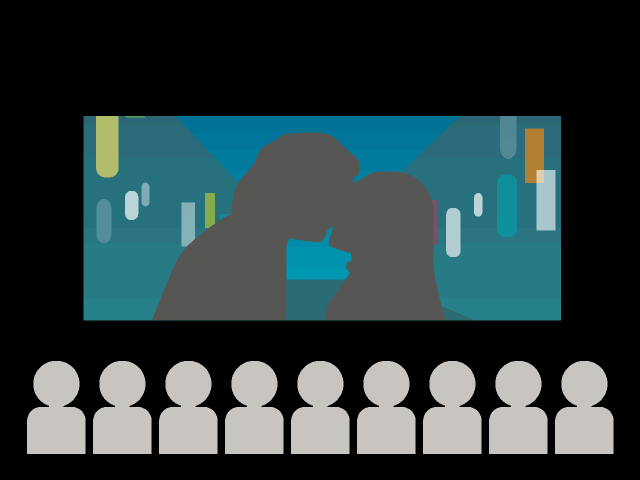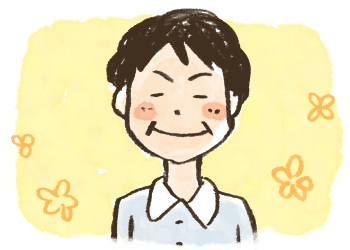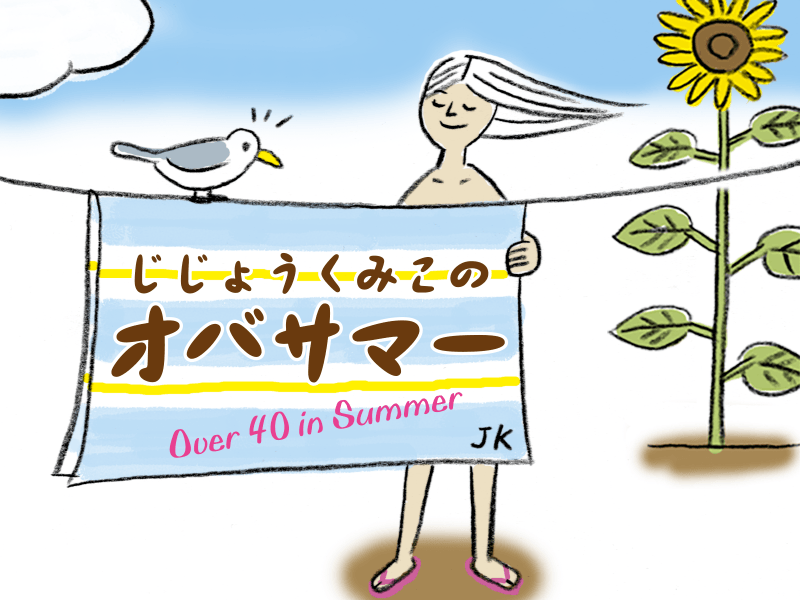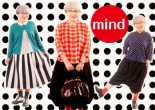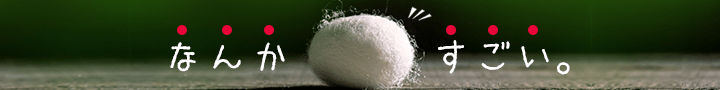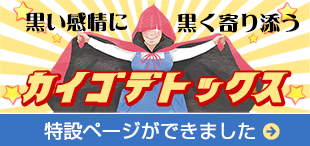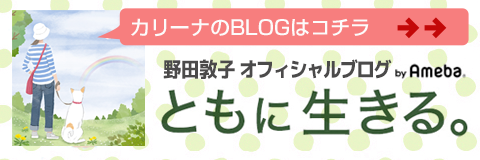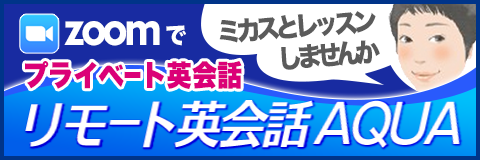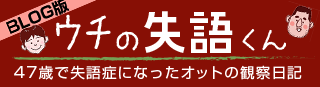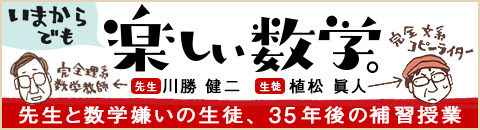秋の空の下

バーミンガムからはじまった国旗掲揚運動は、わたしが住む町にも波及してきて、いま街中のいくつかの地域では、街灯の柱に国旗がくくりつけられてひらひらとはためいている。
だいたいが白地に赤の十字のセント・ジョージ・クロス(イングランド旗)で、ときどきヨークシャーの白バラの旗やユニオンジャック。
この運動を率いている団体というのがあるらしいのだが、ヨークの町のそれが、彼らがやってきて設置したものなのか、彼らに賛同する地元の人たちが設置したものなのか、そこのところはよくわからない。
でも、だれかがわざわざこのために大きな旗を購入して、人の少ない夜か何かにハシゴ登って旗をかかげて、よし!と満足して帰っていったのかあ、と思うと、そのパッションなんなんだ、という気持ちだ。
外国人に遠慮して自国の旗が掲げられないなんておかしい。ここはおれたちの国だ、自分たちの旗を自由に掲げる権利がある。
というのが運動の趣旨らしい。たしかに、地方議会で公共の施設に旗をかかげるのをやめた自治体があって、それも運動の発端になっているとニュースで読んだ。その是非はともかく、
そもそも、イギリスで、人々が国旗を掲げることに遠慮を感じていたなんて、まずそのことに驚いた。
生活用品からおみやげものに至るまで、ユニオンジャックのデザインはいたるところに使われているし、ロンドンのバッキンガム宮殿に行けば、正面の通りの両側は国旗で埋め尽くされていて「大英帝国!」って感じだしで、国旗に、濃淡はあれど複雑な歴史背景を感じる人の多い日本で育ったわたしとしては、イギリスの愛国心はずいぶんあけっぴろげで大らかだなあ、くらいに思っていた。


もちろん、かつての帝国主義や、極右団体国民戦線のイメージなど、ユニオンジャックの含む象徴性に抵抗感をもつ人もいることは知っているけれど、それでも英国旗は、一般的にはイギリスのポジティブなイメージを助けるコマーシャルなアイテムとして国内外に受け入れられていると思っていたのだ。
「自分たちの国旗に誇りを持てない情けない状況」なんてほんとうにあるのかなあ?
とここまで書いてみて、そういえばわたし、イギリスっていっても、今住んでるところ含めて観光地しか知らないんだなあと気がついた。観光とは無縁の町に住んでいたら、また見える景色はぜんぜん違うのかもしれない。
こうした運動を率いる人たちが掲げたい旗のいちばんは、セント・ジョージ・クロス(イングランド旗)なんだろうなあと思う。英国のイングランド内ではじまった運動だからっていうのはもちろんだけれど、やっぱりスポーツの試合やなんかで「おれたちの旗!」っていう帰属意識が強いのがこの白に赤い十字の旗なのかなあ。この旗が、フーリガンや極右グループの旗印だったことを肌で覚えている人はどのくらいいるんだろう。近年は、そういうマイナスイメージはずいぶん払拭されてきているとどこかで読んだけれど。なんとなく、ユニオンジャックやヨークシャー旗は、めくらましのために取り付けてあるような気がしなくもない。
連合王国であるイギリスには、スコットランド、ウェールズにもそれぞれ旗があるんだけれど、それらが翻っていても「地元愛が強いなあ」っていうくらいにしか思わないのに、イングランド旗のセント・ジョージ・クロスにたいしては「んん?」とアラームが鳴る。わたしにとっては、ヨークシャー旗が前者2つと同じような感覚だ。その捉え方も人によってずいぶん違うんだろう。

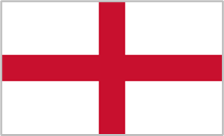


自分ちの敷地内に旗をかかげるのはあくまで個人の自由だし、公共施設での国旗掲揚や、お祭りや祝日なんかに街中に旗がひらめいていてもべつにいいと思うけれど(個人的にはあんまり好きではないけれど)、こうやって公共の道路やなんかに「イギリス人がイギリスの地にイギリスの旗をかかげて何が悪い!」とやられてしまうと、それはやっぱり「文句があるやつは愛国心がない」「いやなら出て行け」というメッセージとして人々に伝わってしまう。
そもそも「イギリスの土地」=「イギリス人の自分が自由にしていい土地」っていうアイデアの飛躍がよくわからない。
プロテスト、という観点からすると、ゲリラ的に街中にメッセージを設置するのはよくある手法、っていうか、プロテストにモラルだのお行儀だのを過剰に求める風潮にはわたしは賛同しないので、そこに物申すつもりはあんまりない。社会からやや逸脱する、騒ぎを起こして訴えるからこそプロテストなんだと思っている(暴力は論外)
ただ、この国旗掲揚行為がちょっとプロテストと違うなあ、と思うのは、彼らの多くはたぶん、「自分たちにはそれを自由にする権利がある、当然のことをしているだけだ」と思っている、というか、そうした主張に煽られている。
ひとりでは非力な者たちが、多少のリスクを冒してでも起こすのがプロテストだとしたら、そういう意味で、彼らは自分たちが非力ではないことを知っている。自分たちは(本来)強者だぞ、お前らに大きな顔はさせないぞ、ということを言っているんだと思う。
旗は、「われわれ」と「あいつら」を分ける陣取り合戦の象徴として機能している。なんていうか、国旗本来のおしごとをさせられているというか。
しかし、公共物に許可なく設置された旗は、どうしたっていつかは撤去対象になってしまう。でもそうすれば、それはまた人々の怒りを煽る結果となり、撤去した自治体は「非愛国的」というレッテルを貼られる。設置する団体側は、そうやって分断や怒りがひろがっていくことをわかってやっていると思う。なので、自治体側も不用意に撤去できない。その結果、旗ははためき続け、人々に支持されている証として機能し始める。
イギリスで、イギリスの国旗を掲げよう運動って、じつはすごく頭がいいのでは。だって一見反対しにくいもんなあ。
イギリスに引っ越してきて2年半、これまで、外国人だからということで嫌な思いをしたことは幸いなことにあまりない(まったくないとは言わないが)。
働いている大学でも、ボランティアをしている公共図書館でも、みんな、配慮はするけれども平等に接してくれるし、できることに価値をおいてくれて、これだから外国人は、というような扱いをうけることもない(そういうのは過去に一度だけ)。きっとイライラすることもあるだろうに、本当にありがたいことだ。
その態度は、外国人だからということだけじゃなく、たとえば障害がある人にたいしてもそうで、みんなが、「みんな誰しもできないことがある」という前提の上で生きているようなのだ。そして「差別はダメです」ということを組織として目に見えるように掲げている。それは、ほんとにすごいことだと思う。
でも、こうやって街中に旗がひらめく様子を見たり、FaceBookにランダムに上がってくる記事につくコメントが、国旗掲揚賛美に埋め尽くされているのを見たりすると、いまこうしてすれ違っているたくさんの人たちのなかで、どのくらいの人がこれに賛成しているのかなあ、とつい思い始めてしまう自分がいる。
もちろん、この運動にいいね!と思うことと、差別に加担することはイコールではない。そんな乱暴なことをいう気はないけれど、鈍感だなあとは思う。そして、これが、人々の意識をうっすらと、でも確実に変えていくかもしれないなあというふうに感じている。
たとえば、わたしがへんなところに立っていて、道をブロックしていたとして、それに「チッ」って思う人が、「こいつめ」じゃなくて「この外国人め」って思い始めるんじゃないか、とか、
わたしが仕事で答えられないことがあったとして、それについて「こいつ使えない」じゃなく、「なんでこんな外国人が職を得ているのか、うちの娘は職探しに苦労してるのに」とかいうふうになっていくんじゃないか、とか、そういうことだ。
なんとなく、うっすらと不満に思っていたことに対象が与えられて、口に出していい、態度に表していいことになっていく。わたし個人の失敗やいたらなさが、「外国人だから」ということにされてしまう。
ひとりひとりだったら、日本人のMさん、ネパール人のSさんなのが、5人集まったら「あやしげな移民」になっちゃう、自分が座ろうと思っていた席に、外国人(に見える人)が座っていて楽しそうにしていたら「いまいましい移民」になっちゃう、わたしたちの意識って、そのくらいぐらぐらしたあやういものなのだ。
先日ロンドンで行われた、政府の移民政策に反対するデモには、ものすごい数の参加者が集まった。「このストリートはわれわれのものだ」と叫んでいる者もいたらしい。
このさき、どうなっていくんだろうか。
でもひとつ、わたしがこちらに引っ越してからこっち感じていることは、この国の多くの人は、目の前に誰かが立っているときに、その人を面前で蔑んだり、残酷になったり、困っているのを放置したりすることにはたぶんあんまり向いていない。いまいましいと思っても、体が動いて助けてしまう気がする。いや、国とか関係ない、にんげんみんなだいたいそうか。
これもまたひとつの「イギリス人」に対する先入観、希望的憶測と言われたら、そうかも。
先入観や推測は、にんげんが生きていくために大切なスキルでもある。
だからこそ、個でつながり続けることがいますごく大事だ。経験をくりかえして、みんな違うんだなあ、でもだいじょうぶだったなあっていうことを体にたたきこむこと。
まだ起こっていないことにたいして、おたがい不安や先入観で警戒しはじめたら、ほんとうに誰かの思う壺なんだから。
この関連のニュースでわたしが気に入ったのは、道にペイントされたセント・ジョージ・フラッグに、だれかがピンクと黄色のペイントを足して、バッテンバーグケーキにしたったやつ。そういうところ好きだぞ。
(GoogleでSt George flag Battenberg cakeで検索すると出てきます)


Byはらぷ