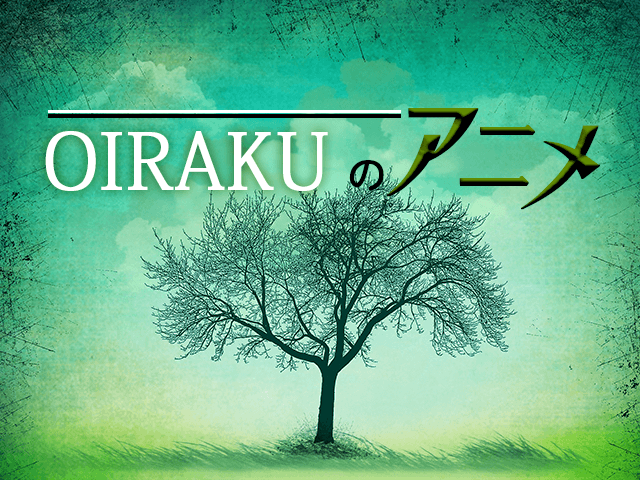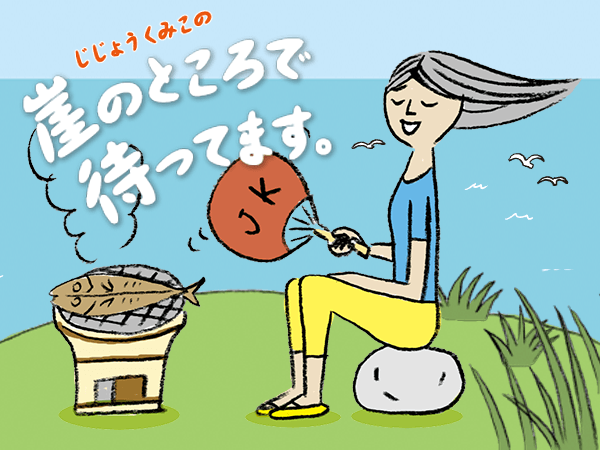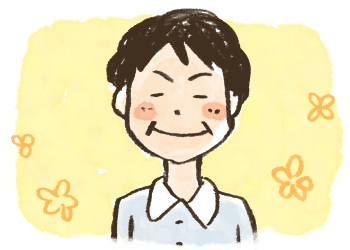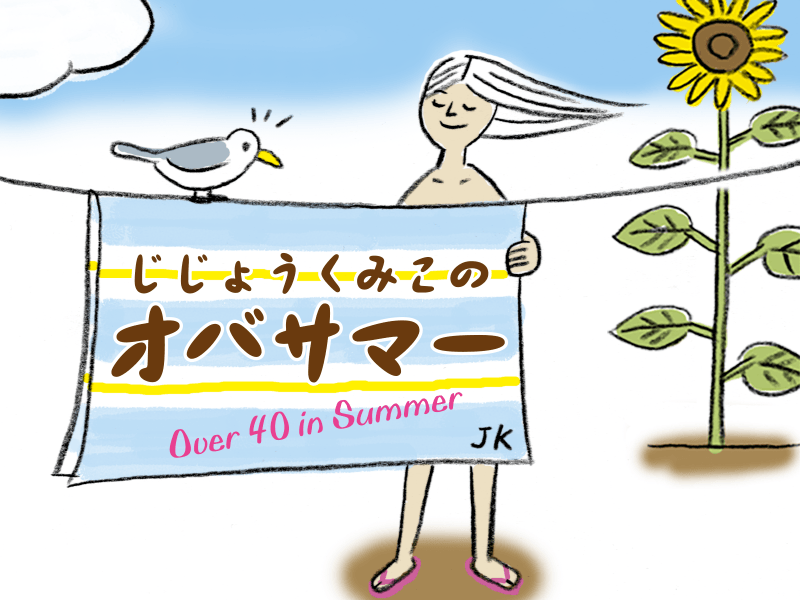【月刊★切実本屋】VOL.62 取り返しのつかないものを自分なりに取り返すために
もう会えないんだと気づいて初めて、「わたし、けっこう彼(彼女)が好きだったみたい」とわかる人がいる。
それはリアルな知り合いに限らず、実際には一度も会ったことのない著名人だったりもし、そっちの方が多かったりもするが、著名人の場合、「もう会えない」というのは、ほぼ死を意味し、たいてい突然なので、驚きと寄る辺なさに狼狽えてしまう。
同じ思いの人と悲しみを分かち合うこともできないではないけれど、分かち合っても、喪失感や後悔が半分になるわけじゃあない。むしろ、もやもやが増えたりする(なんでだろう)。基本的には、ただただその気持ちとひとり向き合うしかないと思い知るのだ。
でも面識がなかった分、最初の寂しさはわりと早く癒える。いや、正確には「癒えた」わけではないが、日常の喧しさがいったん寂しさを凌駕する感じ。気持ちはバリバリ残っているけれど一度、落ち着こう、みたいな。そして、喪失感に引っ張られ過ぎなかったことに正直、安堵する反面、その程度の気持ちだったか、まあ、わたしはそうなんだろうね、と情けなさにも似た罪悪感を覚えるのが常だ。

清志郎やヒデキがそうだった。もっと無意識下では、千代の富士やさくらももこ、深浦加奈子、竹内結子にもそれを感じた。そういう罪悪感は、その人の軌跡を振り返ることで解消するしかわたしには思いつかない。ありがたいことに、このご時世、パソコンを開けば、過去の彼ら(&作品)をずっと見ていられる。
今は、これからも忘れないと、今は(二度言った!)思っている、と意識することでしか、好きだった気持ちを昇華させるすべはないと、時に涙しながら、しばらくパソコンや本を開き続けることになるのだ。

小説家の津原泰水さんもそういう存在だ。千代の富士や深浦加奈子よりもっと無意識だったので、訃報を聞いてからこっち、そんなに好きだったっけ?と驚いている。
作品をすべて網羅しているということは全然なくて、読んでいるのは三作。三作のうちのひとつ『ヒッキーヒッキーシェイク』にまつわる騒動のときは、妙に義憤にも駆られ、くだんの文庫本(もちろん早川書房)を購入して読んだが、その時点でけっこう久しぶりだった津原作品は、相変わらず読者を選ぶ世界で、それをとてもおもしろく読めた自分は、まるで津原さんのシンパでずっといたような、選ばれたままだったような、間違った誇らしささえ感じた。なのに、その後、彼にのめり込むことはなく、先日の訃報を聞くことになったのだ。
そして久しぶりに『ブラバン』を読んだ。この小説は、発売後、わりとすぐに読んだのだが、その後、ハマったのは夫だった。自身も楽器を演奏する夫は、この小説を繰り返し繰り返し読んで、今では、テキトーに開いたページからでも即座に没頭できる域に達したと表明している。時にお風呂にも持ち込むため、本(単行本)の劣化は激しい。

わたしは今回、十五年ぶりぐらいに読んだのだが、やっぱり唯一無二の小説だと思った。そして、やっぱり読者を選ぶ小説だとも。
どこがおもしろいのかわからない、とにかく読みづらい、というレビューにも、わたしの一部は「確かに、構成が混沌としているところがあるし、とにもかくにも明るさに欠けるし…」と理解を示しつつ(ナニサマ?どこ目線?)、でも、残りのわたしは強く否定する。こんなにおもしろい小説があるか!と。
1980年代初頭に広島の高校生だった<僕>は、軽音楽同好会との掛け持ちをしている吹奏楽部員だった。四半世紀が過ぎ、中年になった<僕>は、流行らないバーを経営しているが、吹奏楽部で一年先輩だった女性が結婚することになり、本人の要望により、吹奏楽部を再結成しようという話になる。それが軸になった物語で、時制は、1980年当時と、二十五年後を行き来する。
中年の<僕>が、当時を回想し、ビリー・ジョエルの「オネスティ」の詞の辛辣さを語る場面、高校時代、父親に本物のエレキベースを買ってもらうくだり、四半世紀ぶりに会った先輩に<僕>が「自分はなぜか意地が悪いと言われる」と言ったときの先輩からの返し、閉塞感いっぱいのもろもろを経てのラスト…この小説をおもしろい、沁みる、と思えない人がいるなんて、と残念に思う段階は軽く通り越し、おもしろいと思えない人にもどうか幸あれ、ぐらいなことを思った。自分で書いていてヘンだけど。

今回の記事、津原さんが存命中に書かなかったことを若干悔やみはしつつも、贖罪ではなく、これから、新しい読者が生まれることの、一助になることを願ってやまない。同時に、著者と呼ばれる人は、自分がいなくなっても、地球が滅亡しない限り、その分身は在り続けるという事実を思い、空を見上げ続け過ぎてめまいを覚えたみたいな感覚になっている。脳内は広いな大きいな(意味不明)。
by月亭つまみ