【月刊★切実本屋】VOL.95 食文学ブームについて
昭和の食文学ブーム、それはエッセイ方面に突出していた!‥のではないだろうか。
武田百合子や沢村貞子や高峰秀子や向田邦子が書くものは、エッセイというより随筆といった方がしっくりして、気どりのなさも含めてなんともまあ粋だった。今も、彼女たちに憧れを抱く人は多い。

一方で、桐島洋子や森瑤子、安井かずみも外せない。当時「翔んでる女」というダサい称号を付与された彼女たちの食に関するエッセイも話題になった。こちらは、ライフスタイルの新しさ、かっこよさが前面に出ていて、なんならそのときの当人の恋愛事情も開示されていたから、ド庶民のド田舎のド小娘には正直ピンとこなかった。でもとにかくこれが時代の最先端なのだとは思った(ホントか)。お三方とも1940年前後の生まれだが、森さんと安井さんは21世紀を待たずに50代で鬼籍に入ってしまった。
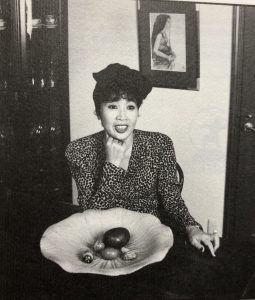
それに対して(別に対抗・対立の「対」ではない)昭和の食エッセイの男性部門といえばなんといっても東海林さだおと椎名誠だろう。こちらは、粋やハイソとは一線も二線も画す庶民目線とユーモラスな語り口が魅力だった。登場する食べものはこぞって旨そうで、読めば必ずお腹が空いた。隠し味のような知性も効果的だったと思う。こちらのおふたりは現在80代でご存命だ。これからもまだまだ生きて食べて、なんならふざけてほしい。

平成以降の食文学には小説の躍進を感じる。現在、再読中の髙田郁の「みをつくし料理帖」シリーズは2009~2014年の作品だが、自分の没入っぷりは二度目とは思えず、このところ少々睡眠不足気味だ。
舞台は江戸時代後期。ヒロイン澪は大阪の出で、幼くして水害で家族を亡くしたが、料理に天性の才能を持ち、尚且つ努力も厭わない人物だ。奉公先の老舗料理屋の店主に見込まれ修行を続けていたが、店が火事で焼失し、店主とその女房(ご寮さん)と一緒に、ふたりの息子である若旦那が店をかまえている江戸にやって来る。でも若旦那の店はなく、彼自身も行方知れずと知る。店の再興を願いながら傷心のまま世を去る店主。澪はご寮さんとともに蕎麦屋「つる家」に職を見つけ、食文化の違いにとまどいながらも料理の才を発揮し、若旦那と、水害で離ればなれになったおさななじみの身を案じながら生きて行く。
澪の暮らしは苦難の連続だ。大手のライバルには妨害され、つる家は一度焼け、恋も容易には進まない。想い人を案じるあまりに指をケガし動きがままならなくなったかと思えば、心身のストレスが高じてニオイや味を感じなくなる。まさに茨の道続きで、そこいらの安直なジェットコースター小説など根こそぎなぎ倒すハラハラドキドキの展開だ。でもそれを補ってあまりあるほどの食の輝きとその癒しがある。

出てくる料理、それを編み出す過程がどれも素晴らしい。江戸の世という食材のシバリが逆に強みになっている。今では地味にさえ映る海のもの、野菜、たまご、豆、乾物‥すべての調理に工夫とリアリティがあって、どれもとんでもなく旨そうなのだ。読んでいると、労を厭わず食に向かいたいと、こんな自分ですら思う。なかなか難しいけれど。せめて、巻末のレシピの斜め読みはやめろ、自分。
澪は、名店の店主から、料理人として後世に名を残す人材として育てたいと打診を受けたときにこう返す。
「口から摂るものだけが、ひとの身体を作ります。つまり、料理はひとの命を支える最も大切なものです。だからこそ、贅を尽くした特別なものではなく、食べるひとの心と身体を日々健やかに保ち得る料理を、私は作り続けていきたい。医師が患者に、母が子に、健やかであれと願う、そうした心を持って料理に向かいたいのです」
(中略)
「残すならば、名前ではなく料理でありたい。私の考えた料理に、のちにまた別の料理人たちの手が加えられてずっと残っていくとしたら、多くのひとの命を支える糧になれるとしたら、それこそ本望です」
勝手に断言するが、「みをつくし料理帖」全10巻は平成以降の食文学の金字塔だと思う。
そして、「みをつくし料理帖」以外でも、平成以降、食がモチーフになっている小説は多く、シリーズものが目立つ。ここ数年読んだものだけでも、柚木麻子の「アッコちゃん」シリーズ、近藤史恵の「ビストロ・パ・マル」シリーズ、成田璃子の「東京すみっこごはん」シリーズ‥要するに、好評だからシリーズ化した、ということだろう。シリーズではないが、原田ひ香の『まずはこれ食べて』や、寺地はるなの『カレーの時間』もよかった。あ、宮部みゆき御大のすべての時代小説も外せない。
そして先週読んだ山本幸久の『社員食堂に三つ星を』もさすがだった。山本幸久ファンを長くやっているので、彼の作品につまらないものはないことは「知っている」が、今回も「通俗小説の極み!」だと思った。
最近の食をモチーフにした一部の小説たちは、ありもしない高みを目指しているものが少なくない気がする。食育という言葉が日常的に使われ、食は身体だけでなく心も育む‥という考え方に異論を唱える人が少ないことを印籠のようにし、食に万能感や崇高さを与えて物語を動かしている、みたいな。小賢しい!
その点、山本作品は2023年の『おでんオデッセイ』も今回も、もっと日常で押しつけがましくない。アツい感動よりあたたかな余韻が残る。これを通俗小説の極みと定義させていただきたい。勝手にしろ、か。
by月亭つまみ







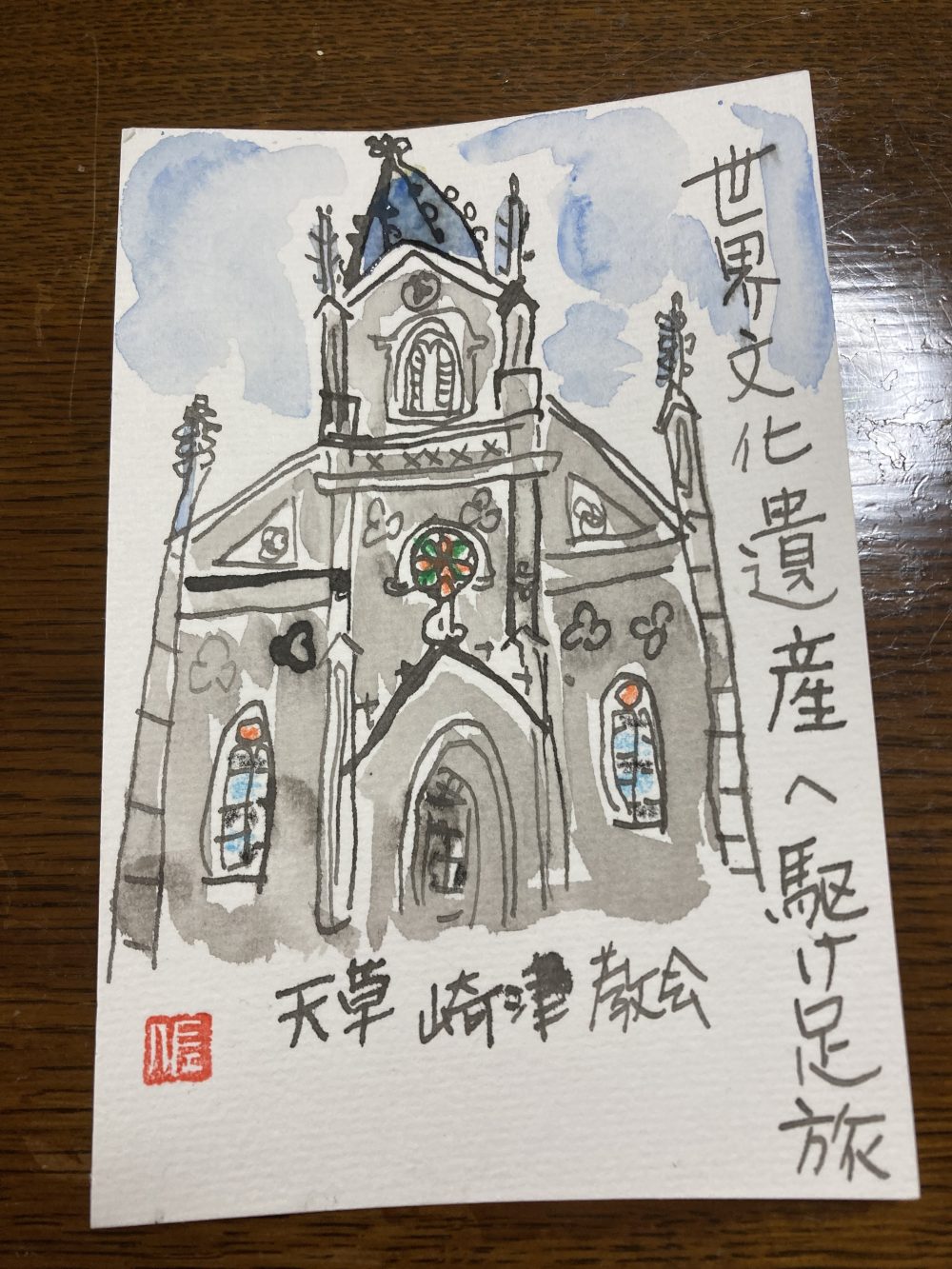
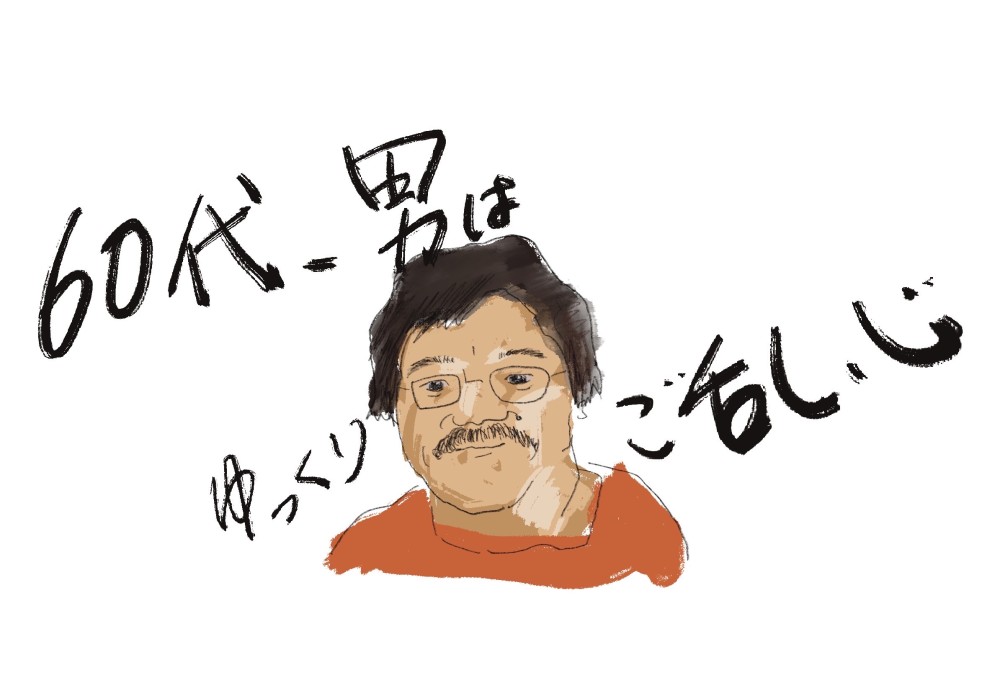

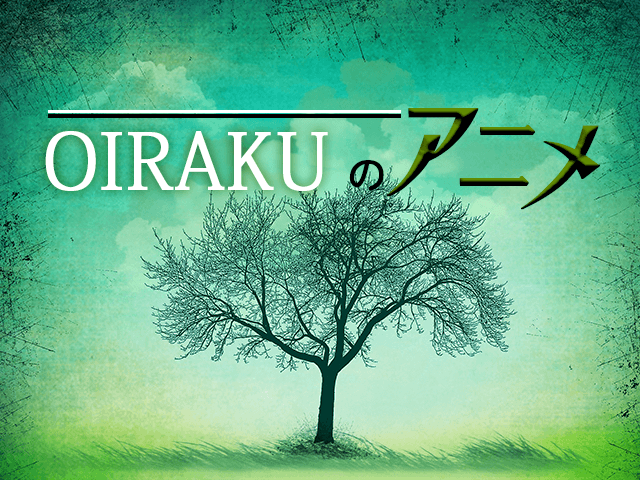


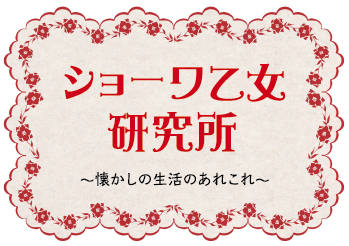

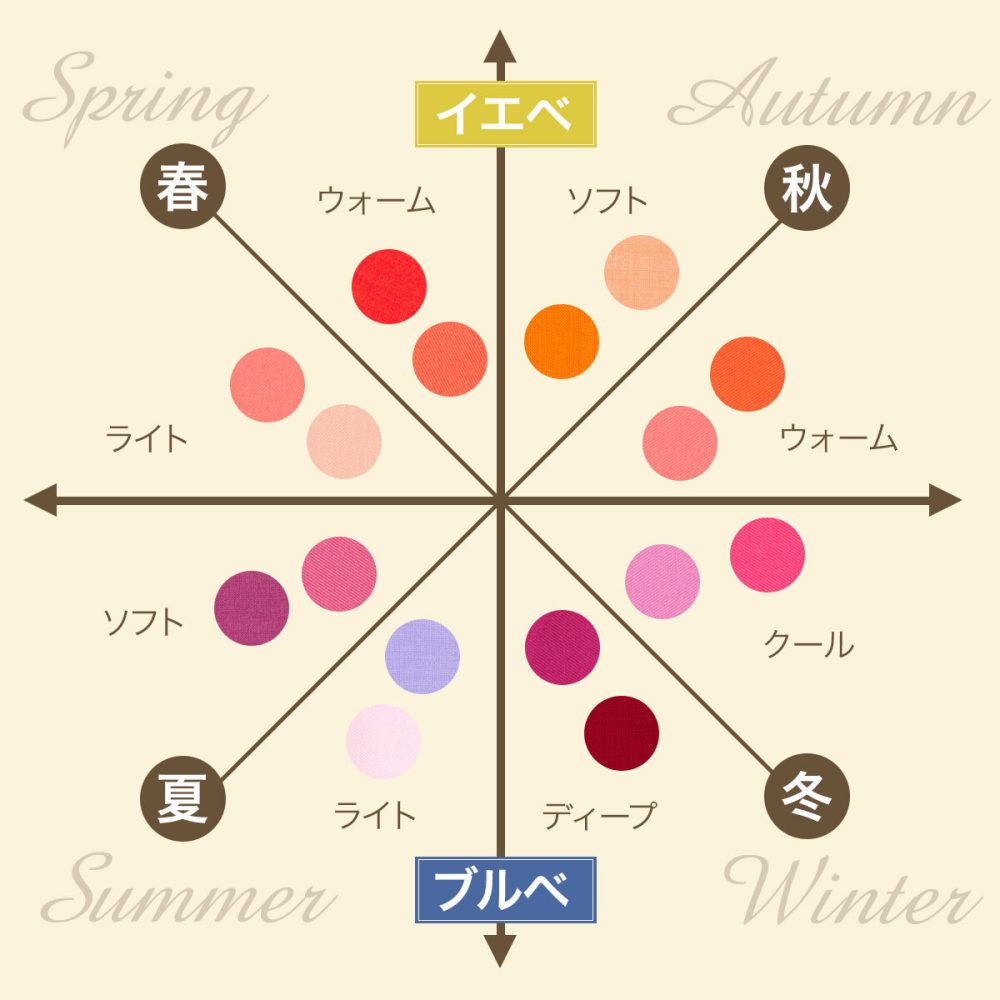
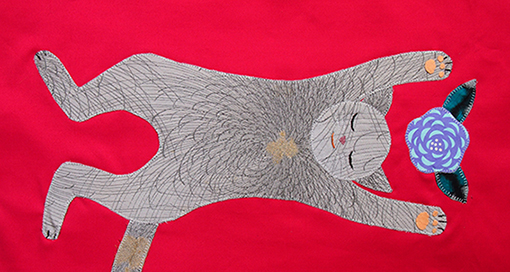






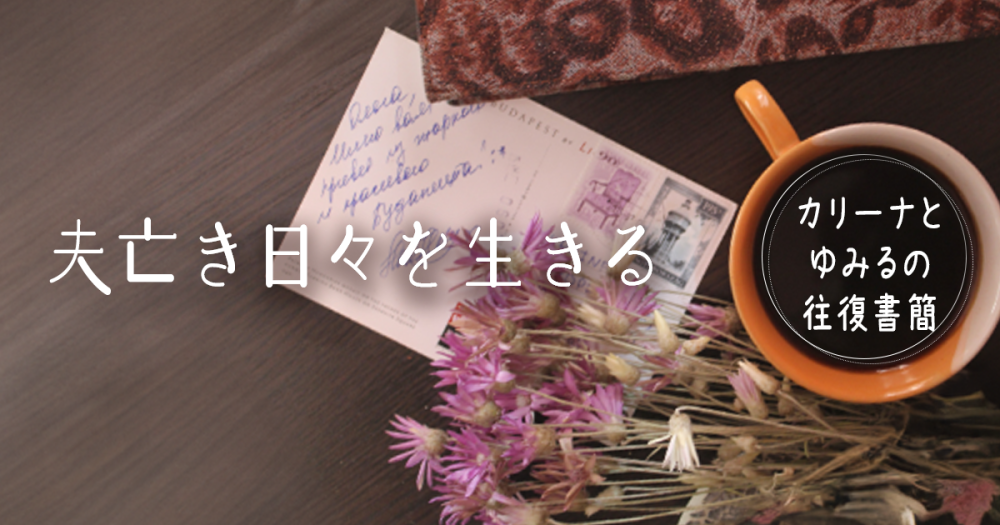
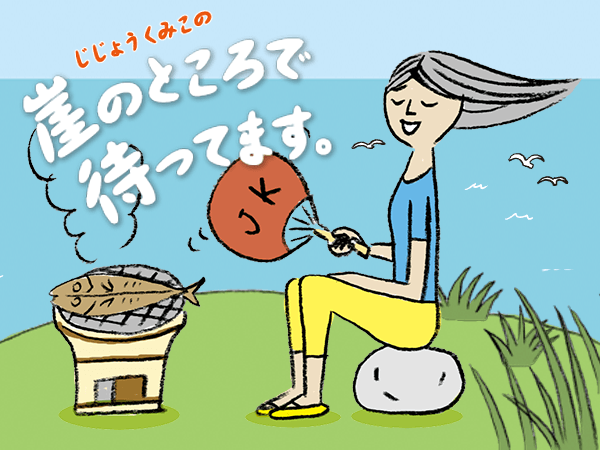

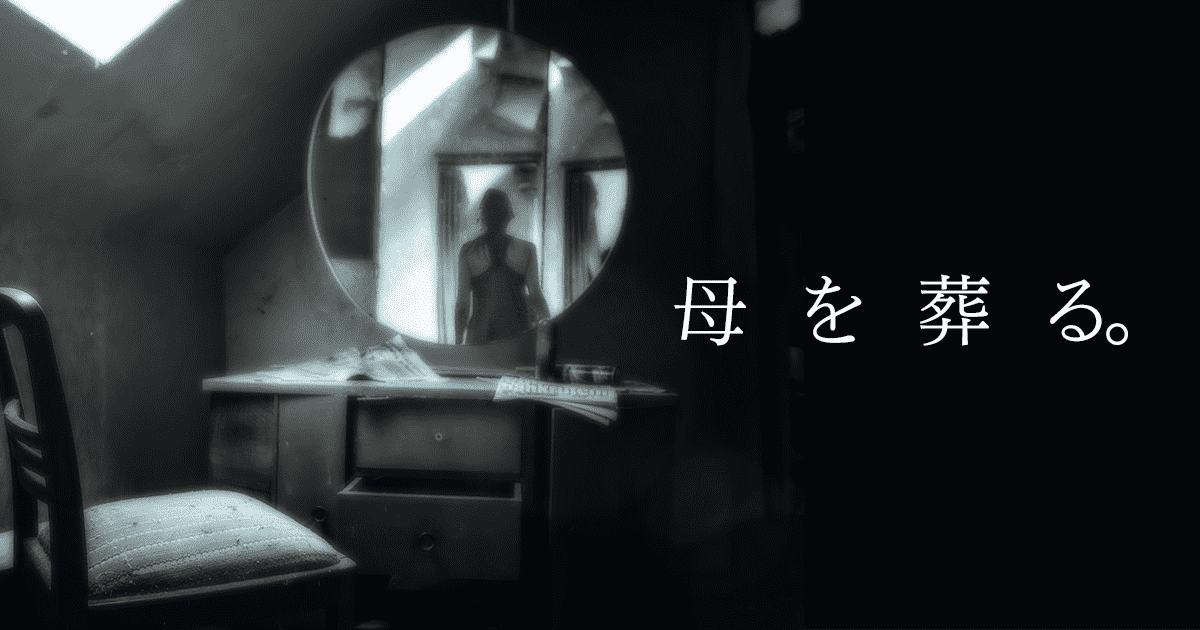


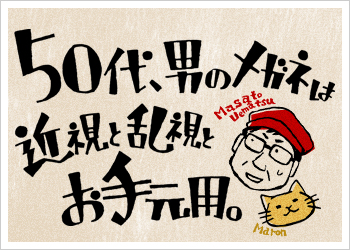









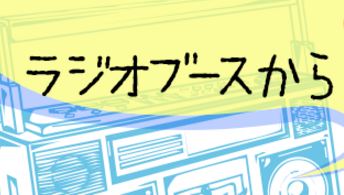








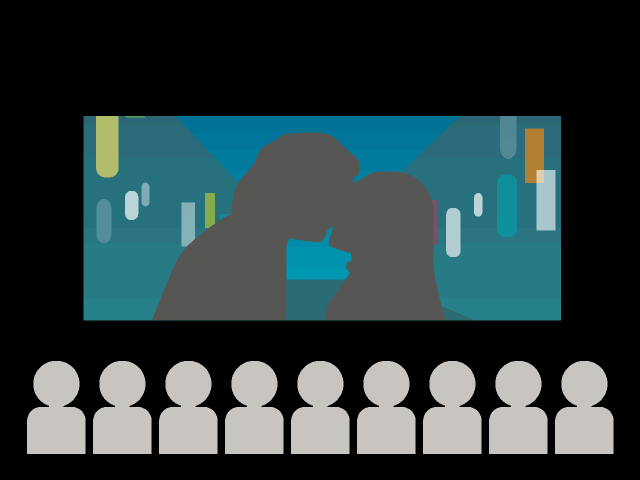
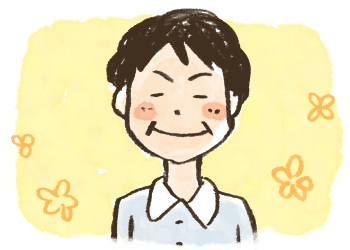
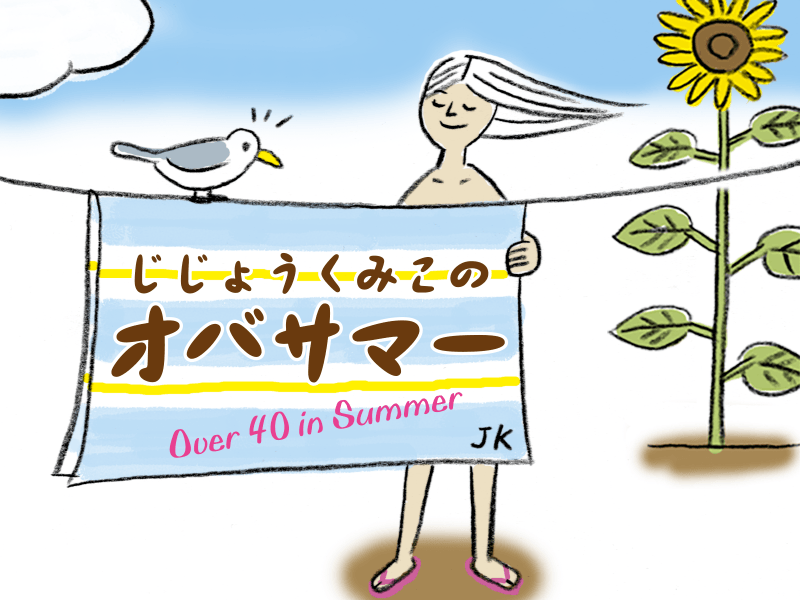





















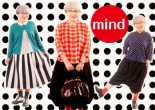





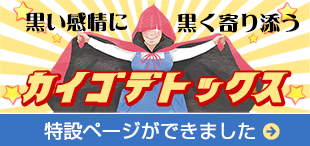


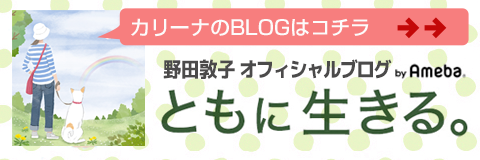
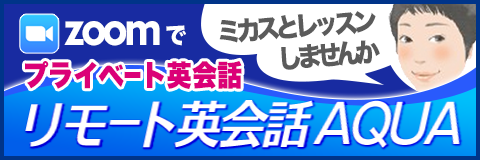
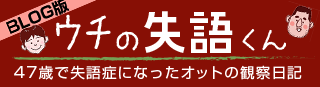
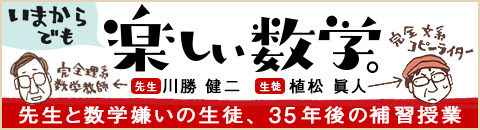

アメちゃん
つまみさん、こんにちは。
東海林さだおのエッセイ、愛読書です!
私の(蔵書の少ない)本棚で幅を利かせてます😆
東海林さんの文章は、ふざけていても下品じゃないのがいいですよね。
かっぱえびせんを何本口にくわえられるか実践してみたり
フルーツゼリーをそのまま上から落として一口で食べるとか
それはやっちゃあ、まずいんじゃないか…??
と心配してしまうおふざけも、あるのはあるんですけどねー。
ふと思いついたことを、「こんなのバカバカしい」と思わず
すぐ西友に走って行って材料を買ってくるあたり
いつまでもふざけていて欲しいと、私も切に思います。
そして、ぜひ長生きして欲しい…😄
つまみ Post author
アメちゃんさん、こんばんは。
東海林さだおを愛読するアメちゃんさん、いいですねー。
私は大昔に読んだきりなので、記憶が定かではありませんが、いい大人がバカバカしいことをふつうにやっている感じは、大人だってふざけていいんだと、守備範囲が広いことを教えてくれるみたいで心強かったです。
また読みたくなりました。