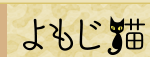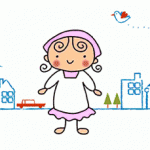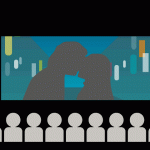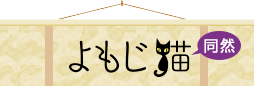Posted on 2024年7月22日 by プリ子
(13)負の循環
母が転院して2か月。病院のケースワーカーから電話がかかってきた。「ご夫婦二人で入れるところを探すことを考えてもらえませんか」と。え、えええ? 今更? そんなに元気なの? 嫌悪!
とにかくさみしがっていて、看護師さんたちが困っているとのこと。「医療が手厚い老人ホーム、しかもお二人同室となると高額ですが、ぜひご検討ください」と言われるが、そんな面倒なことは嫌だし、母の願いを叶えようなんて気はさらさらないので、「財産状況を把握していないので」と断った。
それに、私にはわかっていた。母は元気なようでいて、じつは全く元気ではないのだ。いつもの思い込みで「自分は元気である」「自分は優秀である」と振る舞っているだけ。完全な空元気。
もちろん、母の希望を叶える気など一切無いが、もしあったとして、ここで何かしてもすぐに無駄になる。私にはその確信があった。幼いころからその思い込みに振り回されてきたのだから。そもそも、救急搬送された病院の診断でも、転院時の医師の診立てでも、そう長くはない。看護師さんと医師との間ですり合わせはされていないのだろう。
案の定、一週間後に医師から電話がかかってきた。あと一か月ぐらいだという。ほうらね! 母の行動パターンを熟知している自分に苦笑する。
「コロナで通常は面会できませんが、もう長くないので、ご家族は面会できます」と言われたので、父の面会を手配する。もちろん私は行かない。
数日後に面会した父からの報告では、すでに意識はなかったそうだ。「さみしい」「かまって」を連発していた空元気は、あっという間に持たなくなったようだ。
そんなとき、私は職場で異動が決まった。今まで所属していた部署は、自分の好きなこと、比較的得意なことができていたので、できれば長く続けたかった。しかし希望は却下され、特に希望していたわけでもなく得意でもない部署に異動することになった。
目の前が真っ暗になる。自分は希望もきいてもらえないような、ダメな人間なんだ。今までしてきたことはまったく評価されていないんだ。異動先の仕事はまったく得意ではないから、ますますダメな人間になってしまう。今までだって別に「優秀」だったわけではないが、なんとかギリギリやってきた。今度は完全に落ちこぼれてしまう。どうしよう。おしまいだ。
……明らかに母の刷り込みだ。クビになるわけではない。クビだとしても死ぬほどのことじゃない。なのに、死ななければいけないぐらいの暗澹たる気持ちになってしまう。
よく考えたら、私は母の願望を少しだけ叶えてしまっていたのかもしれない。東大ではないし、理系でもないし、研究者でもないし、出世コースでもないけど、図書館はちょっとだけアカデミックだ。母としては、あれだけ嫌悪していたダンキンドーナツのレジでも専門学校卒でもないから(なんと差別的)、ギリギリ及第点だったのかもしれない。配偶者選びをのぞいては。
だから、大学時代や就職してすぐは、それほど母と険悪ではなかった。幼いときから「この人おかしい」「いろいろ押し付けられて嫌だ」と思っていたのだから、もっとはやくに絶縁してもよかったのに、夫が鬱で休職するまでは、なんとなく親子をやってきた。
母の願いをかなえて、母に認めてもらいたい、親に愛されたいという浅ましい気持ちがあったということなのだ。
おえええーーー
よくよく思い出すと、小学生のとき、母が「図書館司書という仕事があって、アメリカだと専門職なのだ」とか言っていたような気がする。
今の勤務先はたまたま受けて受かっただけなのだけれども、でもその選択肢を思いつくというところが、刷り込みの恐ろしさだ。小中高とずっと図書委員だったのも、母のその一言のせいだったのだろうか…!? ぞっ。
変えられない遺伝子のように、母の痕跡が私のいたるところにある。母を軽蔑し、20年間拒絶しても、無意識の奥深くまで沁み込んでしまっている。
「ステータスがなければいけない」「人より優位に立たなければいけない」「優秀でなければいけない」「他人に賞賛されなければいけない」「そうでなければ生きている資格がない」。
母のそうした考え方をあれだけ忌み嫌っているのに、私が、ほからなぬ私自身を、そのように決めつけ、責めている。「今のままでは許されない」「恥だ」と。
私が母を嫌悪するということは、私の中にいる母をも嫌悪しているということだ。私の中の母は私を監視しジャッジしているのだから、私の中で、大嫌いな母親が私を低く評価し、それを私が嫌い、嫌っている私を私の中の母が押さえつけようとする。負の循環が永遠に起こっている。
胃の中に手を突っ込んで、体中の粘膜に貼りついた「母」をベリベリと剥がし、すべて吐き出してしまいたい。