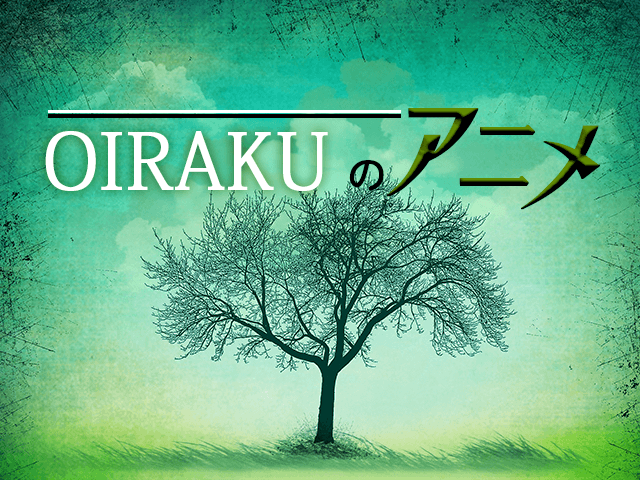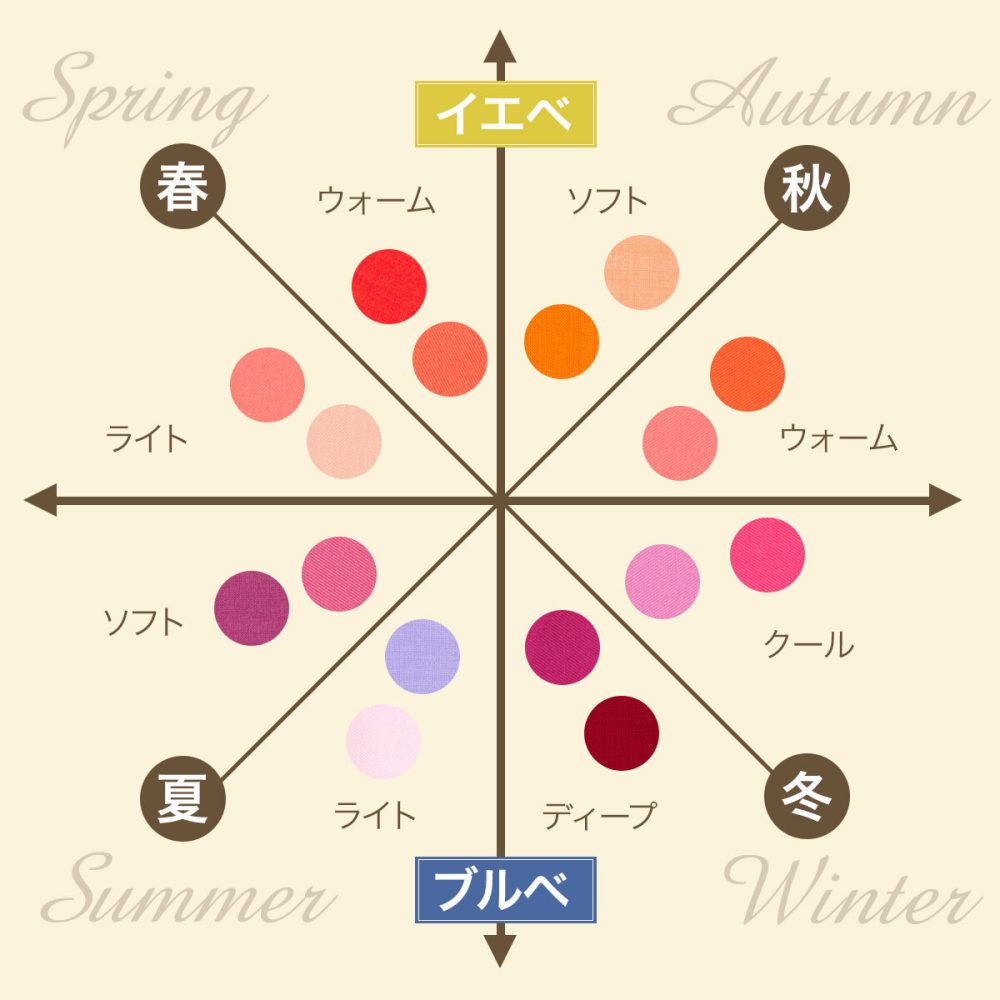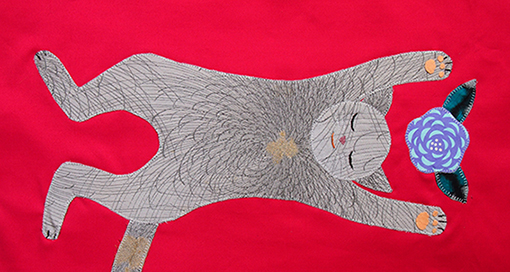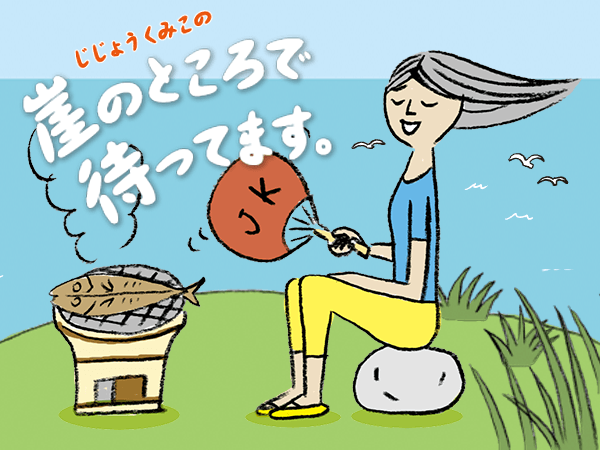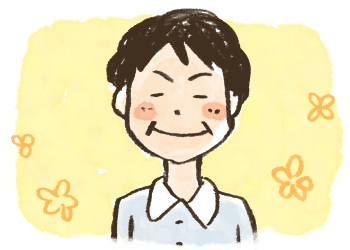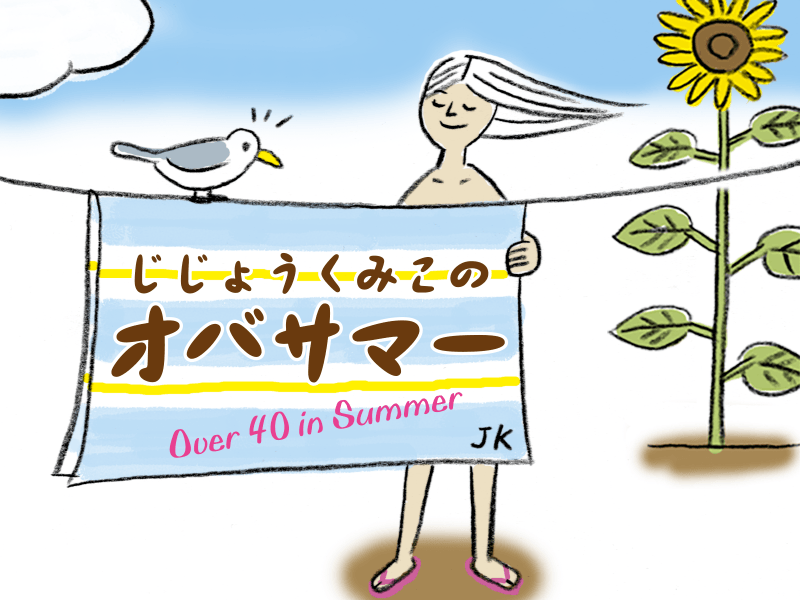【月刊★切実本屋】VOL.57 旅の本で顕わになるもの
旅行はほとんどしないが旅の本は好きだ。
1980年代、そもそもは『メメント・モリ』で知った藤原新也だが、遡って『印度放浪』『西蔵放浪』『全東洋街道』などを立て続けに読んだ。それらは『東京漂流』と共に今も本棚にある。三度の引っ越しでも処分しなかったのは、時を重ねたらまたきっと、これらを開きたくなる日が来るだろう、と思ったからだ。
当時、旅の本業界を席捲していた『深夜特急』にはなぜかあまり心惹かれなかった。沢木耕太郎は『一瞬の夏』や『敗れざる者たち』は繰り返し読み、特に『一瞬の夏』は、カシアス内藤、エディ・タウンゼント…など、今でも登場人物(?)をそらで言えるほど傾倒したのだが、『深夜特急』は、大沢たかおの印象と、平野甲賀による独特の字体の表紙が浮かぶばかりだ。

あれから幾星霜、たまたま目についた旅の本はそこそこ読んできた気がする。今ではもう、その多くは忘れてしまったが、椎名誠、星野道夫、石川直樹、高野秀行、たかのてるこ、宮田珠己…の著作は複数冊読んだ記憶があるので好きだったのだと思う。このなかに欧米の旅の本はほぼない。これって、出会いがしらの藤原新也の呪縛なのか、非欧米特有の混沌さに惹かれる自分がいるのか…自分でもよくわからない。
そんななか、気づいたことがある。芸能人が書いた旅の本に、意外とイケるものが多いのではないか、だ。
仕事柄、海外に行く機会が多いという頻度面(インド綿みたい)もさることながら、国内では有名税とも言われる「他者の目を気にせざるを得ない」日常が、海外では自由になり、それによって、自意識の開放と旅がおもしろくブレンドされたりするのではないか。
それと、メディアを通して本人を知った気になっているというこちらの勘違いで、知人の紀行文のように興味深く読める、というのもあるかもしれない。『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』がそうだった。

これは、お笑いコンビ、オードリーの若林正恭のキューバがメインの(モンゴルとアイスランドの章もある)旅行記である。この旅の前々年、ニューヨークの熱気と邪気に当てられ疲弊感を覚えた彼は、帰国後、夏休みが5日とれると知り「キューバに行こう」と思い立つ。
旅行代理店の女性に「どうしてキューバへ?」と聞かれた彼は、初対面の人間に詳細を説明する必要もないと思い、テレビの受け売りで「アメリカとの国交が回復して、今のようなキューバが見られるのも数年と聞いたから」と答え、彼女から「キューバに行かれる方が、みなさん、そうおっしゃいます!」と元気に返される。
いよいよキューバ行きの(実際は中継地点トロント行きの)飛行機が離陸する。エンジン音が響き渡り、速度を増しているとき、彼は自分の嫌いな言葉「コミュ障」「意識高い系」「スペック」「マウンティング」「オワコン」…などが自分の中に一度、一気にフェードインしてきて、今度はものすごいスピードでフェードアウトしていくのを感じる。アメリカ合衆国由来とも思える価値観から解放されたのだ。
…この、鬱屈したものを忌憚なく、それでも下品にならずに「書く」導入部は見事だ。キューバに到着してからも、特異な歴史を持つこの国のリアルな旅行記として読ませてくれる。旅につきものの「自分探し」からの屈折した距離感を持ったエッセイとしてもおもしろかった。
あらためて、大勢の中から頭角を現し、もぐらたたきゲームにも撃沈せずに存在し続けるお笑い芸人の知力と体幹の強さを感じた。そして、この旅の本当の目的が明かされるくだりは、多少狡猾だと思ったが、泣いた。…いややっぱり、多少どころか、相当狡猾だ。やられちまった。

片桐はいりの『わたしのマトカ』『グアテマラの弟』、岸恵子の『ベラルーシの林檎』なども、秀逸な旅の本だと思う。若林、片桐、岸、三氏の共通点は、旅を記すことで知性が顕わになるところではないだろうか。旅を経て文章に起こすまでに幾度も咀嚼や推敲はあるにせよ、旅って、どんなに緻密な計画を立てても予定どおりにはいかない分、本性と共に知性が出てしまうと思うのだ。
だから私は旅をしないのかもしれない。
by月亭つまみ