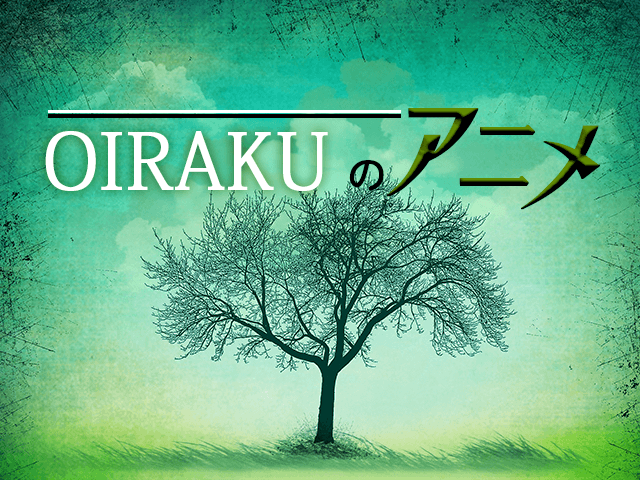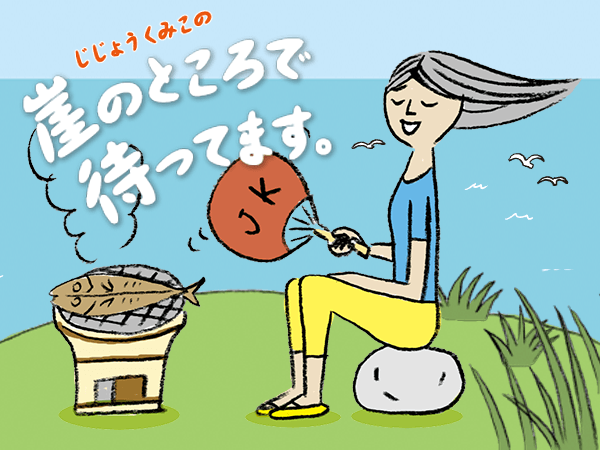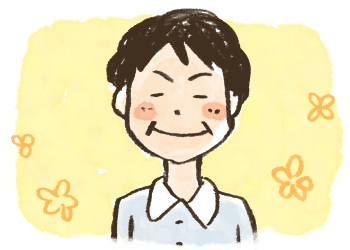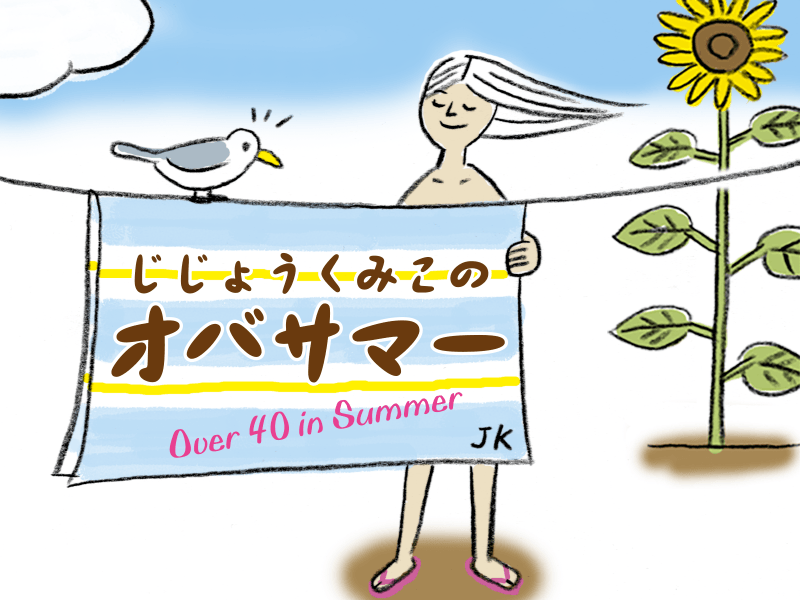【月刊★切実本屋】VOL.61 開き直りにも似た諦観、と二度書いてる。
今まで、本屋さんになりたい、本屋さんで働きたいと思ったことはない。本を読むのも、読みたい本が醸し出す気配も、好きだが、商品として陳列されている本の中で働くことには魅力を感じなかった。
そうカミングアウトすると、なんだか自分の底の浅さとか安っぽさを露呈させてしまう気がするが、しょうがない。所詮、自分の「本に対する思い」なんてその程度だからなあという開き直りにも似た諦観もある。
が、『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』(辻山良雄/著)を読んだら、そんな今までの気持ちが少し変わった。いや、もしかしたら、徐々に変わっていたことに気がつかなかっただけかもしれない。

東京の西、人も羨む(!)中央線の荻窪にあるTitleは稀有な本屋だ。全国には、店主の思いが詰まった個性的な本屋は数多あるだろうが、中でもTitleは特別な気がする。辻山さんの意思を反映した店のしつらえ、選書、並べ方、手入れ具合もさることながら、本に対する思いを届ける言葉を持っていて、それを的確に表現し、伝えることができることがとても大きいと思う。
Titleに行って、ああ、ここは自分にとって格別な本屋だと思った人は多いと思う。私もそうだ。いつまでも居たい、そしてまた来たいと思わせる小規模な本屋、実は私にはあまりない。一周して店の雰囲気や傾向を掴んだ気になり、安易にジャッジして出てきてしまうことも多い。小規模だからこそ、より感じる品揃えというフィルターに、圧というか、居心地の悪さを感じてしまうこともままあるのだ。
Titleはちがった。まるで、店内にある本すべてが自分を待っていてくれたような、まだこんなに読む本があると思えたことで、店に入る前より自分が豊かになったような、気がした。そして、本屋に居ながら、自分の現在の仕事場である学校図書館の棚の配置や見せ方、特集本や図書だよりやイベントについて思いを馳せたりもした。
だが、そんなスペシャルな体験も、時間が経つと印象が希薄になる。Titleは家から遠いので、出向くには東京23区を横断することになる。そしてコロナ。どうしても足は遠のき、もう何年も行っていない。そして、記憶が薄れた頃、この本を読んだ。そしてむしょうにTitleに行きたくなった。

この本は、出版社のwebサイトで掲載された文章の書籍化だ。文体はおしなべて静謐だ。読み始めた当初は、実際に店で辻山さんを見たときに感じた「平常心オーラが強過ぎて、逆にこっちが平常心でいられない」という印象を思い出したが、読むほどに、フラットさに隠れていた文章の瑞々しさが心地よくなった。そして、一見変わり映えのしない日常を流すことなく地道に続け、平易な言葉を誠実に紡ぐことでしか行き着かない唯一無二の場所があるのかもしれないと思った。

本に対する思い、両親の闘病と死、顧客のエピソード、東日本大震災の被災地でのこと…どの文章も心に沁みたが、「わたしにはなにもないから」という章が特に心に残った。
自分の作った本を置いてほしいとやってきた女性に、作品の足りなさを感じて断る、その言葉のなんと的確で、ゆえに残酷なことか。そんな言葉を発しつつも、断った相手から表題の言葉を返されて胸にこたえた辻山さんは、章の最後をこう締めくくっている。
【自分には何もないと思う人生は、リアルな苦労を抱える人生よりも軽いのだろうか。(中略)なにもない自分を見続けた先には、何か待っているものがあるのだろうか。それがわからなくてもわたしたち後ろめたきものは、知りぬいている退屈な自分とともに今日も生きていくしかない。】
世界がコロナ禍と称される状況になって以降の、小売店店主としての苦悩や逡巡、その中にも希望の光を感じること、なども率直に記されている。同じくコロナに言及したエッセイで最近読んだ、文筆業界隈の女性数人による往復書簡の中の、コロナ禍の日々での内省的文章より百倍よかった…って、どさくさに紛れてディスってしまったので、ちょっと薄い字にしてみた。
でも「信じて疑わなかった日常から突然切り離されてしまった」とか言われてもなあ。凡庸過ぎるにも程がある。少なくても、非常事態宣言明け直後から電車に乗って人との接触の多い仕事に行くという「日常」を再開した自分や家族には響かないぞ。もっといえば、自己憐憫に浸ってもいいが(当初はみんなそうだったし)、そこに、不安と恐怖を覚えつつ使命感を持って各方面の現場の最前線で働いている(現在も過去形ではないのがツライ)人々に心を寄せる何かが少しでも感じられればまだしも、とも思った。
そんな風に思ってしまう自分はつくづく現場至上主義なのだなあと、これまた、開き直りにも似た諦観を抱いている2022年中秋の名月イブイブだ。
by月亭つまみ