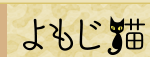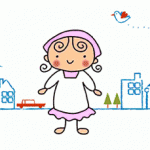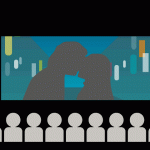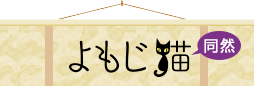Posted on 2017年4月6日 by まゆぽ
エピソード10★大きな店から小さな店へ。
さてさて、聞いた話を形に残すことを仕事にしている「有限会社シリトリア」(→★)。
普通の人の、普通だけど、みんなに知ってほしいエピソードをご紹介していきます。
【エピソード 10】
昭和30年代半ばに神戸の繁盛する料理屋の娘として生まれたアキコさん。祖父母と父母が切り盛りしたお店の盛衰と、アキコさんの目を通して見た家族のお話の後編です。
身内と、身内同様に気のおけない板さん・仲居さんだけのお店だった時代を経て、お店が会社組織に成長したその後の物語をお届けします。

昭和の初めの神戸のとある駅前に大繁盛をしていた一軒の料理屋がありました。家族で商ってきたお店は、昭和40年代半ばに大きな転換期を迎えます。周辺の再開発でお店が立ち退きを迫られることになったのは、アキコさんが小学校6年の時のことでした。
「隣の和菓子屋さんは立ち退きを早々に受け入れたようですが、うちは祖母が条件面でかなり粘ったんですね。そのため、今で言うところの地上げ業者みたいな人たちから嫌がらせも受けました。店の前の駐車スペースに大きな穴を掘られたりとか。
学校ではいろいろ言われました。お前んとこのばあちゃんはガメツイとか。私はおばあちゃん子でしたから悲しかった。初めて、あー寿司屋の子なんてイヤだ、恥ずかしいと思いました…」
やがて店は道一本隔てた場所に移転し、いよいよ大規模な料理店へと変貌を遂げます。テーブル席、カウンター席、座敷席を備えた1階に加え、2階には100人からの宴会のできる大広間と個室。正面玄関とは別の場所に、持ち帰り寿司専門の窓口もできました。板さん、仲居さん、賄いのパートの人たちなど、多い時は20人からの従業員に身内も加わり、店は会社組織へと変わりました。

昭和40年代の神戸 (ブログ「神戸・日々あれこれ2」より)
「祖母の意向もあったんでしょう。そのタイミングで、別の仕事をしていた父の兄弟たちが全員、役員の名目で店に戻ってきました。お店はどんどん繁盛していったけど、私の好きだった、あの小さなお店の雰囲気が、その頃から少しずつ薄れていったような気がします」
高校生になるとアキコさんはバイトとして店で働き始めます。お金を巡る人間関係の歪みや、その中での母親の苦労などを目の当たりにして、自分にできることは何だろう…と思いあぐねた末、大学卒業後、アキコさんは三代目として店を継ぐことを決め、婿養子さんを迎えました。京都の料亭で修業を積んだ板前の夫新しいメニューを考え、時代に合った店づくりを目指しました。
お店はそれなりに繁盛していましたが、似たような和食店が珍しくなくなってきたこと、大手和食チェーンの台頭など、周囲の環境は変わっていきました。しかしアキコさんのお店は、昔気質の祖母がずっと経営を握っていたこともあり、新しい和食店への方向性はなかなか見つけられません。
そんな中、人間関係の軋轢を抱えながら決断の時がきました。アキコさん夫婦は両親と一緒に独立し、新しい店を立ち上げることにしたのです。昭和がまさに終わりを告げようとしていた頃でした。
新しいお店は4つのテーブル席とカウンター席だけ。家族の好きな花の名前を店名にしての再出発です。力を合わせてメニューを考え、おもてなしを工夫し、商売を回していく。大変だけれど、お客さんの喜ぶ顔が店づくりの力になりました。それはもしかしたら、アキコさんの祖父母が始めた最初の小さなお店の第一歩と同じだったかもしれません。
独立した店も畳んだ今、あらためて思い出すのは…とアキコさんは言います。
「私が生まれた、あの小さいお店の時が一番楽しかった。日本全体もどんどん景気が良くなって、ふつうの家族が外で食事をすることが贅沢じゃなくなってきた。そんな時代の熱のようなものがあの店の空気を活気づけてくれていたと思います」
アキコさんの記憶から消えないのは、暑い朝の「麦茶はったいこー!」という、外を歩く売り子の声でした。当時はまだ、麦茶やそば粉を行商で売りにきていた時代だったのです。祖母がその売り子さんから買った麦茶で、大きな大きな鍋で麦茶を沸かして冷やす。汗を拭き拭き暖簾をくぐってくれるお客さんへの心遣いでした。

麦茶 (楽天市場 松田園より)
「麦茶といえば、冷蔵庫の中で四角いプラスチックポットに入ってる。当時、ふつうのおうちはそんな感じでしたよね。私は麦茶と言えば大鍋(笑)。そんな記憶一つでも、ちょっと不思議で貴重な経験をいっぱいしてきた私の“お店人生”だったかもしれません」
- トップの写真/佐藤穂高(広島在住のプロカメラマンです)
- 有限会社シリトリアのHPはこちらから
★月亭つまみとまゆぽのブログ→「チチカカ湖でひと泳ぎ
★ついでにまゆぽの参加している読書会のブログ→「おもしろ本棚」よりみち編