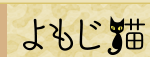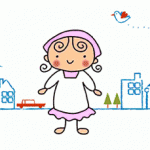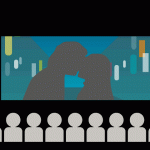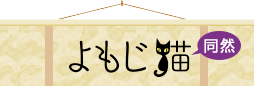Posted on 2024年11月23日 by はらぷ
グッドバイ

一昨日の夕方、11月19日。我が家のねこテーちゃんは、安楽死というかたちでこの世を去った。推定15歳と8ヶ月。2010年の6月から共に暮らした。
わたしたちがノラのティーちゃんを迎えたのは、結婚して、東京郊外に小さなボロ家を買って引っ越した翌年の春だ。わたしたちにとって、家を持つことと、ねこと暮らすことはイコールだったから、さいしょに浮上したねこの保護話がティーちゃんだったことは、神さまにどんなに感謝してもしたりない。
その後の14年間にはいろいろなことがあった。
臆病なティーちゃんはうちにきた初日に姿をくらまし、その後家の中にひそんでいたことがわかったものの、触れるまでに約半年の時間がひつようだった。
東日本大震災があり、子ねこのスマとの共同生活がはじまって(ティーちゃんの屈託ぶりはそりゃあもう見ものだった)、冬は寒く夏は涼しい、妙に日当たりだけはいい我が家の窓際で、ティーちゃんはじつにマイペースに、わたしたちとの暮らしになじんでいった。
6年前に結石で急性腎不全を起こし、サブシステムという人口の尿管を装着して生き延びたあとも、大波小波の体調不良を乗り越えながら、お医者も「すごいねえ、」と褒めるくらいの予後のよさだったのだ。
イギリスへの引っ越しが決まりかけたとき、いちばん心配だったのはティーちゃんの体調だったけれど、日本で準備している一年間のあいだ、ティーちゃんは食欲を取り戻し、体重もちょっと増えて、血液検査の結果も良好、「飛行機での移動も、まっ大丈夫でしょう」と太鼓判を押された。こちらに到着して、ベッドの下でかたまるスマを尻目に、翌日にはトイレを済ませ、家の中を探検した。3キロのちいさい体に、慎重さと、驚くべき勇気が混在する不思議なねこだった。
昨年の夏、ティーちゃんのサブシステムははじめての細菌感染を起こし、あわやと思われたのだが、その後驚異的な回復をみせて、この一年間は今までにないくらい体調が安定していた。処方してもらった薬をのんで、毎日ちゃんとうんちをし、食べたいごはんだけを要求し、日の当たるベッドで丸くなって眠る日々は、安寧そのものだった。
それでも、今年の9月くらいから、ふたたび体力が落ちはじめ、薬が効きにくくなってきていた。食べないことによる体力低下、脱水、それにともなう便秘、体調不良、さらなる食欲減退、という悪循環がたびたび起こり、補液の点滴や、うんちの摘出でそれをいったんリセットし、また繰り返す。げんきなときはいつものごきげんなテーちゃんで、今日はうんちが出た、明日は出るか、とうんちに一喜一憂する日々だった。
そして今月に入ってから、ふたたび細菌感染が確認された。昨年いい仕事をしてくれた抗生物質は、もう効かなかった。ティーちゃんはラジエーターの前にうずくまって過ごし、ときおり口を開けてよだれをたらした。
週末、集中的に補液をしてもらったティーちゃんは、少し元気を取り戻したように見えた。でも週明けの朝、ふたたび病院に連れていって、待合室で待っていると、びっくりするくらい長いつけまつげをしたナースがやってきて、「ティーちゃんの点滴は終わったけれど、いま先生が別の病院と電話してるからもう少し待ってね」と言った。そして、少しすまなそうな顔で、「何か飲む?」と聞いた。わたしは愚鈍で気付かず、「大丈夫です」と答えたけれど、まつ毛のナースはそのときもうわかってたのだ。ほどなく獣医の先生が別室にわたしを呼んで、もうティーちゃんにできる治療はなにもない、と告げたのだった。
週末にあれだけ補液をしたにもかかわらず、ティーちゃんはひどく脱水していて、つまりテーちゃんの体はもう水分をためておけない。もともと平熱の低いティーちゃんだけれど、体温はさらに下がって34度、血圧も低下してきている。ティーちゃんの体が、その機能を終えようとしているのだった。
保って数日、これからティーちゃんは苦しくなっていくばかりだからと、その前に安楽死をすすめられる。そんなこと言われても、これからしばらく、積極的な治療はしないまでも、家で点滴しながらもう少し過ごせるかと思っていたのだ。ほんとうは今日、点滴の方法を習う予定でここに来たのに。
「看取り専門の獣医さんに家に来てもらうこともできる」と先生が名刺をわたしてくる。それをポケットにねじこんで、「とにかく今日は帰ります」と病院をあとにした。先生は、支払いとかはあとでいいから、とドアまで一緒に来てくれた。わたしが泣いていたので、それを他の飼い主たちに見せたくなかったのもあるんだろう。
家につくと、ティーちゃんはよろよろとケージから出て、おしっこをしてから2階まで自分で上がって、わたしたちのベッドにもぐりこんだ。わたしは職場に具合が悪いので休みますと電話をして、上司に「大丈夫?風邪?」と聞かれたけれど、「わからないけどとにかく具合がものすごく悪いんです」と言って電話を切り、職場にいるオットにも電話をして、それからはティーちゃんの傍らで過ごした。
わたしがベッドの端にすわると、ティーちゃんはふとんから出てきて、私の膝によじのぼった。窓からの光で、ティーちゃんの後頭部はつやつやとして、耳の血管が透けて見えた。
あの、触れもしなかった、抱っこの大嫌いなティーちゃんが、自分から来るなんてなあ。
数日前から、ティーちゃんはわたしたちのそばを離れなくなり、夜もふとんの中に入ってきて、わたしのお腹にぴったりとくっついて寝るようになっていた。ティーちゃんと暮らした14年間、いままで一度もないことだった。
ティーちゃんとこうして過ごせる時間は、あとわずかかもしれない、そう思っても、ティーちゃんを長く膝にのせていると、だんだん体が痛くなってくる。そろそろトイレにもいきたい。おなかもすいてきた。こんなときにもおなかがすくなんて、本気が足りないのではないだろうか。わたしがもぞもぞしはじめたので、ティーちゃんは気を悪くしてふとんの中に戻ってしまった。
そのタイミングでおしっこに行き、台所でカップラーメンをいそいで食べて、またすぐに寝室に戻る。わたしもふとんに入って体をよこたえると、ティーちゃんはわたしのおなかに頭をあずけて、腿のあいだにはさまって眠った。ティーちゃんの体は軽くてひらたい。ときどき、身を横たえたまま少量のおしっこをした。色もにおいもない、透明のおしっこだった。
ときどきティーちゃんの息を確かめながら、わたしも少し眠った。

夕方、早めに仕事を切り上げて帰ってきたオットと長い長い話をした。ティーちゃんにとって一番よい選択はなにか。それは本当にティーちゃんのためなのか。そもそも、わたしたちにそんな選択権があることからして、不自然なことなのだ、動物を飼うということは。ティーちゃんは選べない、うちに来たことだって、手術をうけたことだって、これまで治療を続けてきたことだって。ねこはいつもだまって受け入れるのみだ。
わたしたちは、堂々巡りの会話を延々と続け、やがてついに降伏した。けっきょく、口に出せないことばを避けて、その周りをぐるぐると巡り続けているだけなのだった。
それが「よい」ことかどうかわからない。でも、いちばん、ティーちゃんに優しいことをしよう。今まで文句も言わずわたしたちの無茶につきあって、とうとう外国にまできてくれたティーちゃんを、いちばん甘やかす方法。わたしたちにんげんができる、もっとも不遜で不自然な方法で。

その日の朝、窓を開けると、まだ11月だというのに外はうっすらと雪景色だった。わたしはふたたび仮病を使って仕事を休み、オットは泣きながら、午前中だけちょっと仕事片付けてくると出かけていった。
夜中じゅう、ふとんとトイレを往復していたティーちゃんは、朝になると静かになって、体を横たえていても、目を完全に閉じないようになった。ふとんをめくって匂いをかぐと、かすかにあの匂いがした。実家のねこたちも最後に発していた、死にゆくものの匂い。
ティーちゃんのかたわらに身を寄せてわたしも横たわっていると、こうしているうちに、ティーちゃんはそのまま死ぬんじゃないかという気がした。そうだったら、そのほうがいいのにな。
ところが、13時ごろにオットが帰ってくると、ティーちゃんは一階に降りてきて、何か食べたそうなそぶりを見せだした。腎臓に悪いので今まであげないようにしていたかつおぶしのパックをあけると、鼻をならして食べ、自分で水さえ飲んでいる。
ちょっと…死ぬには元気すぎるんじゃ…。
この数日培われてきたわたしの受容は一気に崩れた。ティーちゃん、何してくれてんの…。
「やっぱり、今日はキャンセルしよう」と一気呵成にいうと、オットは意外にも冷静に、
「もしほんとうにそれを望むなら。でも、それがほんとうにティーちゃんのためかわからない」と言った。
「ティーちゃんが回復するとはわたしも思っていない。でもこの調子なら、もう何日か穏やかに過ごせるかもしれないのに」とわたしが泣きながら言っても、オットは、
「その数日間は、ティーちゃんのためじゃなくてMのためだよ」と言うのみだった。
タイミングを逃して、ティーちゃんが苦しみだしたら、ひとりでいかせてしまったら。それを回避するために、わたしたちは決断したのじゃなかったか。
泣いて、地団駄を踏んだら、誰かがなんとかしてくれないだろうか。
それからの数時間、ティーちゃん、オットとわたし、スマの4にんで寝室で過ごした。さっきまで活動的に見えたティーちゃんは、オットの足の間にはさまってほとんど動かなくなり、少し目の焦点があわなくなってきていた。ふだんなら嫉妬しておおさわぎするスマが、ベッドのはしで静かに目をつぶっている。
北国の夕暮れは早い。薄暗くなった部屋で、4にんひしめきあってじっとしていると、わずかな往来のざわめき以外、なんの音も聞こえない。なんてこの世は静かなんだろう。
看取りの獣医さんは5時半ぴったりにやってきて、6時半には帰っていった。
なにひとつ変わらない部屋で、変わったのは、ティーちゃんがもうこの世にいないことだけだ。オットの膝の上から、ティーちゃんは旅立っていった。聞き分けがよすぎる。もがいて、わたしたちを後悔のどん底に突き落とすことだってできたのに。
その夜は、ティーちゃんと同じベッドで眠った。右隣に死んだティーちゃん、左隣に生きているスマをしたがえて。うとうとしては目が覚めて、ティーちゃんに触るたび、ティーちゃんの体は冷たく硬くなっていった。
翌朝、ひさしぶりの太陽がベッドにひだまりを作っていて、ティーちゃんの後頭部はやっぱりつやつやとして、耳の血管が透けて見えた。
「ああ、ティーちゃんはこの太陽を楽しんだろうにな」と言ったら、オットは「ぼくもおんなじこと思ってた」と言ってまたちょっと泣いて、「あーあ、母が死んだときのひゃくばい悲しい」と言った。いくらなんでもひゃくばいはひどい。


byはらぷ