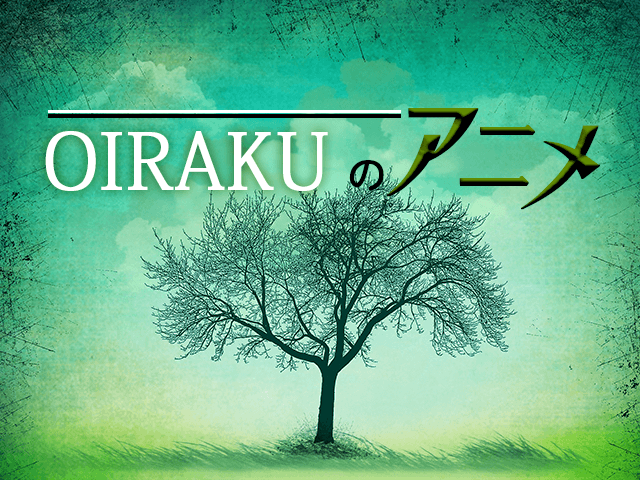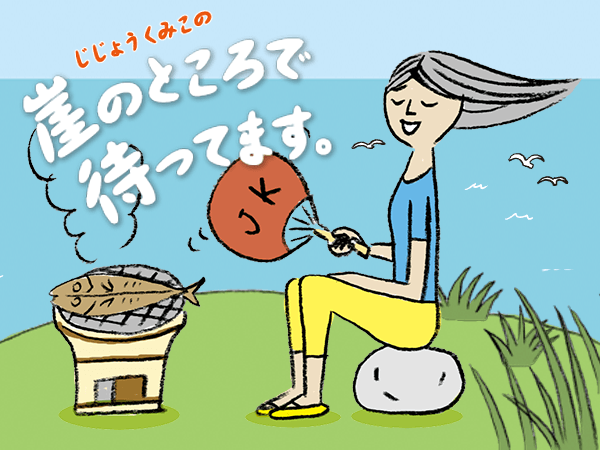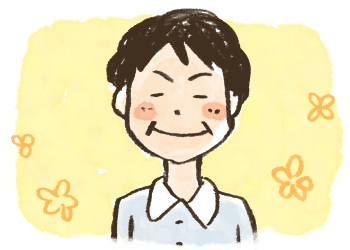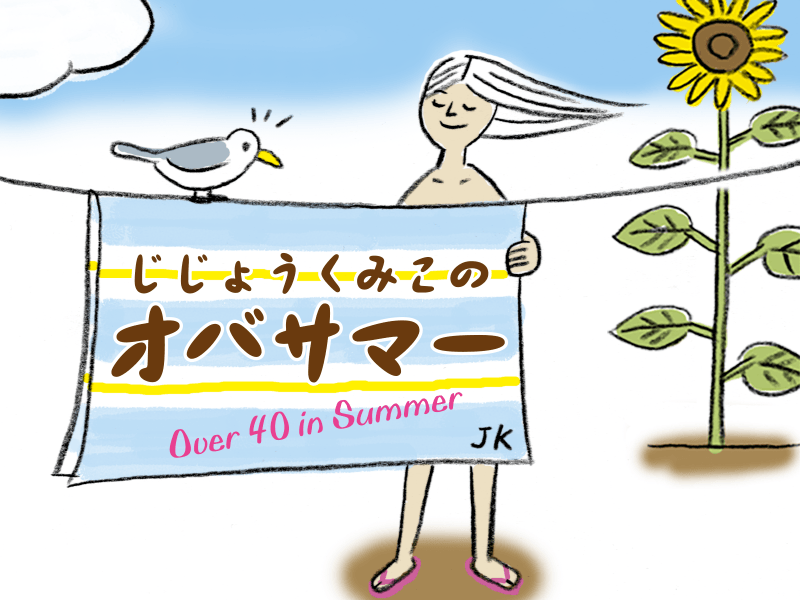【月刊★切実本屋】VOL.74 工場
職歴を問われると、事務員と図書館員を交互ぐらいにやってきて今日に至る、と申し述べることが多いけれど、自分には工場勤務経験もあったのだと、『工場』(小山田浩子/著)という小説を読んで思い出した。
高校卒業後、学校に行きながらしばらくの間、工場で働いた。場所は神奈川県川崎市。大手電機メーカーの東京工場(東京ディズニーランド方式の呼称)だった。最初の工場の印象は「敷地がやたら広い」で、はじめの頃は何度か迷子になりかけながら配属された有線事業部に通った。そこでは、ビルなどで使用する大型の電話交換機を作っていて、わたしは検査班に所属した。
仕事はほぼ「見ること」だった。検査機械の前のイスに座り、検査対象のパネルを1枚ずつ検査機械のしかるべき場所に挿し込み、スタートボタンを押し、順番に点灯するランプを目で追うのだ。パネルに装着されたたくさんのICチップとランプは対になっていて、ICチップに不具合があると、そこのランプが点滅するのだった。

なぜずっと見ていなければならないかというと、点滅する時間はほんの数秒間だからだ。点滅を数回繰り返すと「はい、お知らせタイム終了!たしかに教えたからな!気づかなかったとは言わせないからな!」とばかりに、検査は次のチップに進んでしまう。だから居眠りなどもってのほかである。‥したけど。
ひたすらランプを見続け、点滅があればその箇所をメモしてパネルを不良品箱に入れる。慣れてくるとかんたんな修理もするようになった。不良とジャッジされたICチップを外し、新しいものに付け替えるのだ。ICチップは、上のイメージ画像ほどではないが、足が多くそのすべてが接合されているので、それを一箇所ずつ溶かして外し、新しいチップに付け替える。生まれて初めてハンダゴテを使った。その仕事以降、今日までハンダゴテを使ったことは一度もない、そういえば。

肉体労働ではないし、仕事の性質上、急かされることもなかった。工場のなかには、ラインに入って流れ作業をする家電関係の部署もあった。ラインじゃなくてよかったね、ラッキーだったねと複数の人にに言われ、ああ、そうなのかと思った。左利きはライン作業には配属にならないらしいというのはずいぶんあとで知ったことだ。工場には自分の知らない決まりごとが山のようにあることが察せられた。
工場内は夜間でも煌々と照明が明るく、今がいつで何時でここがどこなのかわからなくなるような感覚にしばしば襲われた。工場での日々を思い出そうとすると、工場内の照明がハレーションを起こしたような脳内画像が浮かび、記憶そのものもまぼろしのような気がするなあとよく思いながらその後の人生を生きてきた。

でも今回、『工場』を読んだら、自分の工場時代の記憶が蘇った。この小説にはハレーションを蹴散らすぐらいの力があったということかもしれない。それは
① 巨大(もしくは大きめの)工場に雇われ
② さほど大変ではない仕事をして報酬を得て
③ 工場の全体像も、そのなかでの自分の仕事のポジションも、そもそもそこは何を作ったり(調べたり)しているのかもあまりわからないまま
という共通点のせいかもしれない。
わたしの工場体験は、常に睡魔との闘いではあったものの、ネガティブな記憶は特にない。若い男女が多かったので、それなりに甘酸っぱい思い出もある(忘れていたけれど)。それでも、工場そのものが少し不気味で得体の知れない存在だった感は否めない。
もしかしたら、工場に一度入ったモノは、物であれ人であれ左利きであれ、知らないうちになんらかのラインに乗せられ、なんらかの処理をされて出てくるのではないか、入ったときとそっくり同じまま出てくる物はもちろん、人もいないのではないか‥みたいな。

働くということは、わかって動くことばかりではなく、むしろ、わからないまま、やれと言われてやることの方が多いという原体験があの工場勤務で培われたのかもしれない。でも、たとえば右の箱にあったパネルにしかるべき検査をし左の箱に移すという、虚業ではない実業的労働を、仕事人生のしょっぱなに経験できたことは案外悪くなかったのではないかとも思っている。
‥ただし、ただしですよ。その認識が、遠い昔とはいえ、工場に足を踏み入れたことによって自分に作為的に付与された概念ではないという確信はない。ライン作業には就かなかったが、工場で仕事の価値観の源流形成のラインにも乗っからなかったとは断言できない。
工場の入口はブラックホールのそれかもしれない。小説の方の『工場』は、そんな類の妄想を感じさせる小説だった。‥あ、内容にはほぼ触れてないや。
by月亭つまみ