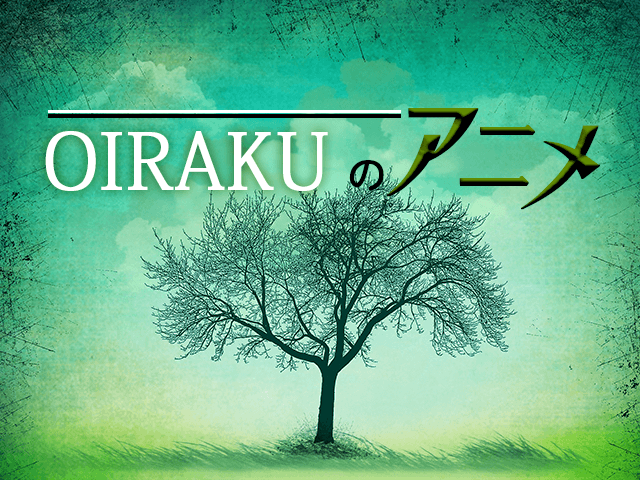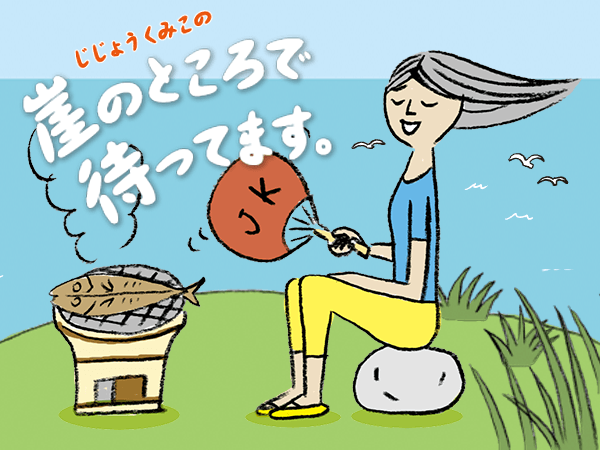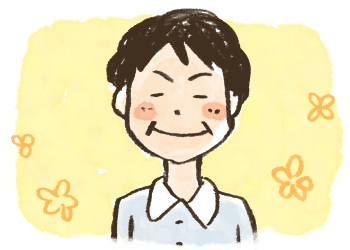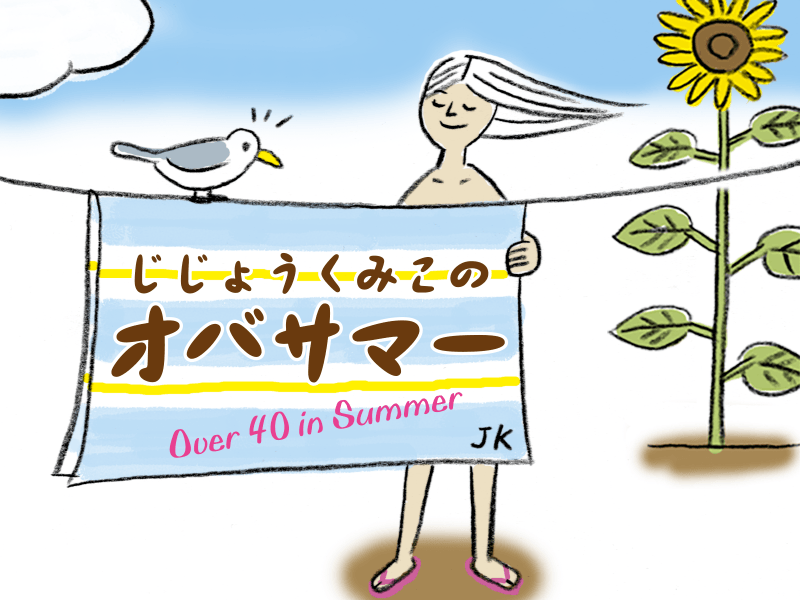『山の上の家/庄野潤三の本』を読んで

夏葉社刊行の『山の上の家 庄野潤三の本』が面白い。もともと庄野潤三のファンだということもあるけれど、こんなにもまっすぐに小説家である人がいたのだというだけで、とても心が温まり、そして、人生をいいものだと思うことができる。
庄野潤三その人の文章もそうなのだけれど、持ってまわった言い方をすることがない。自分がわかっていることを云うときには平たく云うほうがいい、と彼は書く。持ってまわった言い方をしたほうが内容に重みが加わると思うのは間違いで、反対に心ある人のあなどりを受けるだけである、とも書いている。だからこそ、庄野潤三の文章はのびやかでたおやかで生き生きとしているのだろう。
芥川賞をとった『プールサイド小景』など初期の作品は、暮らしの中の不安を描いて面白いが、それ以降の庄野潤三はいつも家族とともに過ごした山の上の家での暮らしを小説の中心に据えることが多い。
庄野潤三は若い頃に、これからどんな小説を書きたいのか、エッセイに書き残している。
「読み終わった読者の胸に(生きていることは、やっぱり懐かしいことだな!)という感動を与える—-そのような小説を、僕は書きたい」
これから小説を書き続けようとする若い作家が、「生きていることは、やっぱり懐かしいことだな!」という感動を与えたいと考えている。この言葉への奇妙な感動はどこから来るのだろう。それは「生きていることは懐かしい」という言葉への違和感だろう。
だが、確かに庄野潤三が書く小説の中に立ち現れてくる世界は、生きていることは素晴らしいという手放しの、未来への賛歌ではない。おそらく、戦争を経て、家族と共に平和に暮らせる世の中で、小説を書くことが出来るという喜びは、一度死んで還ってきたという感慨の上に成立していたものなのかもしれない。
そうでなければ、庄野潤三が死の間際まで書き綴った家族の物語が、平和で幸福で満たされているのにも関わらず、ひりひりとするような切迫感をも同時に感じさせる理由が見当たらないのだ。
かつて開高健が「小説家とは広大な草原を切り立った断崖を歩くように歩く者のことだ」と語ったことがあるが、まさに庄野潤三はそんな小説家の一人だったのだろうと思う。
声高に叫び、噛みつくのではなく、穏やかに微笑みながら書き綴られる世界にそっと死の影を忍ばせ、それが生きることの素晴らしさをより鮮明に浮かび上がらせる。そんな庄野潤三の世界は、みんながSNS以外では黙り込み、目も合わせない現代だからこそ、読まれることに大きな意味があるのかもしれない。
庄野潤三の作品をこれまでに読んでいる人は、ぜひこの本を手にして欲しい。もし、彼の作品の読んだことがない、というのなら、まず書店で彼の代表作が収められた文庫版の小説集を求めて一読してほしい。その上で、面白いと思えたなら、この本を読んでみると良い。きっと、父として小説家として、できる限り朗らかに生きようとした男の、ぬくもりのようなものがページとページの間に、行と行の間に感じられるのではないかと思う。
植松さんとデザイナーのヤブウチさんがラインスタンプを作りました。
ネコのマロンとは?→★
「ネコのマロン」販売サイト
https://store.line.me/stickershop/product/1150262/ja
クリエイターズスタンプのところで、検索した方がはやいかも。
そして、こちらが「ネコのマロン、参院選に立つ。」のサイト
http://www.isana-ad.com/maron/pc/
植松眞人(うえまつまさと) 1962年生まれ。A型さそり座。 兵庫県生まれ。映画の専門学校を出て、なぜかコピーライターに。 現在は、東京・大阪のビジュアルアーツ専門学校で非常勤講師も務める。ヨメと娘と息子と猫のマロンと東京の千駄木で暮らしてます。サイト:オフィス★イサナ
★これまでの植松さんの記事は、こちらからどうぞ。