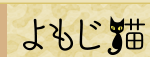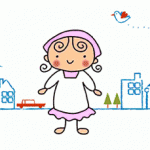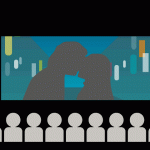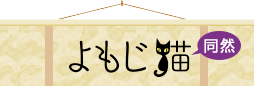Posted on 2024年4月18日 by はらぷ
春の地響き

イギリスは、緯度としては北海道の北端よりも北にあって、首都ロンドン北緯51度、現在住んでいる北部の町ヨークは53度。樺太くらいの位置である。
にもかかわらず、メキシコ湾流と偏西風の影響で気候は温暖…というのが学校で習った地理の知識だが、はるか遠くのメキシコから、どうやってあたたかな海水がイギリス諸島まで届くのか、地球はほんとに不思議である。
温暖…かどうかはあくまで比較であって、ヨークの冬はやはり「北国の冬!」という感じがした。その印象のみなもとは、気温というよりも、いつ終わるともしれない悪天候と、昼間の短さ、午後4時に日が落ちた後の長い夜である。じっさい今年の冬は例年に比べてずいぶん気温が高かったようで、ことによると放射冷却でぐっと冷え込む東京の冬よりも暖かかった。
それでも、11月から3️月にかけて、小雨が降ればたちまち川が溢れ、家々の壁や舗道は常に湿ってぬかるんでいる、という毎日を過ごしていると、北国では春が待ち遠しいってこういうことかあ、とわかるような気がした。しかし一方で、曇りマークが延々と続く週間天気予報の陰鬱さとはうらはらに、意外と陽が差す時間もあるのがほんとうである。こちらの天気はめまぐるしく変わるので、一日のうち数十分(すうじっぷん!)、さーっと光が差してくる瞬間がある(日もある)。すると目に見えるものすべてが劇的に違って見える。そしてしばらくして、それが影のせいだと気がつくのだった。光のあるところ影ができるというこの世の摂理を思い出す。雲が切れて薄い青空が顔をのぞかせ、地上のどこに明るいパッチをなげかけているかがくっきりと見える。
1月から2月にかけては、暗黒の季節と思いきや、その間ずいぶん季節の変化を楽しんだ。1月も中頃を過ぎると、木々は冬芽をのぞかせはじめ、ぺたんこになって越冬していた草花たちも、少しずつ若い葉の角度を上げていく。ハリエニシダの茂みは冬でも盛んに黄色い花を咲かせているし、夏には旺盛な葉でおおわれていた木々の枝ぶりや幹の模様をじっくり楽しめるのも冬ならではの楽しみだった。ようは、日本にいるときと同じで、わたしはけっこう冬が好きである。
そんな中、年が明ける頃くらいからだったろうか、ときどきふしぎな感覚におそわれるようになった。言葉にしていうと、「ああ、どうしよう、もうすぐ春が来てしまう」というような気持ち、春の小さなきざしを発見しては喜んでいるような日々にあって、これは奇妙なことだった。
最初のうちそれは、こちらに越してきてもう10ヶ月くらいも経とうというのに、仕事も決まらずいつまでもままごとのような生活をしている、そんな状況に焦っているのだと理解していた。ところが、補欠だったところから1月末に連絡をもらって仕事が決まり、働き出しても、その気持ちは心の底にずっと残ったままである。
やはり奇妙なことだった。4月にこちらに越してきて、8月に図書館でボランティアを始め、10月に始めた就職活動で、2つ目に受けたところが補欠になり、2月から働いている。期限付きのパートタイムだけれど、最初の職としては申し分ない。オットもわたしも猫たちも元気だし、毎月の家賃も光熱費も、払うことができている。ヨークは人々も親切で暮らしやすいし、友だちも何人かできた。考えてみれば順風満帆といってもいいくらいだ。具体的にいったい何にたいして不安に駆られているのか、なんなら教えてもらいたいもんだね、わたしが他者なら、そう言ってやるところだ。
こちらでは、少し前から堰を切ったように春が溢れ出し、これぞこの世の春である。あと2週間もすれば一周年、5月がくれば、わたしは49歳になる。

つまりはそうなのだ。わたしはこの先に待ち受ける未来ぜんぶがこわいのかもしれない。
さっき「ままごとのような」と書いたけれど、この茫漠とした不安は、「こんな安寧がいつまでも続くとは思えない」という暗い予感に近い。この暮らしには限りがあって、一年がたてば、残りの時間はそれだけ少なくなってしまう。それだのに、春の奔流に押し流されて、思わぬ先まで運ばれていってしまうような。季節がめぐるのを止められないのと同じように、そのときが近づいてくるのを、わたしは手をこまねいて見ていることしかできない。
「そのとき」というのが何なのか、あまり言葉にしてかんがえたくはないけれど、それはやはり「老い」や「死」と関係しているのだと思う。年老いていくことにより、失うだろう数々のこと、病苦、あるいは金銭上の困難、数年のうちに経験することになる猫との別れ、そして残りは、世界の未来に対する切実な不安感。まだ起きていないすべて。
しかし考えてみると、子どもの頃から常にその予感とともに生きてきたのではなかったか。昭和の子どもだったわたしはノストラダムスの予言を真剣に信じていたし、「そのとき」の自分の歳を数えてカウントダウンに怯えていた。夜ふとんのなかで「にんげんは、生まれた以上必ず死ぬ…」とつぶやいていたのも同時期のわたしである。朝起きて、ランドセルをしょって学校に行くのと同じくらい、一日一日、死に近づいていくことが、生きるということだった。
おとなになって、自らの死についていえば以前より怖くなくなっても、「この生活がいつまで続くかしれない」という気持ちはついて回った。結婚前のオットと暮らした千駄木での4年間は、夢のようなモラトリウムライフだったし、終の住処と思って買った小金井の家での14年間中も、やはり「いつまでこの家に住むかわからないし」と思い続けて、結局手放していまこの地にいるのだった。オットとの生活そのものが、出会って20年たってなお、わたしにとっては夢である。
まだ地に足がついたとはとてもいえないこの新しい場所で、不安にならないわたしがいたら、そのほうがどうかしている。
この世は砂上の楼閣だ。でも、げんきんなわたしは、だいたいはそのことを忘れて、毎日元気に生きている。地下を流れる通奏低音の低いバイブレーションを足の裏に感じながら、それがいつか城を崩して、砂山に変えるまで。


By はらぷ