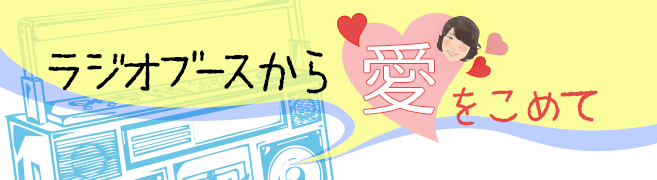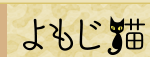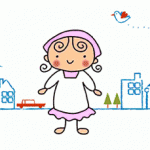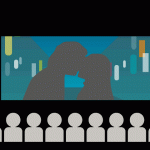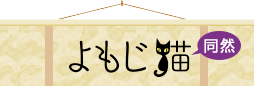Posted on 2017年4月22日 by がっちゃん
音の編集はたのし♪
ラジオ局では4月と10月に番組改編が行われる。終了する番組もあれば、新しくスタートする番組もある。
新しく番組を立ち上げるときは、コンセプトを決め、番組の雰囲気をイメージしながらしゃべり手を選び、企画書を書いてボスを説得し、営業に売ってもらって(売れないことも多いけど)、ようやく実施の運びとなる。
一番苦労するのは、番組タイトルだ。こだわり過ぎて何のことかわからなくなってはいけないし、どこにでもあるタイトルだとインパクトに欠ける。以前お話を伺った批評本の編集長に、「本とか番組とかのタイトル付けのコツはね、名付けの理由をきかれたときに、ワクワクしながら他人に説明できるかどうかだよ」とアドバイス頂いたことがある。確かにそう!その通り!あまりにもナルシスティックなタイトルだと、「なんでそのタイトルなの?」ときかれた瞬間、顔から火が出そうになる。自分でそのタイトルを声に出す度に強烈な気恥ずかしさを伴ったりして。そういうのは、ダメなタイトルなのだ。・・・振り返ると「駄目だったなあ」と思う番組がいっぱいある。タイトルがコケていた。

次に悩むのが、テーマ音楽やBGM、ジングルなどの音関係だ。ラジオはどんな音を使うかで番組のイメージが決まってくる。無難なBGMで庶民的にいくか、カッコいいBGMでクールにいくか、さあどうしよう。
番組タイトルを入れ込んだ10秒前後のサウンドロゴをジングルという。製作費があれば番組オリジナルジングルをアーティストさんに発注できるのだけど、うちの局はお金がないせいか、既製の音楽を使ってジングルをハンドメイドすることが多い。インストゥルメンタルの曲の中の10秒くらいのフレーズを切り取って、アナウンサーのタイトルコールをはめ込み、音の終わりにエコーなどのエフェクトをかける。ディレクターのセンスが問われる仕事である。音の切り取り方によって、またタイトルコールを入れるタイミングによって、カッコよくもダサくもなる。エコーもシャープに決まればよいけれど、ボワ~ンとした響きだと昭和の公衆浴場になってしまう。
ひとり編集室にこもってジングルを制作し、スタッフにお披露目するときは、本当に緊張する。「じゃあ、きかせてもらおう」とか言って集まった皆の衆に腕組みなんかされると、逃げ出したくなる。「・・じゃ、いきま~す!」と言って、苦労してつくったジングルを流す。そして皆の顔色を伺う。良い時は「いいじゃん!」と即座に反応が返ってくる。イマイチの時は、しばし沈黙が流れる。重い空気だ。そして誰かが口を開く。「んー、どうかなー」、「ちょっと、あれだねえ、イメージと違うんだよね~」・・・。そう言われると、私は平静を装うのに苦労する。心の中で「じゃあアンタがつくれよ!!!」って叫んでしまうから。
最近はラジオもデジタルで編集するので、どんな細かい作業もできてしまう。パソコン画面を見ながら、音の波形をマウスでクリック。こうもできるけど、ああもできるぞ、こんなのもいいな・・。選択肢が増えると悩む時間も増える。時間がどんどん過ぎていく。
一昔前までは、アナログで編集をしていた。6ミリテープから6ミリテープへ、ダビングしながら作業をした。だから細かい音の編集は難しかった。そして上手い下手がはっきり分かれた。新人がやると「ぐにょ」「ブツッ」と編集ノイズが入った。
編集には2台のテレコ(6ミリテープをかける機械)を使った。音素材の入ったテープを左のテレコにセットし、何も入ってないテープを右のテレコにかける。左のテレコで編集ポイントを探り、そこから30度くらい手でテープを巻き戻す。左手で左のテレコの再生ボタンを押した次の瞬間、(0.01秒くらいの差で)右手で右のテレコの録音ボタンを押す…みたいなことを、えんえんやっていた。新人の頃はコツがわからず苦労したが、何年かすると体が覚えて編集が楽しくなった。インタビューも録音構成もアナウンサーの失言も、このやり方で編集した。職人になった気分でスパスパと音をつないだ。さすがに最近は6ミリテープを使う機会はないが、ノウハウは体にしみ込んでいる。私の数少ないスキルの一つといえる。どこかでこの技術、役に立たないだろうか。6ミリテープの音編集ならいつでも私に御用命くだされ。

私がラジオの仕事を始めたのは平成3年。その少し前まで、うちの局ではもっとワイルドな編集が行われていた。先輩達は2台のテレコではなく、1台のテレコで編集していた。どうするのか?6ミリテープをカッターナイフで切って、専用のセロテープでくっつけるのだ。不要な部分をスパっと切り落とし、その都度セロテープでつなげていく。足元には切り落とされたテープの端切れが散乱する・・・。なんて男らしいのだろう!デジタル編集になれた世代には絶対に太刀打ちできない。なぜならこれは、やり直しがきかない「一発編集」だからだ。「編集は一発で決める!」これがラジオの王道だ。
このようにして、昔のディレクターは音の感覚、編集の感覚を磨いていったのだと思う。先輩達には本当に頭が下がります。