義弟の死
やぶからぼうですがオットの弟が突然、死んでしまった。
寝ているあいだに心臓発作を起こして、そのまま起きなかった。朝になってパートナーのJが気付いたときには、もういってしまった後だった。
その日、私は夜に出かけていて、遅くに家に帰ってきたら、出迎えたオットが「ちょっとここにすわって」と言って私に紅茶のマグカップをわたした。その瞬間、やはり不思議なことに、「誰か死んだな」とわかるものなのだった。そして、オットにはあまり体調がいいとはいえない母と、もうひとり下の弟(←アル中)がいるので、妙に冷静に、どっちかだろうと思った。しかしオットの口から出てきた名前は、あまりに思いがけない上の弟の名前(T)だったので、ほんとうに混乱した。え?なんで?
よく考えれば、彼も3年前に心臓発作を起こしてバイパス手術を受けている。だから立派な候補者のひとり(っていっていいのか)として予想にあがってきてもおかしくなかったのだが、その後の経過がとても順調で、ほぼ普段通りの生活に戻っていたものだから、ごっそり頭から抜け落ちていたのだった。2日前には定期検診を受けて、何の異常も見つからなかったらしい。
オットはそのとき義母とスカイプで話をしていて、義母がかかってきた電話をとり、その信じられない知らせを受けて、みるみる大混乱に陥っていくのをパソコン画面のこちら側でなす術もなく見ていたそうである。世界は近くなったように見えて、体がそこにないっていうのはこういうことなんだと思い知ったと言っていた。
そういう私も、実際の距離というものが、こんなにも実感のなさに直結するものだということはついぞ知らなかった。
もしこれが、飛行機で数時間という距離だったら、あるいは地続きであったなら、私たちはすぐさま立ち上がって準備して、翌朝には出発しただろう。そしてこの、今向こうで起こっているおそろしい出来事が本当のことなのだと実感できたことだろう。
でも、私たちは翌日いつものように仕事にでかけ、帰ってきたら向こうに電話して、状況や今後の日取り等を確認する。最初の数日間、ともかく毎日電話するということ以外にできることが何もなかった。向こうでは葬儀は日本みたいにすぐに行なわれるものではないらしく、1週間以上も発ってから葬儀の日が確定し、オットはそれでもとにかく休みをとって4日目には発っていったが、私はといえば葬儀の前々日に出立するまで、じつに宙ぶらりんなまま日々を過ごすことになった。一日のうちに何度もそのことを考えるのだが、だからといって普段通りの生活をしないということは難しかった。正直にいうと、時々忘れそうになってはハッと気が付く、ということの繰り返しだった。
そして19時間かけてイギリスに到着し(高すぎて直行便が買えなかった)、なんとなく頭が興奮状態のまま、家族との再会、涙、Tとの対面、涙、すごい人数の知らない親戚と対面、前夜はほぼホームパーティの様相、喧噪&笑い、葬儀、当然涙、さらに大人数の参列者と対面、という一連の葬儀シリーズに突入していくことになったのだった。
どこの国でも葬式というのはある種の興奮状態にあって、さっきまで泣いていたかと思ったらもうげらげらと笑っていたりと喜怒哀楽が忙しい。私も同じように泣いたり笑ったりしながら、どこか悲しさというのは相対的なものだな、と思っていた。自分が悲しいのか、相手に共鳴して悲しいのかというのはじっさい区別がつけられない。
ここにきてもまだ、現実感がともなわない、どこか俯瞰しているような気持ちでいるのは、別の国で、別の言葉をしゃべっているからなのだろうかと考えていた。そして、頭のどこかに観察する眼があって、こっちでは特別に「喪服」っていうものはないのだな(持っていった喪服を会う人会う人に異常に褒められた、こういう時でも服を褒めるのだな)、とか、葬儀の時には詩を読むのか、そして読まれた詩の一つはあの「千の風になって」ってやつじゃないか、イギリス人的にそれはいいのか、とか、葬儀の最後に音楽と共に祭壇の前のカーテンがするすると閉まって棺が見えなくなるところが文字通り「幕引き」って感じだなあとか、お焼香がないからけっこう式自体はすぐ終わるんだな、とか思っていた。
その後場所を変えて行なわれた会でも、いろんな人が入れ替わり立ち代わりやってきて、それらの人々すべてが私のことをあらかじめ知っている、という現象があった。外国人(東洋人)は私だけだからすぐわかる。どこで何が話されていたというのか。
そして故人とごく親しい家族としてお悔やみを言ってくれるのだが、それにも何やら奇妙な居心地の悪さがあった。私が個人的にTに感じている近しさと好意は、付き合いの長さや密度で計れるものではないけれど、こちらに来るようになってからの12年間で、実際のところ通算何回彼に会ったのだろう、この人のことを本当は何も知らないじゃないと考えてしまう。それに比べればそちらのほうがよっぽどお悔やみ申し上げますじゃないのかね、と思ったりして、なんと説明したらいいのかわからないが、例えていうなら劇場にいて、役を演じているような感じが抜けなかった。
こんな風に観察している自分に気付いては罪悪感を感じ、泣いている時はそれはそれで、「泣くほど彼を知ってたのか」と思う、という2つの感慨が入れ替わりやってきて、そのうちそういうことにも疲れたので、途中からは「茶番こそが人生だ」と思うことにした。
それは、子どもの頃は寄宿舎、19で家を出てから30代半ばまで音信不通というちょっとコメントしづらい前半生を持つオットにとっても同様のようだった。

干潮時の風景、ワイト島
帰ってきてから3週間経って、最近ようやく、「死ぬ」ってことは「その人ともう会わない」し、「もう動いている姿を見ない」ってことなんだなあという当たり前のことが腑に落ちつつある。という話をオットとしたばかりだ。そして、人は時々こうやってかんたんに死んでしまう。
ちょっと前に台湾で、Tへのお土産に包丁を買った。以前行ったときに買ったのがすごくよかったので、Tにも買ってってやろうとオットが言ったのだった。そして、誕生日のときに送ろうともったいぶって取っておいていた。でも、こういうことがあるから、やはり善は急げというのは真理なのであって、ことわざを侮るべきではない。
一方で、その突然の死に方を、うらやましいと思う自分もいる。でもそれは自分が死ぬ側だと仮定しての話であって、オットが「こんなのひどすぎるけど、週末に友人と楽しく過ごして、楽しかったね、また明日ねって言って恋人と同じベッドで寝たまま死ぬなんて、死に方としちゃ最高だよ。」と言ったときには瞬時に「私は残されたくないよ!」と思ったし、同様の話を義母の友人としたところ、彼女も即座に「残されたほうは地獄よ。」と言っていた。彼女は3年前に夫を脳梗塞で亡くしている。そして「男ってなぜか自分が先に死ぬと思っててのんきだよね…。」ということで深く同意したのだった。
その朝、異変に気付いたJが警察を呼んで、やってきた警察官のひとりがまずJに指示したことは、「あんたはまず外に行って、隣の家にかけこんで誰か連れて来なさい。誰でもいい。ともかくひとりでいてはいけない。」だったという。そしてJはそのとおりにした。いかにもイギリスらしい(と言えるほどイギリスをよく知らないが)やりかただと思った。
そのJだが、最近「Honey bunch」は日本語で何て書くの?と不穏な質問をしてきて、もしや…と思ったが案の定「彼のことをいつもそう呼んでたからタトゥーを入れようと思って♡」てなことを言い出した。Jよ、それ、たぶん一時の気の迷いだから。

冗談みたいな森の小道

を抜けるとホビット庄が…(嘘)

ホビット庄の家(嘘)
byはらぷ
※「なんかすごい。」は、毎月第3木曜の更新です。はらぷさんのブログはこちら。
※はらぷさんが、お祖父さんの作ったものをアップするTwitterのアカウントはこちら。











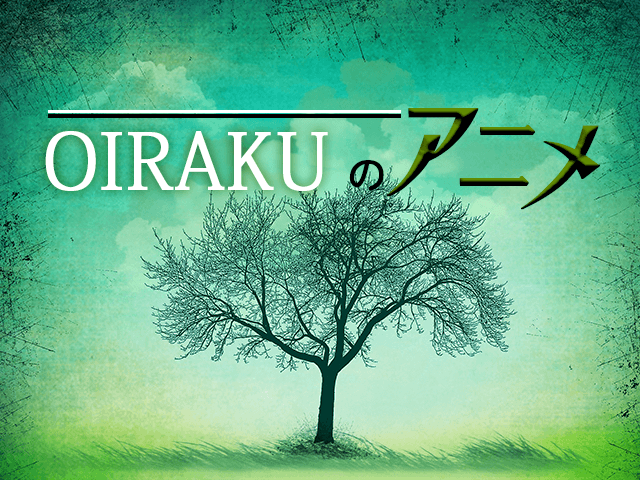



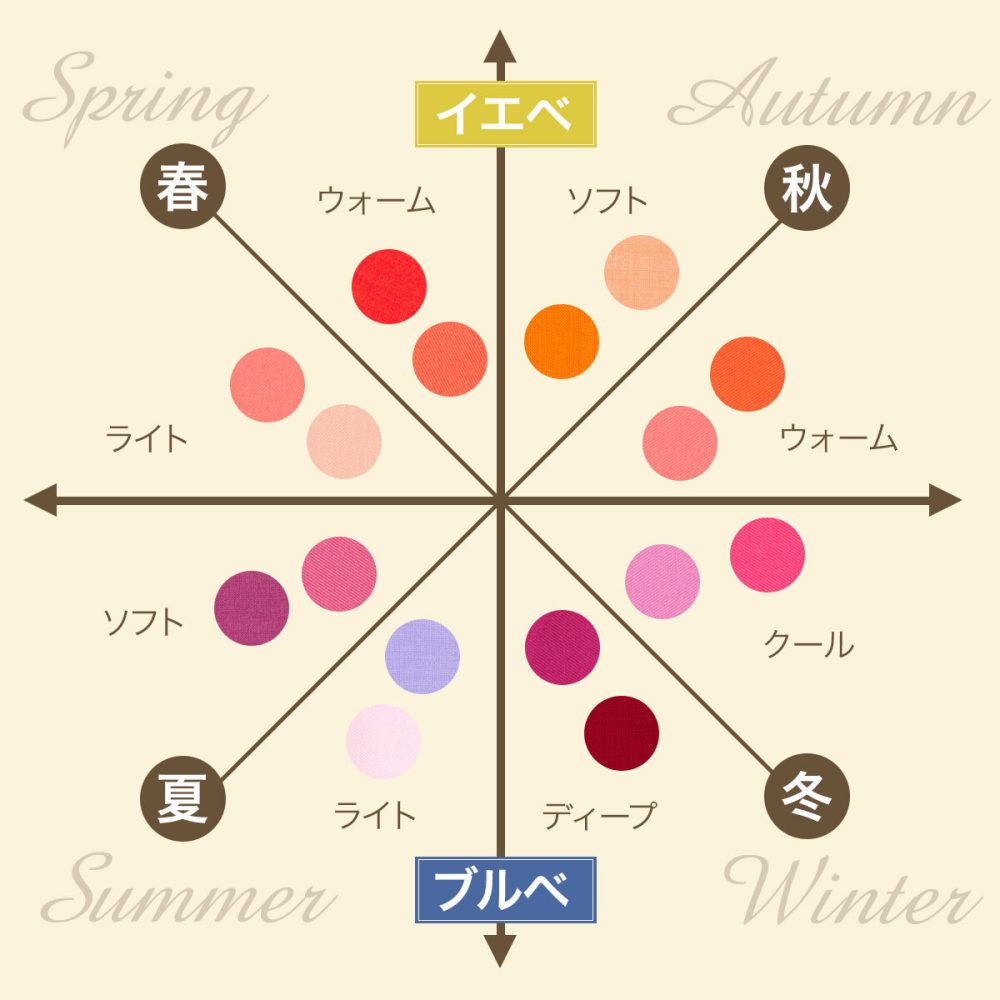
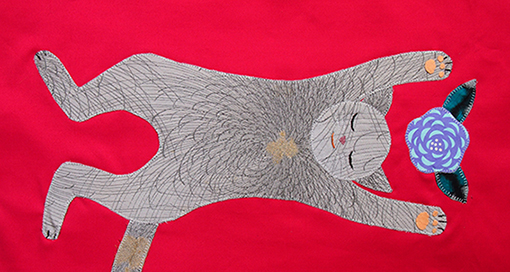





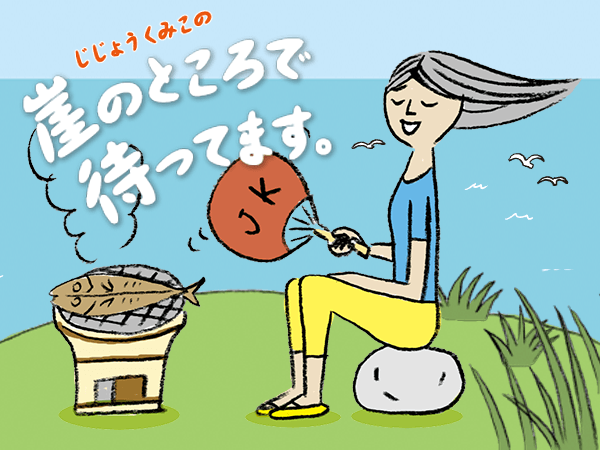
























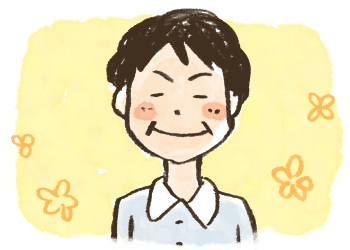
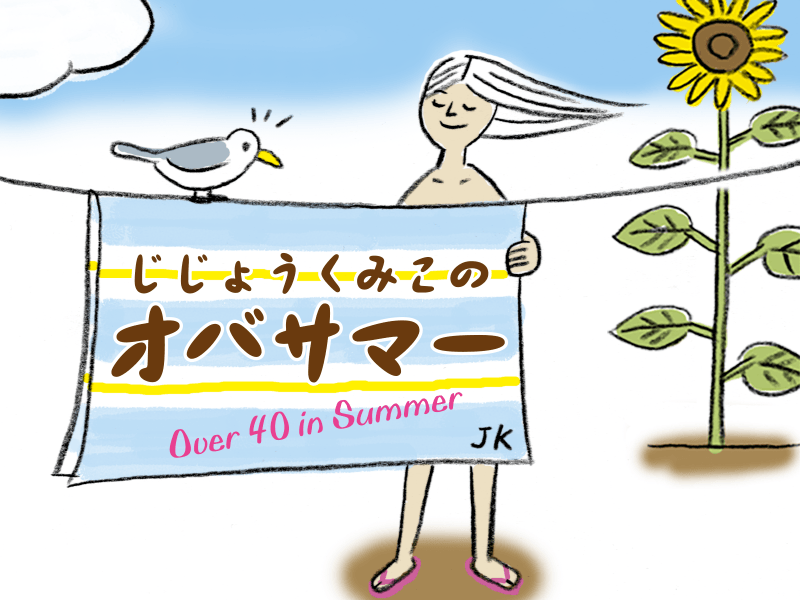























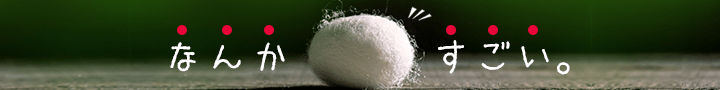











ぽめ
はらぷさんの文章とものの見方が好きです。
読んでいると、須賀敦子の文章を思い出します。
はらぷさんのおじいさまの作品も好きです。
作品集を今までに2冊買いました。1冊目は自分用で、2冊目は、うつ病の家族や介護が必要な家族を抱えて心身共に疲れ切っているであろう、美術作家の親戚に送りました。
はらぷさんは、おじいさまから、とてもよい意味での自意識のなさ、を受け継いだのでしょうね。
そしてそれは、感じたことを感じたままに誰かに伝える上で欠かせない資質、と思います。
次のブログも楽しみにしています。
はらぷ Post author
ぽめさま
こんばんは、はじめまして。
な、何て言ったらいいんでしょう。いただいたコメントが嬉しすぎて、数日お返事が書けませんでした。
須賀敦子、大好きです…。しかし恐れ多すぎて熱が出そうです!
祖父の作品のことも、ありがとうございます。
祖父の人形を見ていると、なんだこれ、かわいい!と身悶えするいっぽうで、そうだ、自由だ、ヤッチマエ!!(何をだ)と突き抜けたような気持ちにもなります。
祖父の作品が、ご親戚のかたに、ほんの一瞬でも日常を離れてわあーッと思える時間を提供することができたら、どんなにかいいだろうな、と心から思います。
そして、そんなふうにさりげなく贈り物ができるぽめさんが素敵です…。きっとご親戚のかたはそのことが一番嬉しいのではないでしょうか。誰かが見ていてくれているということが。
祖父は101歳にしてついに、自意識からの自由を手に入れたように思われます。
私はといえば、とてもその域にはいっていなくて、階段の一段目をあがったり降りたりしている感じです。もしかして、自意識がありすぎて、ありすぎるのでどーんと投げ出してしまえー!、とか思っているのかもしれません。