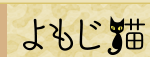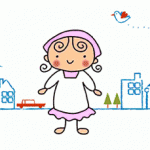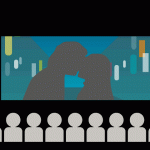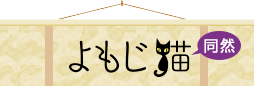Posted on 2017年12月21日 by はらぷ
旅先に持っていく本
19日深夜、この原稿を書いている。この回が公開される21日には、私はイギリスの義母の家にいるだろう。順調に飛行機が飛べば。
去年は、オットの弟が次々に亡くなって、何度も向こうに飛ぶことになった。ひとつ下の弟が5月、一番下の弟が11月の終わり、葬儀があったのが12月中頃だったから、もう一年になるのか。
実質、それ以来はじめてのクリスマスということになる。とうぜん祝祭という雰囲気からはほど遠い。でも、死者の思い出話などしながら、中年と老人の3人で静かにすごすクリスマスというのもいいだろう。(いや、ちょっと嫌かも)
不在がことのほかこたえるのは、家族のなかに子どもや若者がいないせいもある、と思う。誰かが誰かの代わりになれるものではもちろんないし、いなくなった弟ふたりは、去りゆく世代としてはいかにも早いが、それでも、次の世代のものたちがいるところでは、新しい命の輝きが、死者の不在の穴を光で塗りつぶしてくれる。
自分がいなくなっても、まわりの家族や愛するものたちが、その不在の網の目をみるみるうちにうめてしまう、と書いたのは、たしか山田詠美の『晩年の子ども』だった。
ところで、きゅうに現実的なことを言うと、一年になんども飛行機に乗ると金がかかる。
二人分ともなれば、もうたいへんなことである。とくに、数年前にヴァージン・アトランティックが東京—ロンドン便から撤退してしまってからというもの、直行便が高くなった(ような気がする)。そこで、ここ何回かは乗り継ぎ便で行っている。
今回は、羽田から4時間乗って北京、そこで3時間の待ち合わせ。それから11時間乗ってヒースローに着く。所要時間だいたい19時間。
この19時間、何を読んで過ごすか、ということが、出発前夜の現在、もっか私の頭を悩ませているだいもんだいである。(荷造りはどうした。)
前回乗った時は、ミランダ・ジュライの『あなたを選んでくれるもの』(新潮社)を持っていって、とてもよかった。
すべてネットでやりとりが主流の時代に、紙のフリーペーパーに「売ります」広告を出す人々を、著者が訪ねて書いたインタビュー集。彼らが売りたい「何か」から浮かび上がる、どこかいびつな人々の人生の断片。途中でやめて、後からまた開いても、いつでもすっと本の中に戻れて、なにより、偶然乗り合わせただけの人々が肩をならべて、そのくせみんなひとりでいる、にわか運命共同体みたいな飛行機と、この本が内包する孤独はよく似合った。そして、クレストブックスは単行本なのに、とにかく本が軽いところがすばらしい。
長い道中なのだから、このさい読みのがしていたマンガを一気に読む、という手もあって、たとえばこないだのマンガ座談会で話が出た「マカロニほうれん荘」に「イヴの息子たち」に「パートナー」、「エースをねらえ!」。こういうのだったら、どんなに長い移動時間でも退屈しなさそうだ。長いシリーズを一気に読みたい。そうするとやっぱりタブレットはいいな、常夜灯も必要ないし。
でも、マンガの難点は、夢中になりすぎて、しばしば戻ってこられなくなることである。到着したさきで、どんな頭で歩き出すか、ということこそ、旅の本におおいに影響されるところではないか。
そんなわけで、読んだものにすぐに影響されるわかりやすい性格としては、たいてい外国文学から何か選んで持っていくことが多い。家にある、まだ読んでない本の数といったらもう、選びほうだいだ。
今回は、前回も持っていって読まずに持って帰ってきた気がする『灯台守の話』(ジャネット・ウィンターソン著 白水社)と、ちょっと前に買った、まさかの未読『クリスマスのフロスト』(R.D.ウィングフィールド 創元推理文庫)、昔子どものころに読んだ気がするが、最近文庫本を手に入れた『この湖にボート禁止』(ジェフリー・トゥリーズ著 福武書店)を持っていくことにする。
本を選ぶときはいつも、読むものがなくなったらどうしよう…、と心配するのだが、これまでのところまったくの杞憂である。だいたい持っていっても、たいていうとうとしていてろくに読んでやしない!
10年くらい前までは、どこか遠出をするとなると、必ず村上春樹の『遠い太鼓』の文庫版を持っていった。イタリアとギリシャの滞在記で、もうさほど村上春樹を好きでもなくなって久しいけれど、これはずっと好きな本。
須賀敦子や内田洋子の本も、移動にはよく似合う。ぜんぶ、イタリアの話だ。
イタリアには、大学生2年生のときに旅行で、ローマ、フィレンツェ、アッシジ、ミラノと駆け足で数日間滞在したきりだが、陽気で、若い女と見れば自動的に片目はウインクし、口からは賛美の言葉が流れ出す、ミッソーニを着たイタリアおじさん、というのは本当にいるんだ(しかもいたるところに)、さすがイタリアはイメージを裏切らない、と思った。と同時に、石畳の坂道や、黒々と陰を落とす細い路地、バスの窓から見た、オリーブ畑の丘陵と古い領主館、そうした風景から、どんなものも、時の流れにはかなわない、という諦観のようなものがにじみでてくるような気もしたものだった。
日常のすぐ隣に、古代の遺跡がさほど顧みられもせず、ごろごろと転がっているような場所で暮らしていると、そうなってしまうものなのだろうか。
外国に住んで、どれほど土地になじんでも、どこかいつも異邦人の目で物事を見ている。孤独と、その地で出会う、どこかはらはらさせられるような欠陥だらけの、愛すべき人々。
イタリアに限らず、滞在記で好きな本は多い。梨木香歩の『春になったら苺を摘みに』。これは著者がイギリスに留学していたときのはなし。
『犬が星見た』(武田百合子)、『お嬢さん放浪記』(犬飼道子)、石井桃子の見たアメリカ、少女時代をソビエト体制下のチェコで過ごした米原万里の『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』。
一世代前の、女の人が書いたものが多いのは、まだ渡航がよほど気軽でなかった時代に、たったひとり出かけていって、異国で孤独を友に過ごしたまなざしに、惹かれるからだと思う。
彼らをとおして、異邦人の目を手に入れて、これから行く国を眺めようと思っている、ずいぶんロマンチックで、浸り屋だなあと我ながら思う。
そんなことより、荷造りをしろ。
ちょっと気が早いけど、みなさん、どうぞよい年末年始をお過ごしください。
byはらぷ
※「なんかすごい。」は、毎月第3木曜の更新です。はらぷさんのブログはこちら。
※はらぷさんが、お祖父さんの作ったものをアップするTwitterのアカウントはこちら。