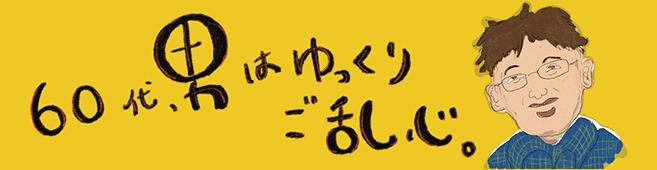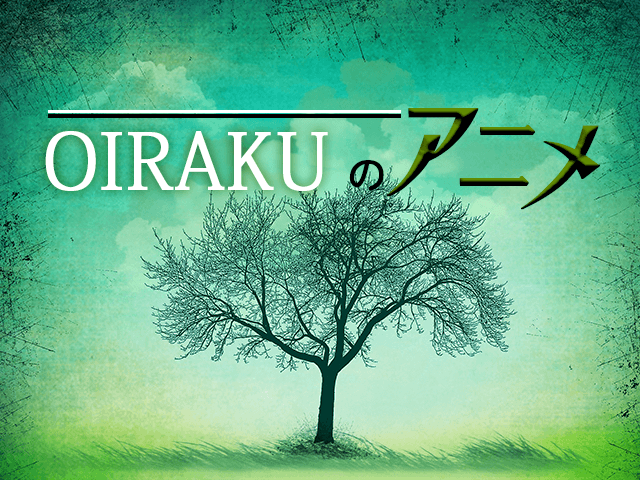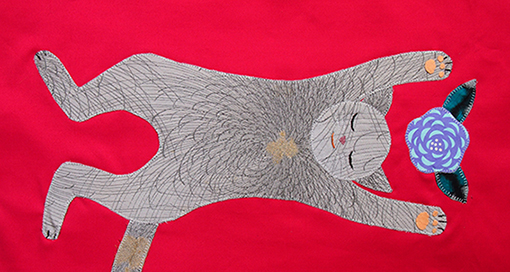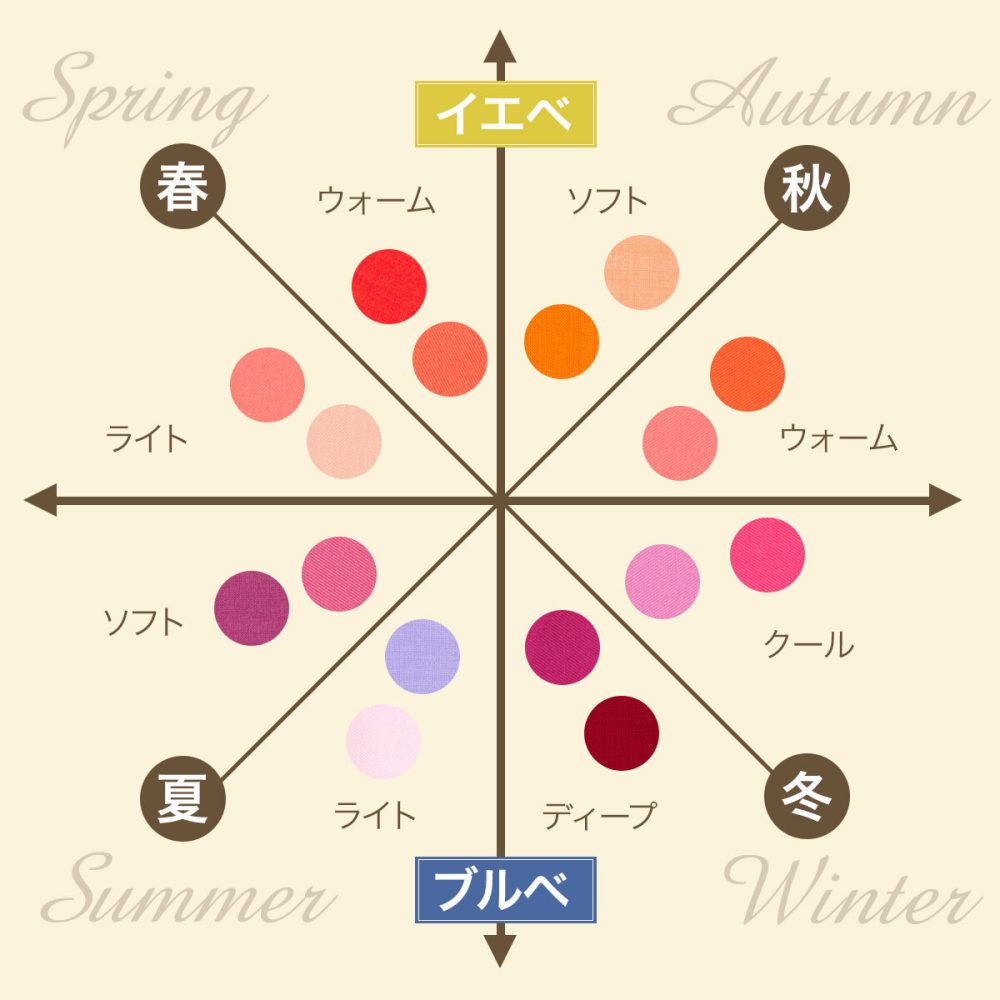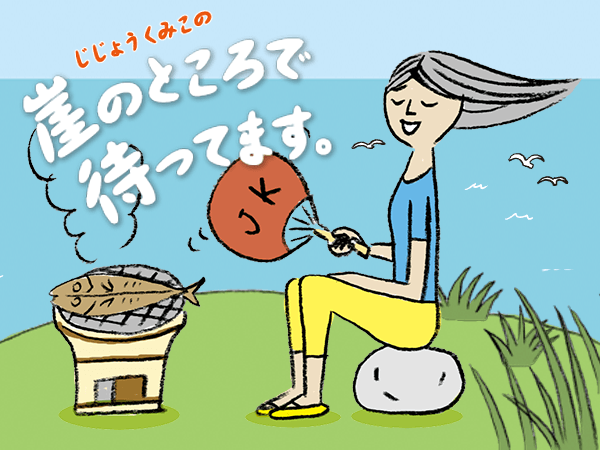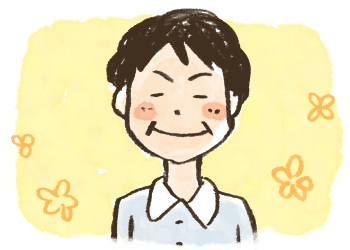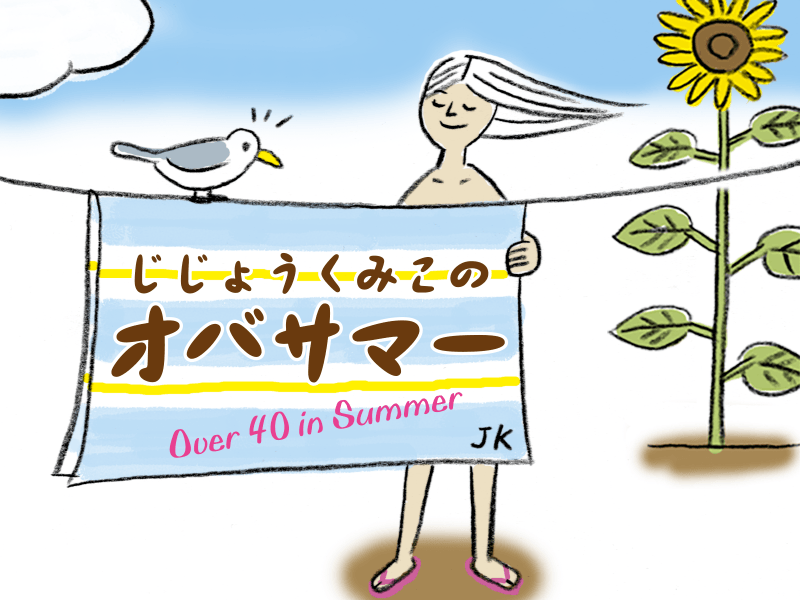藤本義一先生とATGの大人びた幼児性

前回、藤本義一先生の『映像ロマンの旗手たち』という本について書いた。中学生に頃に夢中になって読んだ記憶について書いたのだった。そして、前回の文章の最後に『映像ロマンの旗手たち』を再読してどんな感想を持つのか、次回書きます、と記した。けれど、僕の手元に『映像ロマンの旗手たち』という本は未だにない。Amazonで見つけた古本を注文したのだけれど、なんの手違いか未だに届かない。なので、今回『映像ロマンの旗手たち』については書けないのである。仕方がない。嘘つきなのではない。本当に届かないのだから、本当に仕方がない。
ということで、僕は『映像ロマンの旗手たち』を諦めて、『鬼の詩』という藤本義一先生が直木賞を受賞した小説を読んだ。これはさすがに直木賞を受賞している作品だけあって、電子書籍として発売されていたので、あっという間にダウンロードしてあっという間に読んだ。上方落語、つまり、大阪の落語の世界に実在した落語家をモデルにした小説だった。小説の中の名前は桂馬喬で、実在の落語は桂米喬という人らしい。この桂米喬という実在の落語家が本当に芸に狂った人だったらしい。憧れの師匠が出来ると、その師匠の隣の家に住み、同じものを食べ、同じマッサージ師にかかり、同じ声を出し、同じ間で落語を語る。そんな桂米喬はコレラを乗り越え、関東大震災を乗り越えて、売れないながらも、芸に熱心な狂った落語家としてそれなりに知られていく。しかし、空気も読めない人なので、周囲との軋轢はなかなか激しかったという。
なんでも、あの有名な桂春団治も、この桂米喬を疎ましく思い、憎み、仲間と一緒に寄席から帰る桂米喬を夜討ちしようとしたらしい。すると、相手を間違えて他の落語家を襲おうとしてしまう。これを聞いた桂米喬は春団治を呼び、「お前のしたことは間違ってはおらん。それくらい熱心に芸を磨け。おれはお前を許す」と言われたそうだ。すると、今度は春団治が桂米喬に心酔し、以降、春団治の落語は桂米喬とそっくりな間と声色になったというから、芸の世界というのは本当に恐ろしい。
さて、この『鬼の詩』は映画にもなっている。主演はいまも活躍している若き日の桂福團治と、日活ロマンポルノで活躍した片桐夕子である。そして、監督は村野鐵太郎。制作会社はあのATGなのだ。配信レンタルにこの作品があるというのも、デジタル時代の恩恵だが、見たいなあと思ったその日に僕はこの映画版『鬼の詩』を見たのである。いやもう、すごい。印影の強い絵作り、無表情にも見えるすごみのある演技、誰にも忖度しない濡れ場と暴力。もう、70年代のATGはこうだったと、懐かしい気持ちがいっぱいだった。そして、物語の途中で、主人公の落語家は好きな女と放浪の旅に出て、雪の野原や炎天下の道端で落語をしながら堕ちていく。そこで男と女は「どこまでも一緒に堕ちていこう」と囁きあうのだ。
この「一緒に堕ちていこう」「どこまでも堕ちていこう」という言葉こそがあの頃のATGの本質だったような気がする。世の中が一億中流といわれ、これからバブルがやってくる前夜。何をしても食べていける。飢え死にするやつなんていない。そんな時代だったからこそ、堕ちていくという行為がなんとなく格好良くて、憧れをもって語られていたような気がする。
いまは、もうみんながいつ堕ちてもおかしくない時代だ。しかも、昨日まで信用していた友人や知人に掌を返したように裏切られることだってあるし、なんなから国が自分たちを追い詰めてくるかもしれない。もしかしたら、70年代のおどろおどろしい雰囲気を漂わせたATG映画は、あの頃、大人びて見えた物の正体が、実はものすごく子どもっぽいものだったことをいま証しているのかもしれない。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。