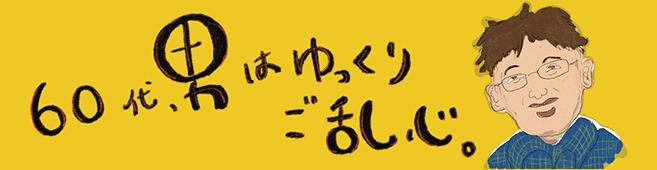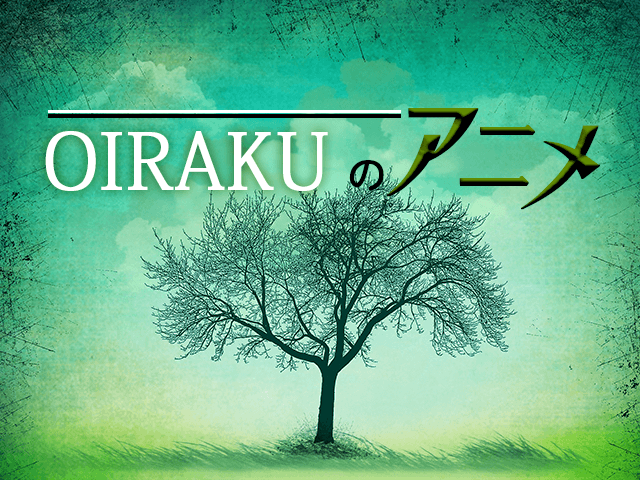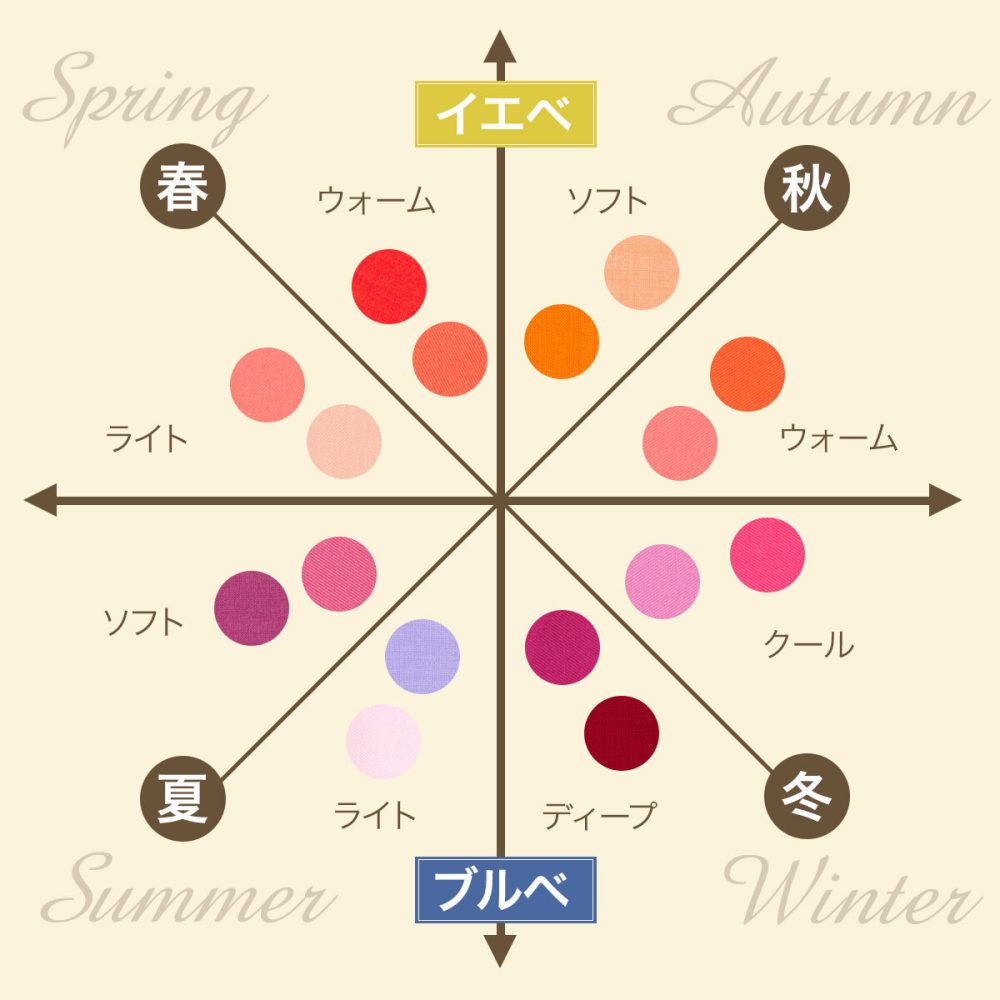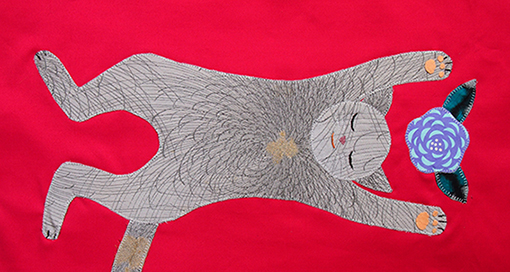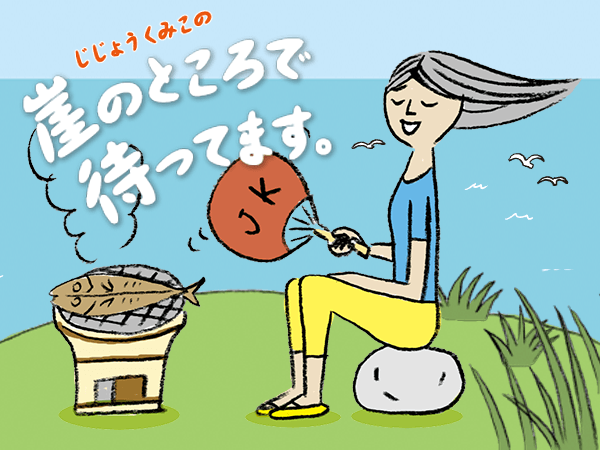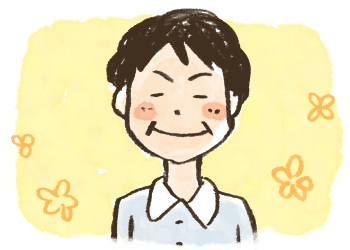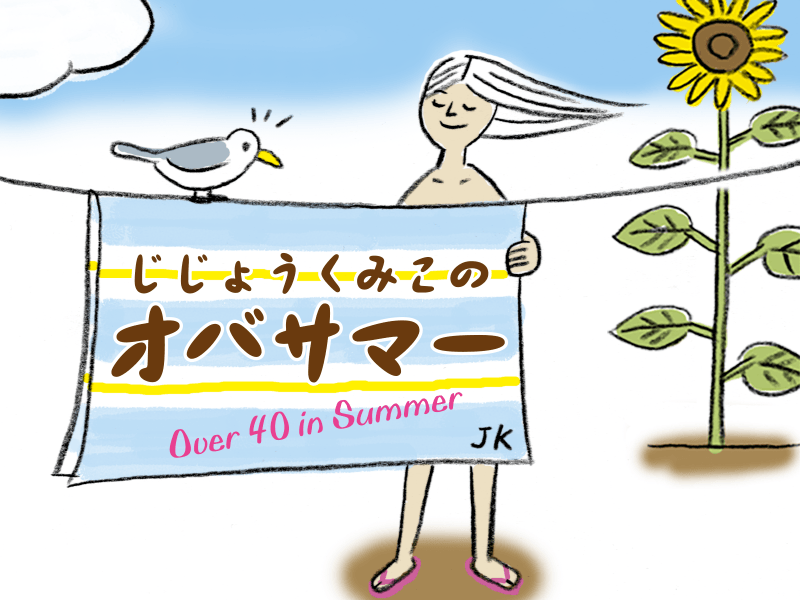母より、と書かれた手紙。
ひとり暮らしをし始めたのは、専門学校を卒業した年だったと思う。20歳になってすぐに、「友だちと小さな事務所を借りて仕事をする」と嘘をついて、父親に保証人の欄に名前を書かせて、判子を押させた。
専門学校を卒業しても正式な就職先を探せずに、フリーの助監督や撮影助手のアルバイトなんかをやっていた。まあ、その事務所兼住居というのは間違いではなかったのだが…う〜ん、まあ事務所ではないかな。
ひとり暮らしを始めてからは毎日が楽しくて仕方がなく、実家まで1時間もかからない距離に住んでいるのに、ほとんど帰らなくなった。盆と正月くらいに思い出したように顔を出しても、寝泊まりすることはなく帰ってしまう。そして、仕事にあぶれ食糧に困ると、実家に忍び込んでインスタントラーメンなどを勝手に持ち帰っていた。もっとも、それも、明らかに僕に持ち帰らせる用の段ボールが用意され始めてからは、やらなくなった。
特に最初の1年くらいは、なぜか絶対に帰らないぞ、という心に決めていた。当時は携帯もなかったので、固定電話も家にいなければ出ないので、ほとんど音信不通という感じだったと思う。そんなある日、一通の手紙が届いた。宛名は僕の名前で、差出人は母の名前だった。
お元気ですか。
寒い日が続きますが、風邪など引いていませんか。
救急車が走るたびに、もしかしたらと心配しています。
気が向いたら顔を見せに帰ってきてください。母より
とまあ、こんな感じの内容だった。いやもう、僕はどうしていいのやら。だって、うちの母親はそんな手紙を書くようなタイプじゃないし、誰がどう見たってその手紙の文字は父親の文字だったからだ。なんだか、恥ずかしいやら腹が立やら。まあ、これが友だちの話なら「お前もたまには実家に顔出してやれよ」くらいは言うと思うのだが、自分のことになると、冷静でいることができず、その手紙は丸めて捨ててしまった。そうやって、見なかったことにしないとやるせない気持ちになってしまうのだった。
この話をすると、「もしかしたら、お母さんが心配して、お父さんに書いてもらったんじゃないの」という人が何人かいたのだが、それは違う。うちは母が子どもに無関心で、父がまるで母親のようにかまいたがりの家だったのでよくわかる。父が心配し、しかも自分の名前じゃ読まないかもしれないと考え、半分おどけた顔をしながら手紙を書く様子が目に浮かぶ。だから、息子としては「気持ち悪いよ」という気持ちと「恥ずかしいよ」という気持ちがない交ぜになって手紙を捨てさせたのだ。
あれから40年以上が経って、母のふりをして手紙を書いた父も亡くなり、絶対にあんな手紙を書くことのない母は元気でピンピンしている。いまだにいろんな出来事に振り回される息子ではあるが、最近は、「オヤジがあの世で見守ってくれているのかもなあ」という気持ちになることがある。そんな気持ちで、仏間に飾られた、なんだか笑顔の父の遺影を見ると、「見守ってはいるんやけども、なんかそんなに力がなくて、いろいろお前のところに行ってしまうんよ」と笑いながら謝られているような気分になる。そして、いまならあの手紙を笑いながら読んで、本の間にでも挟んでおいたのになあ、と思うのである。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。