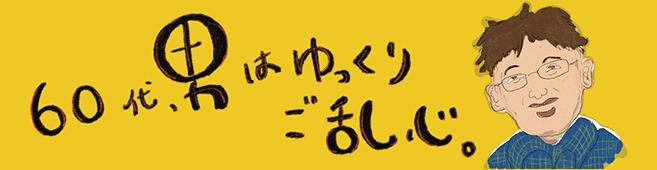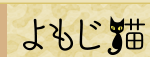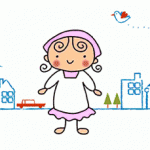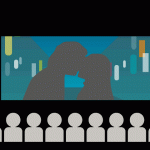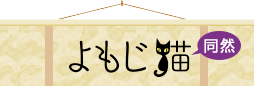Posted on 2024年2月28日 by uematsu
あの煙草屋のシベリア帰りのお爺さんの絶望

子どもの頃、父親からおつかいを頼まれることが多かった。ほとんどが煙草だった。近所の煙草屋へ煙草を買いに行くのだ。父が呑んでいた煙草の銘柄が「わかば」だったので、ほとんどの自動販売機にはなかったからだ。なぜなかったのかと言えば、「わかば」がそれほど美味くはなく安いだけが取り柄の銘柄だったからだ。実際、父以外に「わかば」を呑んでいる人を僕は見たことがなかった。
当時住んでいた家からいちばん近い煙草屋は歩いて5分ほどのところにあった。大きな車は通れない狭い生活道路が交差する場所の角に、いかにも煙草屋らしい風情でその店はあった。「TABACCO」と赤いゴシック体で書かれた看板があり、自動販売機も横に置いてあった。カートン買いする客以外はほとんど自動販売機で買うので、ガラス戸を開けて店の中に声をかける人は少ない。僕はガラス戸の向こうにいるお爺さんが苦手だった。痩せた白髪頭のお爺さんは、いつ行っても小さなちゃぶ台に湯呑みを置いて、新聞を読んでいた。そして、僕がガラス戸を開けて、「わかばください」というと、「あんたが吸うんとちゃうやろな」と返すのである。高校生くらいならともかく、小学校の2年3年が吸わないだろうと思うのだが、毎回、そう聞かれる。時々、世間話のように「今日は暑いなあ」とか「ちゃんと勉強してるか」とか聞くようになってからも「あんたが吸うんとちゃうやろな」と挨拶のように言われるのが、なんとなく苦手だった。その度に僕は「僕とちゃう。父が吸います」と生真面目に答えていたのだった。
そんな煙草屋のお爺さんが戦争中、シベリアに抑留されていたのだという話を聞いたのが誰からだったのかは思い出せない。お爺さんから直接聞いたのか、父から聞いたのか、そのあたりでよく買い物をしていた母から聞いたのか、今となっては思い出せないのだが、いつの間にかそのお爺さんがシベリア帰りだということを僕は知っていた。そして、そのことを自分からお爺さんに話すこともなく、お爺さんが僕に話すこともなく、ただ、煙草を買いに行くたびに「このお爺さんはシベリアという極感の地で囚われていたのだ」と思いながら、いつもの「あんたが吸うんとちゃうやろな」という言葉を聞き、お金を渡し、わかばをもらい、帰るのである。
中学生になり、高校生になり、父親が僕に煙草を頼むこともなくなり、気付いたときには煙草屋のシャッターは開けられることがなくなった。そして、しばらくするとシャッターの前に二台目の自動販売機が置かれた。それは、もう二度と煙草屋のシャッターが開けられることはないということが宣言されているようで、きっとお爺さんはシャッターの向こうにもいないのだろうと僕は思った。
なぜ、こんなことを思い出したのか。たぶん、言葉にしなければわからないことだらけだ、とここしばらく思っているからだろう。言いたいことがたくさんある、というのではなく、言ったところでちゃんと伝わらないのなら黙っていたって一緒だ、と思うことが増えてきた。けれど、だからと言って黙っていると、あのお爺さんがどんな人だったのか、ということは僕にはなにもわからないままだった。言うべきことがある人が黙っていて、声が大きければくだらないことでも世間に拡大されていく。そんな世の中に僕は絶望している。そして、あのお爺さんにそんな話をしてみたい。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。