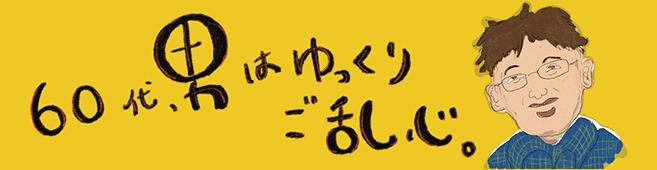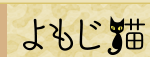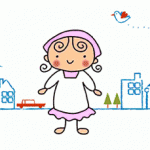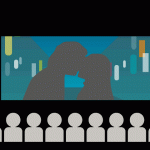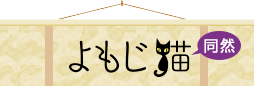Posted on 2024年11月13日 by uematsu
父とのキャッチボール
野球が苦手だった。
子どものころ、近所の悪ガキたちと一緒に三角ベースの野球をして、楽しかった思い出がない。みんながそれぞれに自分に有利なルールを主張し、年かさの子が年下の子を押しのけて得点して喜んでいるような野球だったので、面白いと思うどころか、野球なんて大嫌いだと思う時間だった。でも、テレビゲームもなければ、一人で家に閉じこもれるほど孤独に強いわけでもなく、仕方なく毎日近所の草っ原に出かけては、自然に集まってくる近所もガキどもと、面白くもない三角ベース的な野球に興じていた。
こんな子ども時代の思い出があるからだろう。僕は大きくなっても野球に関心を持つことがなかった。テレビ中継も見ないし、毎週買っているコミック雑誌でも野球マンガは読まない。昔の『巨人の星』や『侍ジャイアンツ』みたいな根性ものとかコメディものなら読むけれど、真面目に野球の面白さを伝えようとするタイトルは、最後まで読んだことがない。
しかし、だからと言って野球が嫌いなわけではない。野球に対しての憧れのようなものがずっとある。映画『フィールド・オブ・ドリーム』の原作にもなったWPキンセラの小説『シューレス・ジョー』みたいな話には素直に憧れがある。あの小説は主人公がトウモロコシ畑を歩いていると、空から声が聞こえてくる。「それを作れば彼が来る」と。その声に導かれて、主人公は畑を切り拓いて、野球場をつくる。すると、往年のメジャーリーグの選手の幽霊が次々と現れ試合を始めるのだ。その試合を見ようと多くの見物人も集まってくる。なかには、八百長事件に巻き込まれ、子どものファンに「嘘だと言ってよ、ジョー」と声をかけられたというシューレス・ジョーが現れ、主人公がつくった野球場の興奮は最高潮に達する。
ここまで読み進めてくると、「それを作れば彼が来る」と言ったのは、シューレス・ジョーのことだったのかと思う。けれど、本当は違うのだ。この後に、主人公の亡くなった父が現れる。そして、二人は黙ってキャッチボールを始めるのだ。彼とは父のことだった。僕はこの小説を読みながら、父とキャッチボールをした日のことを思い出した。
僕が小学校の1年生か2年生だったと思う。父が僕と弟が三角ベース野球で使っていた玩具のようなグローブと軟式のボールを持って、「キャッチボールするぞ」と言った。父とキャッチボールなどしたことがなかったので、驚いた。本気かどうかわからなかったので、しばらく黙っていた。すると、短気な父は「はやくしろ」と少し苛立った声で言ったので、僕はあわてて父について家を出た。
近所の空き地で僕と父はぎこちなく距離をとり、まず父が僕に向かってボールを投げた。父のボールは大きく逸れて、僕の遙か後ろに消えていった。僕はそれを拾い、今度は僕が投げた。父は「さあ、こい」と笑うと、グローブを高く上げた。僕はそのグローブに向かってボールを投げた。父よりはマシだったけれど、ボールは父を越えて言った。父は、「ちゃんと投げろ」と言うと、ボールを探しに行った。それから、僕と父はたがいに下手なフォームで、あちらこちらにボールを飛ばし、最後にはボールが草むらに消えたまま見つからなくなった。それまでの時間はたぶん10分もかからなかったと思う。父はなんだか不機嫌になり、そのまま僕と父の初めてのキャッチボールは終わった。もちろん、それ以降、二度目のキャッチボールをすることもなかった。
おそらく、父も憧れていたのだと思う。休日にキャッチボールをするような父と息子というものに憧れに似た思いを持っていたのだろう。けれど、もともと野球にあまり興味のなかった父にとって、キャッチボールはハードルが高かったのだと思う。それ以来、父が僕にキャッチボールをしようということもなかったし、他のスポーツに誘われたこともなかった。
いま思うと、父は不器用な人だった。父親という役割に向いている人でもなかったし、僕自身も父親に懐いてついていくタイプでもなかった。そんなことを思い出したのは、自分自身が息子を持ち、小学校に上がったころに二人でキャッチボールをしたときだった。息子が欲しがった玩具のグローブとボールを買ってやったときに、「公園でキャッチボールをしよう」と僕は声をかけた。喜んでついてきた息子だったが、僕は僕の父と同じように野球が下手だった。そして、息子は子どもの頃の僕よりもキャッチボールがうまかった。息子が投げる。私がとる。私が投げる。息子にとれないところに暴投する。その繰り返しで、息子のほうが音を上げてしまった。
僕と父がたった一度しかキャッチボールをしなかったように、僕と息子もあの時の一度しかキャッチボールをしたことがない。父は亡くなってしまったが、僕と息子はまだ元気だ。いつかまた、どこかで息子とキャッチボールをする機会はあるだろうか。それはたぶん、僕が声をかけるかどうかだろう。だとしたら、まだ僕が元気なうちに一度でいいから、キャッチボールに誘ってみようと思う。きっと、父はものすごく羨ましがることだと思う。
植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。
植松事務所
植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。