Posted on 2020年1月14日 by ミカス
失われる「確かさ」: ごぼうと鶏ひき肉の中華炒め
身内に認知症の人がいる方は『長谷川式』という言葉に聞き覚えがあることと思います。
『長谷川式』は、認知症の早期診断の検査指標で、認知症治療の第一人者である長谷川和夫さんによって開発されました。
その長谷川さんが認知症になりました。
そして、1年に渡ってその様子を取材した「NHKスペシャル 認知症の第一人者が認知症になった」が先日放送されました。
長谷川さんが認知症への理解を深めるきっかけとなったとある患者さんがいます。50代でアルツハイマー病を発症したその患者さんは、亡くなるまでその胸の内を明かすことはありませんでした。しかし、亡くなった後、「僕の心の高鳴りはどこへ行ってしまったんだろうか」と悲痛な叫びが書き留められた五線紙が見つかったのだそうです。それを知った時、長谷川さんは、「絶対に認知症に対する研究・診療は何が何でも続けるぞ」と心に決めたといいます。
ふと、母のことを思い出しました。
初めて介護認定を受ける際、介護認定と言うと必ず怒り出すであろうと思われたので、私は「役所から高齢者の健康について調査をする人が来るよ」と母に伝えました。それでも「来られては困る。断ってくれ」と言う母をなだめすかして、なんとか訪問調査を終えたのですが、その後、母の鞄から一枚の紙きれが出てきました。そこにはこう書かれていました。
「舅も姑も、認知症で大変でした。自分もそうなるのではないかと不安です」
心臓を鷲掴みにされたような気持になりました。
調査担当の人に伝えたいことを忘れてしまわないように、母はそれを書いたのだと思います。それでも調査当日には、母は、その紙きれの存在すらすっかり忘れていました。
私はいまだにその紙を捨てることができません。でも、いまだにその紙に書かれた言葉を周りの誰にも言うことができずにいます。
また、日に日に口数が少なくなっていく長谷川さんは、こんなことを口にします。
「(自分が)何回も念を押して聞くから、(周りが)鬱陶しくなって…。今、こういうことを言っていいのか、言わない方がいいのか、自信がなくなる。だから寡黙にならざるを得ない」
ああ、母も言っていたっけ。妹と3人で喋っていた時、しばらく黙って頷いていたたけれど「私、わかっているふりをしているのよ。本当はわからないから聞きたいのだけど」
母のそんな切ない気持ちを知ったなら、もう少し優しく、もう少し穏やかに、自宅での介護を続けられたのではないかと考えてみるのですが、すぐに、それとこれとは別の問題だと気持ちを引き戻します。
認知症の症状が進んでいく自分に得も言われぬ不安を感じる母の恐怖に思いを馳せたところで、罵詈雑言を浴びせられたり、掴みかかられたりという母の不穏に毎日付き合うことは、やはり私には出来ないのです。
長谷川さんは、認知症になったことで「生きていくうえでの『確かさ』が少なくなってきた」と言います。『確かさ』が日々失われていくのだと。
認知症という病気は、なんと残酷なものなのでしょう。
でも、他者とつながることで、その『確かさ』を少しでも取り戻すことができるとも言います。
だとしたら、家族のみならず、社会が認知症の人への理解、興味を深めることでその残酷さを少し和らげることができるのかもしれません。
認知症の早期診断を可能にしてくれる『長谷川式』。
昨年末、父が『長谷川式』検査を受け、アルツハイマー型認知症と診断されました。
また、始まります。
でも、早期診断ができたことで出来ることも多くあるはず。
また、始めます。
さて、今日の一品は『ごぼうと鶏ひき肉の中華炒め』です。
ごぼうは太めに切って、敢えてよく噛まないといけないように。よく噛むことで、脳を活性化させましょう。
ごぼうと鶏ひき肉の中華炒め

- 包丁の背でごぼうの皮をこそげ落とし、厚さ1.5センチくらいの斜め切りにします。
- 1のごぼうを水にさらします。あまり長い時間さらしてしまうと風味が抜けてしまうので、私は2~3分ほどで水から上げます。
ペーパータオルなどで水気をふき取り、片栗粉を軽くまぶしておきましょう。 - 深めのフライパンでやや多めの油を熱し、鶏ひき肉を炒めます。
- ひき肉の色が変わったら、フライパンの片方に寄せてスペースを作り、そこへ2のごぼうを入れて焼きます。
- ごぼうの周りが焼けたら 酒、老油醤、醤油、砂糖少々を加えて ひき肉と混ぜ合わせ、蓋をします。
老油醤がない場合は(大抵のお宅にはないと思います)、XO醤、甜麺醤などでもOK。 - ごぼうがお好みの固さに仕上がったら、ごま油を少々加えてさっと混ぜて出来上がりです。
両親ともに認知症の診断を受けたことで、最近、自分が認知症になることへの恐怖を感じるようになってきました。
緑茶を飲んだり、亜麻仁油を摂ってみたり、効果があるのかないのかわからないけれどとりあえずやっています。
気休めだけどね。
ミカスでした。



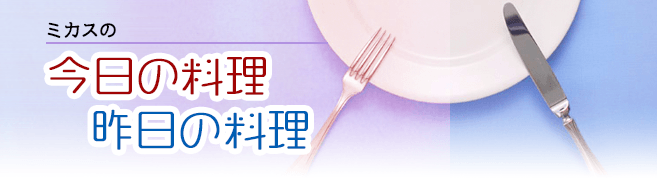






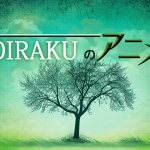

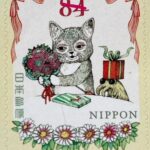





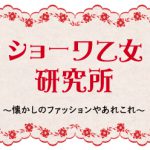


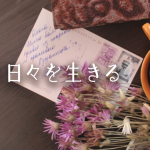

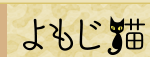

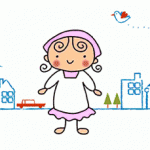

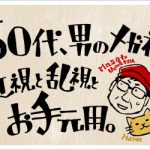









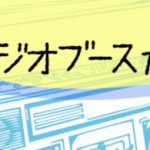








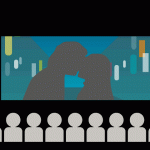
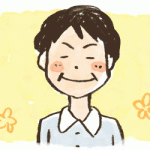



















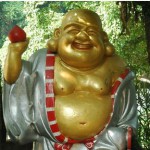




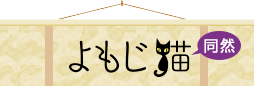




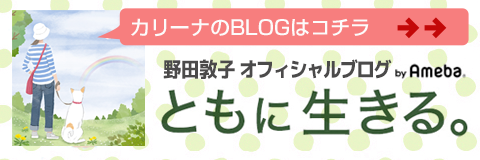
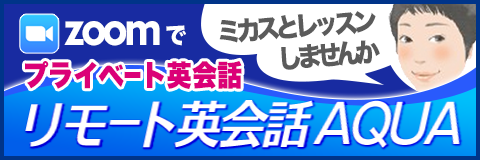
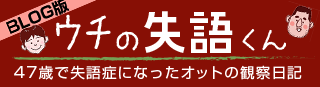
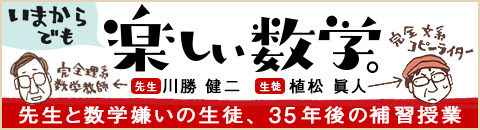

都忘れ
ミカス様。テレビ、観ました~。
こういう番組は、気持ちが沈みがちになるので、用事もないのにバタバタしながら観ていました。
認知症の患者さんは、いろんな不安から怒りっぽくなると聞きますが、病気のことを知り尽くしている長谷川さんの心の中は、いつも嵐が吹き荒れているのだろうか…と思ったりしました。
私がすごいな~と思ったのは、奥さんの明るさです。
テレビカメラが入っていることもあるとは思うけど、あの明るさは、たぶん普段からのものじゃないだろうかと。
いつも身だしなみもきれいにされていて、ご自身も腰を丸めながらの介護は大変だと思いますが、あの笑い声に救われた気がしました。
ミカスさんが、もしも認知症を発症することがあるとしても、どんどん医療が進んでいくから、大丈夫、大丈夫。
予防も治療も出来るんじゃないかな…と。これという根拠はないけど、意外と大丈夫なものです。
いつも目のごちそう、ありがとうございます♪
ミカス Post author
都忘れさん
最もどろどろとした部分は放送されなかったのかもしれませんが、
それにしても、奥さまも娘さんも穏やかな介護をされていましたね。
おそらくは、長谷川さんご本人も含め、ご家族全体が(長谷川さんが認知症を発症する前も)
穏やかに生活をされてきたことの結果なのだろうと私は思いました。
とはいえ、やはり苦悩や苛立ちはそれなりにあるのでしょうけど。
もし、認知症の予防や治療が可能になるのなら、あと数年のうちにそうなってもらいたいものだと思います。
私もいつ認知症を発症してもおかしくはない年齢なので。
祈ります! 頼むぞ、医療!!
Jane
今夜は鶏肉の代わりに使いかけの牛ひき肉パック半分で、ゴボウ炒めとキャベ丼とふろふき大根の肉味噌かけをつくりました。キャベ丼シンプルでヘルシーでお安くしかも美味しいですね。今週はあとおくらと鳥肉の梅干し和えとかじきのネギだれかけもつくりますわ、ミカスさんのレシピで!家庭料理万歳!
えー、ここからは当事者の事情を知らない他人の勝手な戯言と流して聞いていただきたいのですが、正月の一族郎党の集まりといい、介護といい、お料理おもてなし上手とは言え、ミカスさん一人で頑張りすぎていませんか?
そしてミカスさんはお料理もプロ級、英語もお出来になる。もしかして、たとえば外国人付きの家事介護ヘルパーとしてお仕事されてそのお金でミカスさんのご家族をほかの方に見ていただく、というような労働の交換はできないでしょうか?ミカスさんはカナダでそういうような研修を受けられていたと思うのですが。
まったく無責任な発言で、無理!かもしれないのですが、とりあえず、思い付きをコメントさせていただくことをお許しください。
マリオン
私も観ました。
一年前義母が長谷川式のテストを受けた時、横で聞いていて、こんな質問をお医者さんに聞かれたら緊張して私も答えられないわ!かわいそうやわ!って、涙こらえてました。今思うとピント外れです。
このおじいちゃんが考えたんだ!家族のためにデーケアも考えてくれたんだ!テレビの中の長谷川さんに感謝しました。
長谷川さんが先輩に「君自身が認知症になって初めて君の研究は完成する」と言われたと。認知症と診断できても、わからないのはその心です。それが難儀です。心を理解できた時を完成とするなら、永遠に完成なんかないと思います。
ミカスさん
私も怖いですよ。でも、その恐怖は、心豊かに生きる原動力になるかも。今日食べた美味しいもの、窓から見える景色、空気の冷たさ…日々の暮らしの中で思う存分感じたいです。
ミカス Post author
Janeさん
ああ、Janeさん、そんなお仕事があって、状況が許すならやりたいです。
でも不思議なものですよね。親の介護でひーひー言っている私が、介護を仕事にしてみたいなんて。
もちろん、家族の介護と他人の介護、無報酬と報酬ありでは全く違うということはわかっていますが、
それでも不思議なものだよなぁ、と。
とはいえ、料理はまだまだ素人です。
なのに、ミカ料レシピを色々と役立ててくださってありがたい。うれしいです。
料理ももっと修行せねば。
ミカス Post author
マリオンさん
私もね、長谷川式で高得点を取る自信がないのですよ。
マリオンさんがおっしゃるように、お医者さんの前で緊張してしまって、とんでもないことを言ってしまいそうです。
家族の休息のためにデイケアを作ってくれた長谷川さんが、娘さんに「お母さんのため」と言われても
もうデイケアには行かない、という場面に考えさせられました。
「あそこ(デイケア)で私は孤独です」という言葉が胸に刺さりました。
「心を理解できた時が完成」なら、確かに永遠に完成などないですよね。
認知症への恐怖が、心豊かに生きるための原動力か…
感じる力が弱くなっていく前に、色々な事物に触れて、楽しんで、吸収していきたいですね。