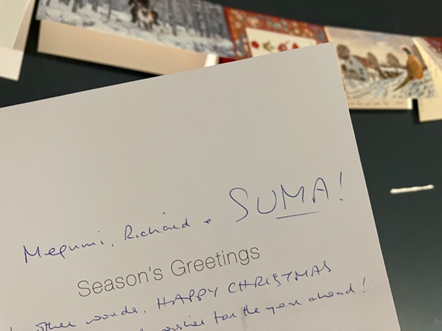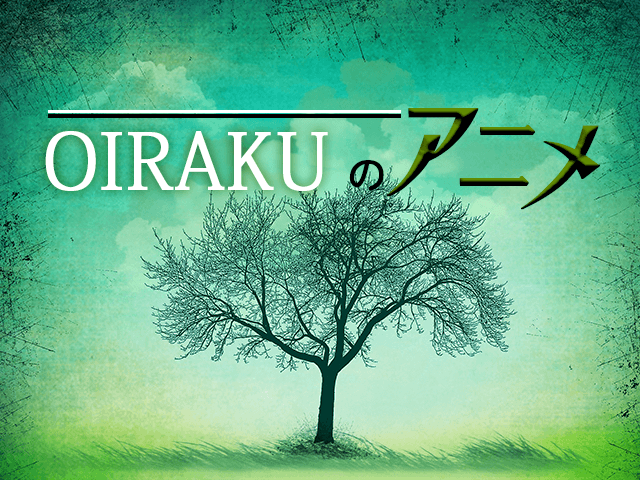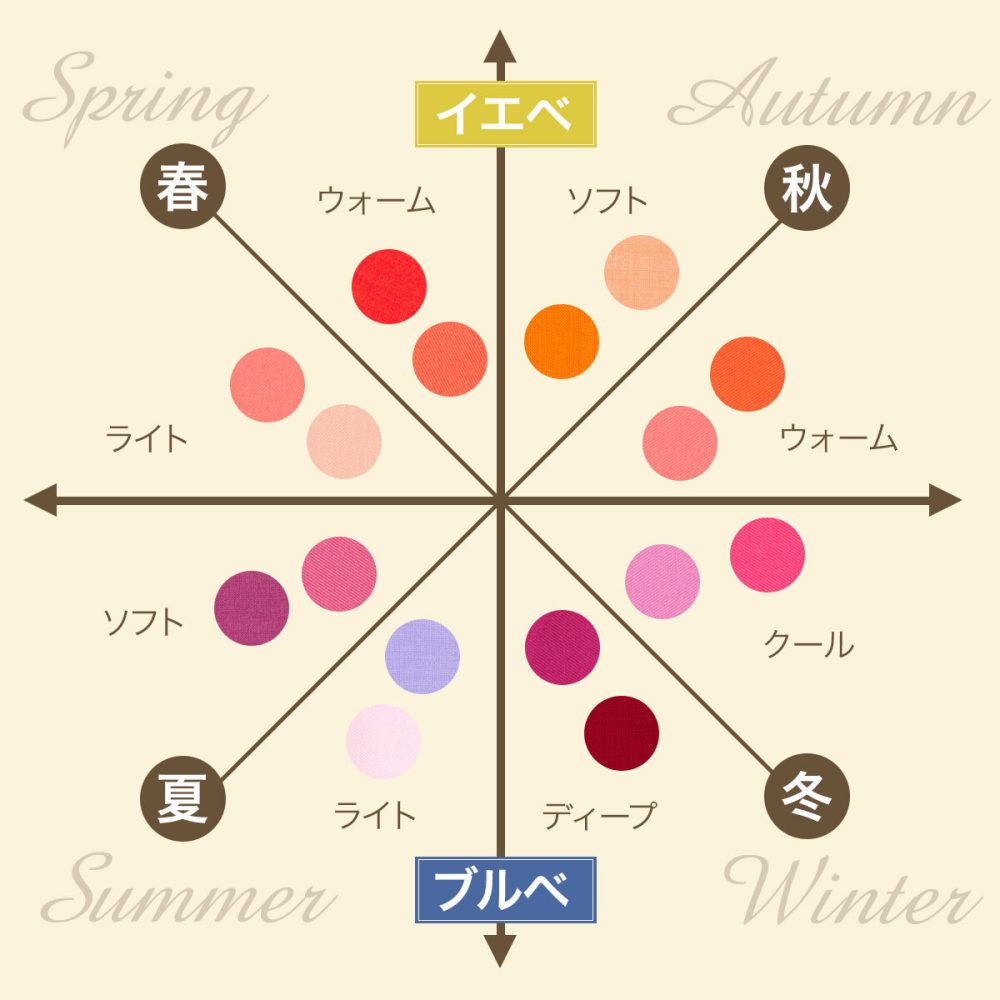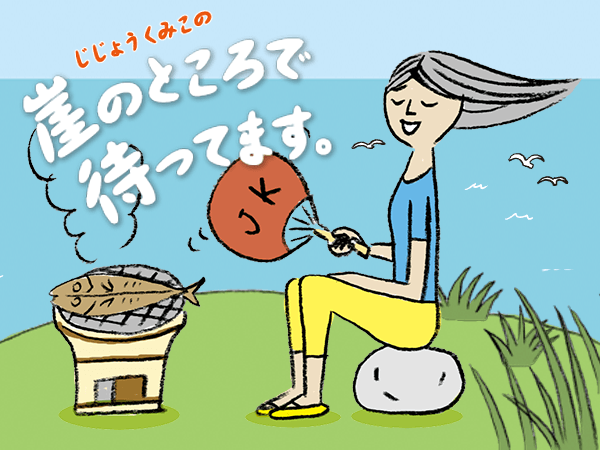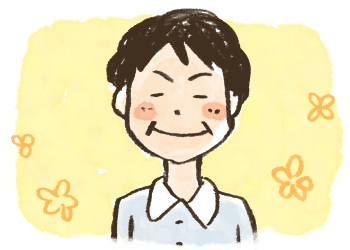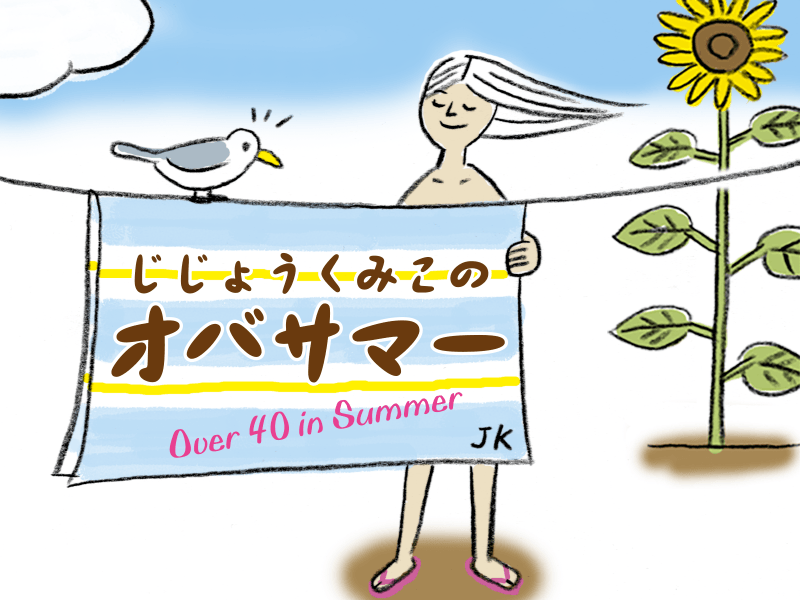◆◇やっかみかもしれませんが…◆◇ 第37回 VIVA!図書部
長嶋有さんは、とりたててファンではないけれど(わざわざ言うな)、たまにその世界に触れたくなる小説家で、『猛スピードで母は』 『問いのない答え』 『三の隣は五号室』 『もう生まれたくない』などは読んでいる。スポットライトを当てる箇所や心理が独創的で、そう来たか、そこ行くか、という、予定調和感皆無の心地よい衝撃がある。これって、大好きな津村記久子さんに通じるかもしれない。
あれ?だったらなんで、津村記久子の小説は大好きで、長嶋有はそうでもないんだろう。…ま、いいや。とにかく、自分にとって彼の小説は長らくそんなポジションだったのである。
で、『ぼくは落ち着きがない』である。これ、すごく良かった。心が震えた。
とはいえ、やっぱりそこは長嶋作品なので、ちゃんと風変わりだし、ちゃんと、これといった結論は出ない。なので、ちゃんと万人向けではない。ゆえに全方面にお薦めはしない。この本を取り上げるのが、本にまつわる記事の【切実★本屋】ではなく、この【やっかみかもしれませんが…】の方ということでも「特に薦めませんよ」というわたしの気持ちが漏れ出ているというものである。勝手にしろ、だろうが。
![フリー素材 背景 学校図書室 [2] | Cenário anime, Fundo de animação ...](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG6CX7bFaQ6O-4GUHsIE4EGxa0jUpFIlumLIIgtXzQfANvfkPmLs0sVANbX6XznIKe5Ng2OIUQXZ_pCw7VvDwCwXny4r0lhGMw3F-BrNNjhug7M8wm2RDU82vmIFN1Pv4RSIgs11V4JDf6xUdnzq-GHya4dy2uJbhP7v-E38_AKqCXROwvYb2-1N1tgLn9hwbYyj3ll6a4qYOdm41gJjwg077KYY51HA93grtOMw3sDF_hCMMART10XB2GlT736NDkA==/5881163f4fb783634fd0d323d7678852.jpg?errorImage=false)
舞台は、高校の図書室である。語り手は、図書部の三年生の望美(のぞみ)。クラスごとに指名される図書「委員」とは別に、自然発生的に生まれたのが図書「部」なのである。
部室は、図書室の一部をベニヤ板で仕切った変則的なスペースで、ベニヤなので寄りかかり厳禁。ちょうどその仕切りの上には照明があるという(ふつう、照明の真下に部屋と部屋を区切るパーテーションは設置しない)その部の存在と親和性の高い、ちょっと非公式なイメージの活動場所である。
望美はそこで、ことさら存在感を出すわけでも、あえて埋没するわけでもなく、等身大で存在している。他者をひそかにジャッジしたり、空気を敏感に察知したり、マイルールを自身で検証したりしながら、わりかし平和に生息しているのだ。
ちなみに、この小説は高校(男女共学)が舞台でありながら、基本的に図書室以外は出てこない。舞台は高校ではなく、あくまでも高校の図書室&部室なのだ。そして、高校生同士の恋愛模様も表立っては描かれない。部員たちが、教室を避け(ているように見える)部室で長い時間を過ごす理由も一切語られない。
不登校になる部員もいたりするわけだが、そこに小説のテーマとしてはわかりやすい問題が仄見えたりはするものの、なにひとつ、明らかにはされないのだ。
傾向としてなんとなく、高校生活を無難にこなせる→図書委員 無難とは無縁→図書部員 というベクトルが成立しそうな感じがあるが、そういう決めつけこそ、書き手はなにより回避しているように見える。明らかにするより回避することで、より強いなにかが明らかにされる、というような手法とも違う、もっと、なんていうか「人間ってそうそう明文化できるもんじゃないじゃん」みたいな。
この小説に心打たれたのは、華やかでも、きらめいても、さほどイキイキとしても見えない部員たちの日々が、とても瑞々しく描かれていることだ。それは、目に見える輝きでも、将来、なつかしく思い出されるかけがえのなさ、みたいな種類ではないかわりに、そのときの自分の状況だけでなく心情までもが、丸ごとそのまま「在り続ける」ことを信じられるような水分保有量だ。
高校時代に図書委員だった自分がやっかむのは、この瑞々しさと、ベニヤ板で仕切られた部室の存在が、自分にはなかったこと。あったからといって、その価値に気づけたか否かは別として、この小説で描かれる、部室の中でひしめき合いながらも、軋轢をカンタンに表に出すことなく、それでも完璧に隠蔽するわけでもない高校生たちは、あまりにもリアルで愛おしい。
わたしはずっと、特に何もなくつまらない図書委員だった、地味でエピソードトークに事欠く高校生活だったのは残念、などと思っていた。バカだ。
そういう意味で、バカではまったくない望美がまぶしい。望美はかっこいい。そして、彼女に多大な影響を及ぼす、人を食ったような元司書の金子先生が羨ましい。
この小説を読んで、ベタなイメージの学校司書についつい憑りつかれがちな自分よ、さようなら、と言いたくなった。まだ言ってないけどさ。
by月亭つまみ