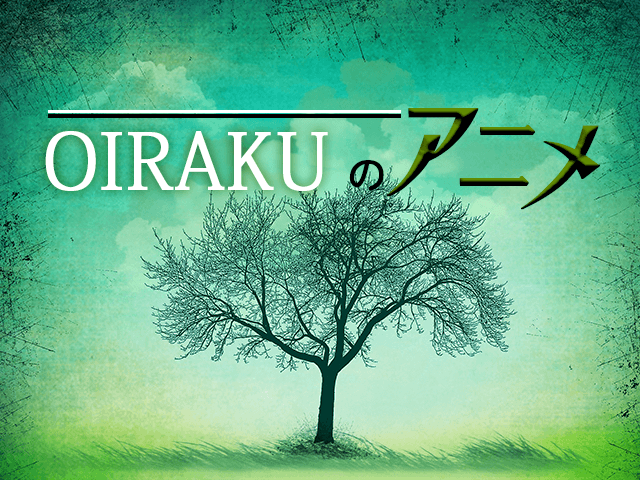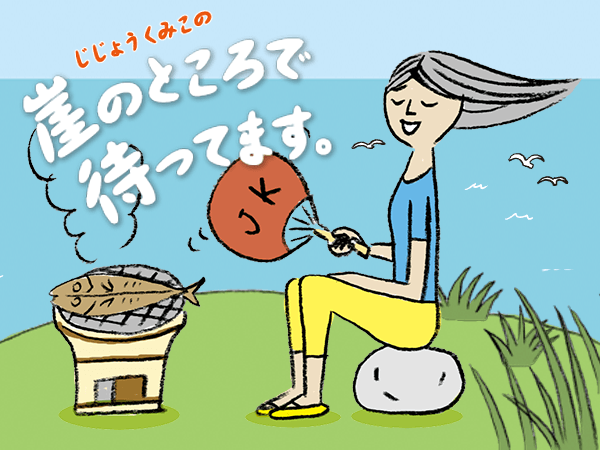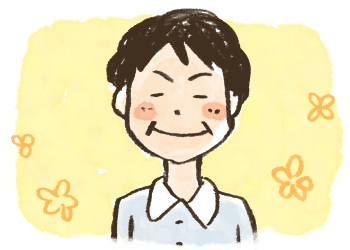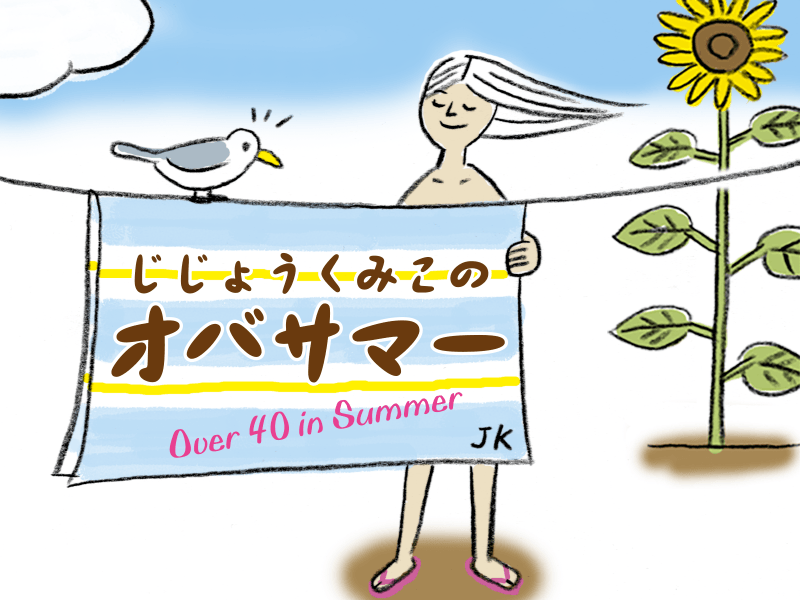【月刊★切実本屋】VOL.51 中年以降の高校生小説 犬編
感動を狙っているのが透けて見える小説は苦手だ。もっと言えば、着地点が最初から決まっていて、登場人物がそのための駒にしか見えないような小説には妙に臭覚が利き、文字どおり鼻につく。あっけなく術中にハマって、なんなら号泣もするくせに、感想は「好みじゃない」になることもしばしばである。
申し訳ないけれど、十年ぐらい前に出た『四十九日のレシピ』という小説は私にはそう映った。善良な人が誉めそうな小説だとは思ったが、その収まりのよさが、瑕疵の少なさが、私には瑕疵だった。もう細部は忘れたくせに、「伊吹有喜さんはもういいかも」と思ったことだけは覚えている。ちなみに、ずっと男性作家だと思っていた。
だから、「犬がいた季節」を読むつもりはあまりなかった。でも、高校が舞台で、本屋大賞で上位に入ったと知って、中学校の図書室での購入を検討するために、あらすじは読んだ。
舞台は三重県。捨てられた子犬が高校で暮らすようになる。「世話をする会」が結成され、生徒によってそれが引き継がれる。その係になった3年生の日々を3年間隔で綴った小説とのこと。昭和の終わりから平成の終わりまでの、その時々の流行や世相も描かれている…ふ~む、こりゃあ、そこそこいい話に決まってる!それはよくないのではないか(自分には)、と思った。
でもうっかり読んだのは、中学校の図書だよりで犬の本特集をしたことと、中学校の図書委員長の2年生女子が「いいですよ」と言ったからである。こう見えて私はけっこう素直なのだ。

結論からいえば、読んでよかった。
伊吹有喜さんは、小説を書くことに対して手慣れた作家ではないと思った、いい意味で。わりと不器用で、アナログな思考回路の人のような気がする。小説に対する自分の思いや書き方が、理路整然としたデータベースでなく、そのときの自分の状況や気分に左右されるので、手書きの、書き込みだらけのノートになっている感じというか…意味不明ですかね。

この小説の犬の名前はコーシロー。その語源(?)となった美術部の早瀬光司郎と塩見優花にスポットが当たった第一章は、光GENJIの曲が流れる昭和の最後の日々で、とにかくその展開に胸キュン(!)である。高校生活という、人生でも特別に輝いた、でも人によっては苦難や暗黒でもあったりする日々が、そのネガティブさも含めて、リアルというより、郷愁方面で感情過多気味に描かれている。
感情過多気味スタンスで始まったコーシローの18年間は、同じスタンスで終わっていく。ジュリアナ東京、SMAP、ノストラダムスの大予言、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件などの数々の世相や事件、そして数々の伏線を回収しながら。
折々にコーシローが語り部になった文章が挿し挟まれるのだが、胸に迫る。人が恋していることを匂いでわかるというのもいい。そう、犬は本当にこういうことがありそう、と、これまた感情過多で鼻がツンとした。特に、コーシローが別れを確信する、肉体に訪れるある現象のシーンでは、ツンどころではなく号泣。
というわけで、まんまとしてやられた。でも清々しい気分。読後感のよさもさることながら、この作者の狙っている感動が(あくまでも「狙っている」と言い張るのか自分)多面体だからだと思う。単に「いい話だった」ではなく、希望と、それと対になるちょっとした絶望に満ちているからだ。

この本を読んでから、高校のときのことをよく思い出している。戻りたいとは思わないが郷愁がすごい。そして、この小説を「いい」と言えるリアル十代がいることに驚き、同時にものすごく救われる気がする。
だってこれ、中年以降の人間にしか通じない言語で書かれてる、ぐらいに思ったから。
by月亭つまみ