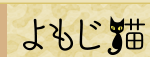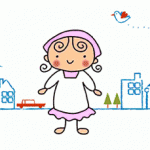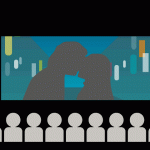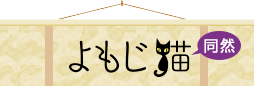Posted on 2024年9月12日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.85 〇〇室がない学校図書館勤めを希望
学校図書館で働くようになって11年目だ。その前に、専門学校の図書室に7年、公共図書館に約9年いたが、児童の担当には一度もならなかったので、学校司書になると決めたとき、自分で自分に「大丈夫か、おい」と思ったものだった。
大丈夫でもあったし、大丈夫でもなかった。それは今も続いている。
「大丈夫であった」のは、こどもと接することが概ね楽しいということに尽きる。「わたし、こどもが好きなんですぅ~」と表明するような人生は歩んでこなかったし、公共図書館の配属希望調査で「児童」と書いたことは一度もないので「どのクチが言う?」だが、内心では「おとなよりこどもとの方が楽しく話せるかも」と思っていて、おおかたそのとおりだった。
以前だったら「こんなことを言うと、こどもがいなくてわかってないからお気楽に『こどもが好き』って言えるのだと思われないだろうか」と躊躇したかもしれない。でも、そういうのはもういいんじゃないかと思う。加齢も悪くない。

後者の「大丈夫でもなかった」は、学校という組織に対する苦手意識がいつまで経っても払拭できないことがおおきい。なにしろいまだに朝、職員室に入るときは丹田に力を込めるクセが抜けない。そして、挨拶の回数(入室の際の一回でいいのか、カギをとるまで、そのへんにいる教職員にいちいち言うか)の正解がわからない。
学校図書館や読書が、教条的な方面に引っ張られることに加担するくらいなら、気の利かないうすらバカ司書と思われた方がマシだとも思っている。おおきなもの(読書=お勉強 的な考え)に持っていかれないために、ちいさなもの(軽度のおべんちゃらとか心の入らない感心)を日々目くらましに撒いておくことに対して良心が咎めたりはしない。とはいえ、ちいさなものでもチリツモなので、心は汚れていくわけで、「汚れつちまつた悲しみに今日も小雪の降りかかる」だ。こんにちは、中原昼夜問わずです、みたいな(意味不明にもほどがある)。

ふだんはそんなこんなでやり過ごし、整合性はとれないまでも基本的には楽しく働いているが、学校司書という職務に「正しい」意気込みを見せる世界(人や書物)に接すると、お尻のあたりが少しもぞもぞする。申し訳ないような、応援したいような、正論かよっと毒つきたいような、前言撤回して全面的に同意したくなるような、目を背けたいような‥。いろいろな感情が湧き居たたまれなくなったりしている。
『27000冊ガーデン』(大崎梢/著)は、まさにわたしをそういう心持ちにさせる物語だった。
舞台は神奈川県立高校の学校図書館。主人公の星川駒子はそこの司書だ。この人が、悪口の言いようのない方なのである。ちゃんとした人の定番で、やみくもにポジティブではなく、悩みもままならない気持ちもたくさんあって、それをきちんと描くこの著者の作品は、そういえばどれも読みやすいし巧い。元書店員だけあって本や出版に関する確かな認識を踏まえて、そこから「人を信じる」ことを描いてみせてくれたりする。『クローバー・レイン』なんて相当好きだ。が、今回の星川駒子さんはお友達になりたいタイプではない。スミマセン。

意欲、知識、向上心…そうか、学校司書ってこうあるべきなのかと、自分の日々のモットーみたいなものの浅はかさを思い知らされるのであまり至近距離にいてほしくないのかもしれない。でもそれだけではない。
学校司書は教師ではない、と表明する駒子の生徒への接し方がわたしから見るとけっこう教師っぽいのである。このニュアンスはちょっと説明しづらいが、わたしは、教師ではもちろんなく、さりとて無責任なオバチャンでもなく、迎合し過ぎず、安易に理解者ぶらず、正論をぶたず、私論を押し付けず、ご機嫌はとらず、友達ではないが気安く話せる司書でいたいのだ。なんて欲張りなんだろう。もちろん難しい。でも、最後まで達成できなくても心がける価値はあると思っている。
それはそれとして、連作短編ミステリーとしての『27000冊ガーデン』はどの編もなかなか面白かった。3編目の「せいしょる せいしょられる」は、胸が痛むある種の高校の現実が描かれているのだけれど、救いのある終わり方だった。そして、物語の中でたくさんの実在の小説が「お薦めの本」として紹介され、「とにかく読んでみて!」という駒子さんの、作者の、思いが伝わってくる。
自分がもっと若かったら、たとえ非正規でも毎日勤務の中学校か高校の司書になりたかったかも。そこに職員室がなかったらサイコー。‥んなところないよ!
by月亭つまみ