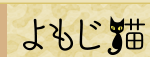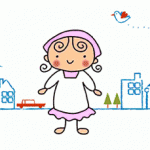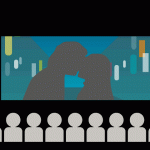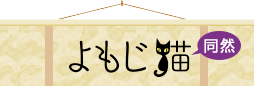Posted on 2024年11月14日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.87 かつての竹中直人の芸風の本
前田隆弘『死なれちゃったあとで』(中央公論新社)を読んだ。
この本の感想を書こう、そのためにはあまり時間を置かないようにしよう、なにしろ自分の毎日は常に「もの忘れイブ」だから‥などと思っているうちに時間が経ってしまった。案の定、読み終わった直後特有の熱と、なんならその後の余熱もあらかた冷めた。気がつけば平熱。付箋を貼ったり、メモをとりながら本を読むことはないので、ああ、これでライブ感のある(感想の)言葉を放出しそびれた!と思ったが、そこからさらに数日経ったらフシギな現象が起こった。この本に対する印象が変わったのだ。

『死なれちゃったあとで』は、友人だったり肉親だったり通りすがりに近い人だったり、その年齢にしては少なくない数の人の死に接してきた著者が、その経緯や気持ちを、率直な、でも感情過多にならない軽めの筆致で綴っているエッセイだ。
第一章の「針中野の占い師」では、著者の大学の後輩Dの自死について語られている。執筆時から遡ること20年前のことで、当時広告代理店勤務だった著者は、Dの元彼女Nちゃんからの電話でそれを知る。以降、現実の時間(20年前だが)と、Dとともに過ごした時間、そしてDの死に責任を感じるNちゃんが語る著者が知らない大学中退後のDのことが、「Dの死」という屹立する主軸はあれど、交錯し時空を行き来しながら20年後の今(執筆時)語られる。
この章の極めつけが、死んだDのポケットに入っていたメモにあった「情けない人生でした。」という言葉であることは、読んだ人のほぼ一致した見解だと思う。その一言が書かれた行を目にしたときは、一読者のこちらまで膝が崩れるような気がした。悲しみとか哀れという言葉では足りない、絶望というか無力感は、人間の存在の無意味さまで孕んでいる感じがした。どうしてそんな風にしか生きられなかったんだよと面識もないのにDの肩を揺さぶりたいような、でもその行為や衝動に意味はないし、そもそも自分がそんなことをしたいわけじゃないこともハナからわかっているような、やりきれなさと諦観が共存するような気持ちになったのだ。

やりきれなさと諦観は、この章で特に顕著だったけれど、どの章にも通じる、いわば著者の、死に対する認識の通奏低音だと思った。それがあるからこそ、文章のトーンをライトにしてバランスをとっていると感じたのだ。が、読み終わってしばらくすると、違うかもしれないと思うようになった。この本は、著者は、かつての竹中直人の芸風なのかもしれない、と。

著者は、飄々と時には笑いながら怒ってる、怒り続けている。それを持て余してこの本を書いたのではないか。通奏低音は、やりきれなさでも諦観でもなく怒りなのではないか。
Dも、溺死した父親も、通りすがりといっていい自転車の女性も、著名な女性ライターも、その死は遺された人を傷つける。だから著者は幾度も傷つけられてきた。でも、傷つけられたことが理由で、死者に対して怒っているわけではないと思う。どうしてもっと生きてくれなかったんだと悔しい気持ちになったにせよ、それが怒りを誘発しているわけではない気がする。それより、彼らを生かし続けることができずに逝かせてしまったこの世界に対して怒っているのではないか。もちろん、その世界には自分自身も含まれる。やりきれなさを感じるとしたらその部分のような気がする。

自分も身近な人の死を経験してきて思うのは、死はすべて理不尽だということだ。たとえ自死でも、平均寿命以上生きても、覚悟や受容する時間があったとしても、死は理不尽だ。遺される側にとっても。だから「死なれた」ではなく「死なれちゃった」なのではないだろうか。
最後に「種子島へ」の章があってよかった。陳腐な言い方だが「死を凌駕するのは希望だ」と思えたから。いい本だった。
by月亭つまみ