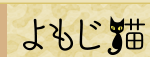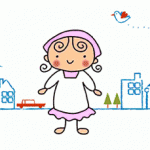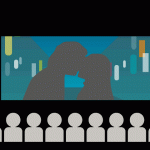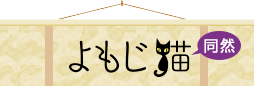Posted on 2023年5月11日 by つまみ
【月刊★切実本屋】VOL.69 A Place of Action
もがきながらも動こうとしている人間が出てくる小説が好きだ。ままならない日々に、くすぶったり逡巡した揚げ句、おもいきった行動に出る‥そんな姿がリアルに描かれていると、なんだか自分が肯定されるようでうれしい。若くなくなってもずっとそうだ。
だから『遠い空の下、僕らはおそるおそる声を出す』(野中ともそ/著)はドストライクだった。

物語の主人公、砂原 一葦(いちい)は16歳の男子だ。ニューヨークにちゃんぽんの店を出そうとする両親と共に、生まれ育った長崎を離れ、マンハッタンのダウンタウンにやってくる。レベルが高いとはいえない学校でもパッとしない彼は、極力声を立てず、目立たず騒がず、とにかくその日を生き延びることを命題にしている。中学時代も似たようなものだったし、とあきらめの言葉をちらつかせながら。
とはいえ、マーベルのコミックと映画が好きなおかげで、一葦にはいわゆるオタク仲間がいる。ハイチ系ドミニカ人で同胞意識の高いパンパ、破滅型ミュージシャンのジャコ・パストリアスを敬愛する頭脳明晰な韓国人のじゃこ、何をやってもイケていて天真爛漫に見える青い目のくじら。一葦は葦の英訳でリードと呼ばれる。
くじらの発案でバンドを結成しようとする彼らだったが、ひょんなことからアカペラコーラスを始めることになる。時は2020年2月、新型コロナウィルスが世界を侵食し始める頃だ。

瞬く間にコロナ禍で非常事態が日常になってしまった一葦の暮らしは平穏とは程遠くなる。いわれなき中傷、治安の悪化、家族の苦労と受難‥と息苦しい日々を強いられる。それでも、3人との音楽は一葦の活力の源になる。
並行して、彼の中学時代も描かれる。心を通わせた同級生の少女すぐりとのたどたどしくも瑞々しい日々。一葦にとって、率直で希望に満ちたすぐりはまぶしい存在だったが、すぐりの身の上に変化が起こり、ふたりの時間はフリーズしてしまうのだった。
すぐりに対する後悔を抱えたまま、それでもニューヨークで仲間と共に自分の居場所を見つけようとする一葦。それを邪魔するコロナ。コロナで助長‥というより、より可視化される差別や偏見。

小説、ノンフィクションという体の違いはあるものの、読んでいて幾度か『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(ブレイディみかこ/著)を思い出した。『ぼくは‥』が親側の視点から書かれているのに対し、『遠い空の下‥』は徹頭徹尾、十代目線だ。
十代目線のこの物語は力強くぐいぐい読ませる。特に後半。そこにSNS、line、ZOOMの役割は大きい。そして音楽。音楽が彼らの世界を牽引している。力づくではなく背中を押すように。
タイトルの「おそるおそる声を出す」の「声」は、一葦や登場人物たちだけのそれだけではなく、もっと広義な、人々の思いや希望などが幾重にも重なった集合体に思える。音楽小説の中でも、合奏小説または重奏小説。小説中に何度も登場する「A Place of Action」というキーワードに、一葦が自分なりの意味を重ねたように、声にも声以上のものが重ねられる、どうか重ねてくれ‥という作者の願いを感じた。
十代の成長小説のいいところは、小説が終わっても、物語はそして世界は続いていくのだ、とふつうに思えるところだ。今回は、読み終わってからもしばらく自分の脳内には「スタンドバイミー」が流れるというおまけつき。
悪くない余韻だ。
by月亭つまみ